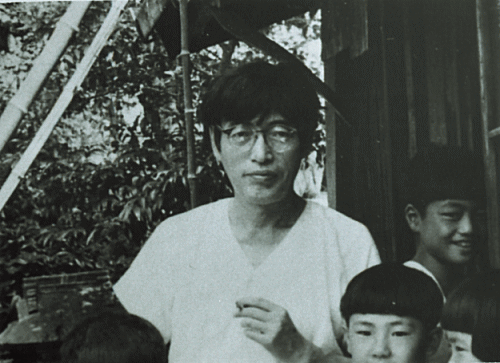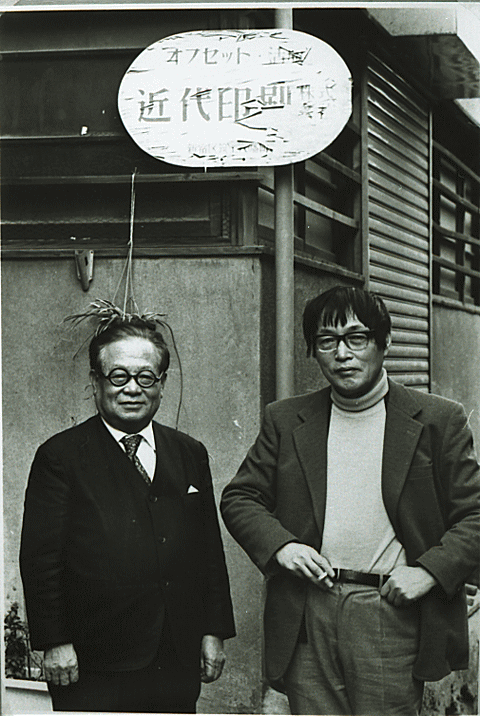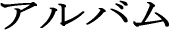 |
| (文 森富子) |
| Part 2 |
|
 |
| 東京の雅叙園で結婚した森敦と妻・暘 |
昭和16年5月のことで、森敦29歳、暘23歳。「横光(利一)さん夫妻の媒酌で式は盛大なものとなり、菊池(寛)さんのきもいりで新婚旅行の宿は、文藝春秋社から玉木屋旅館をとってもらいました。」(「わが妻 その愛」)
|
 |
| 富岡光学機械製造所雪谷本社にて、昭和17年ころ・30歳前後の森敦(左端)。 |
結婚を機に、初めて勤めた会社で、若くして製造部長になった。この会社で特にレンズに興味を持ち、放浪の間も考え続けて、のちに、「リアリズム一・二五倍論」などを書き、『意味の変容』を著して、独自な構造論を展開させた。
|
 |
| 昭和31年5月20日、酒田祭の日に大成丸を見学したときの森敦と妻・暢(右の二人)。 |
結婚当時は東京の雪谷に住んだが、昭和20年の終戦で富岡光学機械製造所が解散となり、酒田市に移り住んだ。「酒田市から庄内平野を過ったバスがようやく山あいにはいり、行きどまると吉ケ沢というむらがある。阪神の住吉に育ち奈良市で会った女房の里が、こんなところにあるとは知らなかった」(「私の風土記」)。妻の故郷が山形の庄内にあったという縁で、吹浦や酒田、狩川、加茂、湯野浜、鶴岡、大山、朝日村・七五三掛などに移り住んだ。長く庄内平野を転々としたときの体験や見聞が、小説『月山』『鳥海山』『われ逝くもののごとく』などの代表作を生む礎となった。
|
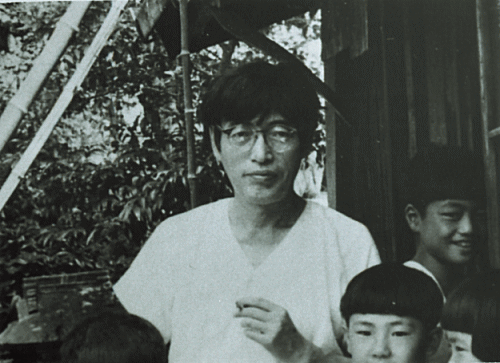 |
| 放浪最後の地、鶴岡市大山での森敦(昭和37年・50歳ころ)。 |
「わたしは加茂というさびれた港町にいて、ようやく夏になろうとするころ、この庄内の大山という町に来た」(「光陰」)のだが、「庄内平野の町々、村々を転々としたことにわたしの生涯があるとすれば、ここはわたしの生涯が一望のうちにある」(「吹きの夜の想い」)と思い、大山を舞台に短編小説「光陰」「吹きの夜の想い」などを書いた。
|
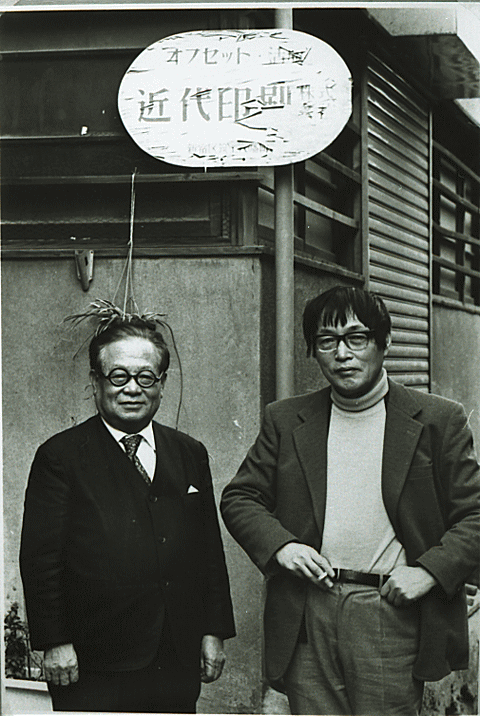 |
| 最後に勤めた近代印刷の前で、社長の小山恵市氏(左)と森敦。 |
| 昭和40年1月上旬、大山を後にして上京、同月22日の誕生日で53歳となった。東京・東府中市の借家から、都心の飯田橋にあった近代印刷に通った。毎日毎日、日曜日も祭日も、朝早く起きて始発電車に乗って、山手線を何度も回りながら、俳句手帳やゲラ用紙に原稿を書き続けた。それが『月山』『鳥海山』『意味の変容』などの作品となった。 |
| ↑ページトップ |
| アルバム一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |
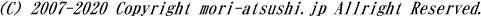 |