| (文 森富子) |
| Part 4 |
|
|
 |
| 岩下志麻さんと対談した森敦(昭和50年・63歳) |
| 「週刊女性」(昭和50年4月8日号)連載の「志麻対談」最後のゲストに招かれて対談したときの写真。これをしばらくの間、書斎に飾って、来訪者にうれしそうに話していた。
|
 |
| 書斎にしていたアパート(調布市布田・やよい荘)での森敦。 |
| この写真は、昭和50年5月18日に、二村次郎氏が撮影したもの。 「ぼくは四畳半に二畳の汚い木造モルタルの二階にいる。毎日送られて来る郵便だけでも相当の量なので、たちまち身の置きどころもなくなる。いきおい、隣りも借りれば階下も借りて行かねばならぬ始末になった……。窓を開ければコンクリートの壁越しに孟宗竹が茂り、それが彼方の道路の騒音を防ぐのか、駅の近くにありながら意外に静かで、この点だけはだれもがこの借景を褒める。」(「借景の効用」) |
 |
| 昭和56年8月28日、朝日村七五三・注連寺に建った文学碑の除幕式にて、 森敦(69歳)と娘・富子(左端)。 |
| 「注連寺の境内に、ぼくの『月山』の文学碑が建った。幅3・5メートル、高さ2・5メートル、16トンもある巨大な自然石で、月山と大書し『すべて吹きの寄するところこれ月山なり』と刻し、別に黒い磨き石を建てて、この文学碑を建てたゆえんが記されている。…… 8月28日、その日は晴れてはいなかったが、月山がよく見えた。文学碑には和紙でつくった白い蚊帳がかぶせられ『天の夢』と大書されている。……祈祷が終わると除幕式である。ぼくと娘が左右に分かれて紐を引いたが、除幕式とはいいながら、『天の夢』と書かれた白い蚊帳は、高くつり上げられて、天空に舞っているのである。…… 8月28日はぼくにとって忘れ得ぬ日になったが、朝などふとあの巨大な自然石が、ひとり建ってやがて冬を迎えるのだと思い、なんともいえぬ気持ちになる。それはまさにぼく自身が、そのようにあり、またあらねばならぬという実存の厳しさを感じさせられるからかもしれない。」(「吹きの寄するところ−朝日村に建った『月山』文学碑」) |
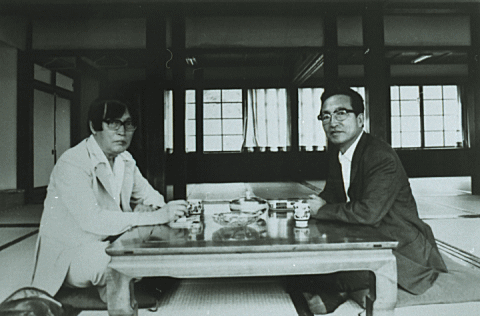 |
| 昭和56年9月4日、注連寺にて、対談中の小島信夫氏と森敦(69歳)。 |
| 雑誌「文藝」に、昭和56年6月号から翌年の5月号までの一年間、「文学と人生」と題して、小島信夫氏と長編対談をした。いつも東京・市谷田町の森宅でしていたが、第6回目は『月山』の舞台となった注連寺の二階に場所をかえて対談した。写真に映っている注連寺の二階は、森敦が蚊帳をつって一冬過ごしたところである。 「小島さんとはじめて会ったとき、小島さんは黒縁の丸い眼鏡を掛けていた。おや、わたしとおなじ眼鏡を掛けているな、と思った記憶がある。ぼくはなにごとにつけ、年月日だけは超越したいと心掛けていたから、それがなん年前のいつのことだったか覚えていない。…… ぼくは鳥海山の麓の吹浦という農漁村に移った。農漁村といってもぼくがその二階を借りた家には庭もあり、建て方もしょうしゃだった。小島さんはそこにもよく来てくれた。小島さんが来ると女房も喜び、一緒によく松かさを拾いに行ったり、流木を取りに行ったりした。遥かに飛島を見る美しい日本海も、しだいに冬の気配になって来たので、酒田に移った。……もちろん、そこにも小島さんはよく来てくれた。」(「小島さんとのこと」) |
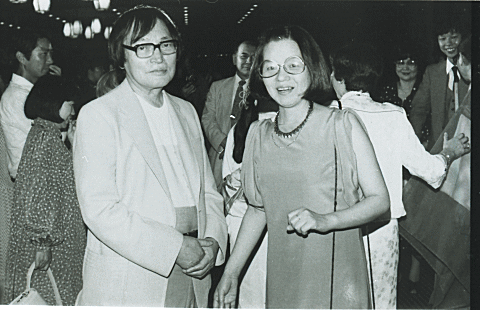 |
| 昭和57年6月17日、東京會館での、高野悦子氏の『シネマ人間紀行』出版記念会にて、 森敦(70歳)と娘・富子。 |
| 「夜、九時を回ったと思うころ、表にタクシーが止まり、やがて走り去る音がして、『メリー』と娘が向かいのお屋敷のセパードを呼ぶ声がする。娘は大手の教科書会社に勤めている。…… 娘は血を分けた娘ではない。しかし、こうしているとほんとうの娘のような情が湧くばかりか、なまじ血を分けた娘よりいいと思うことがある。…… 『お父さんだって、暗いうちから起き上がって、電車の中で書いていたじゃないの。あのころは、郊外のアパートだったから、わたしたち閉口したけど、いまとなってはとても懐かしいわ』 わたしたちとは、亡くなった女房のことを含めて言っているので、娘は女房と姉妹のように仲がよかった。」(「日記から」) |
| ↑ページトップ |
| アルバム一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |