| 017 鰻への想い |
| 出典:翰林選書 横光利一と宇佐 平成5年10月30日 |
| 父森敦が「横光さんがね……」と話し出すときは、いつも嬉しそうな表情をした。 「写真の顔もいいが、実物はもっと素晴らしかった。こうして、蓬髪を掻き上げるんだ。あの恰好はよかった」 と、横光さんの蓬髪を掻き上げる仕種を真似た。 前髪が眼鏡の上にかぶさるのを見かねて切ったのが始まりで、以来、私が森敦の床屋をするようになった。プロの道具を使い、手つきを真似しても虎刈りになった。 そのころ、宮城まり子さんに請われて、ねむの木学園に行ったことがあった。子供たちがワーッと寄って来て、 「森さんの頭は、僕たちと同じ、虎刈りだあーッ」 「そうだね。誰に切ってもらってるの?」 「おかあーさーん」 子供たちにとってまり子おかあさんは神様のようなものである。よく見ると、子供のそれぞれの顔だちに合ったヘアスタイルになっているのだがどの子供も虎刈りだ。 「一列に並んだ子供たちを次々に切っていくので、虎刈りになってしまうのよ」 と、まり子おかあさんが子供の頭を撫でて笑った。 森敦は、虎刈りについては何も言わなかったが、いつも「短く切るんじゃないよ」と言った。ところが、毛先を切りそろえているうちに、気がつくと短くなっている。あるとき、短く切りすぎてカッパの絵にあるような髪形になったことがあった。 「目が覚めたら、カッパじゃないか」 と、前髪に手を入れて、あの蓬髪を掻き上げる横光さんの真似をした。 「またすぐ伸びるわよ。今日の理髪代は、タダにしてあげる」 それから前髪に鋏を入れるときは、居眠りをしていてもパッと目を開けて言うのだ。 「短くするんじゃないよ」 カッパに懲りて、眉毛にかぶさるくらいの長さに切れと言うのだ。そのとおりに切ると、すぐさま前髪が眼鏡にかぶさってくる。忙しくて月に一度の床屋がやっとだったので、説得して眉毛の山が見え隠れするくらいの長さに落ち着いていった。慣れるにつれ、前髪の長さの攻防も穏やかになり、気に入った形に仕上がると、 「今日のお代はいくらだい?」 「そうねえ。五万円にまけておくわ」 「そうかい」 と、薄くなった前髪を掻き上げて、横光さんの仕種を真似た。 私は床屋をする度に、森敦の、横光さんへの想いの並々ならぬ深さを感じた。初めは遊び心で理髪代云々したが、その想いの丈に気づいてからは、理髪代の数字を問われる度に、横光さんへのその想いの丈を推し量って、七万、十万と数字がエスカレートした。 その横光さんへの想いは、日常の中で形を変えて様々なことに現れていた。 あるとき、勝手の分からない土地で、鰻屋を探しながら、嬉しそうな顔でこう言った。 「横光さんが鰻屋に入る前に、まずいなら皮を残せ、と囁くんだ。皮はまずかったという、鰻屋への無言の言葉なんだそうだ。ところが、横光さんはいつだって皮まで食べていたなあ」 森敦はいくら食べても飽きないほど鰻が好きであった。神楽坂の「たつみや」の鰻重がひいきで、近くの印刷屋に勤めていたころは知人友人と連れ立って、毎日のように通ったという。 森敦が横光さんの鰻について書いた「鰻のハシゴ」(「朝日新聞」昭和五十八年七月二十三日夕刊)の最後の部分でこう書いている。 《横光利一はぼくにとって、大恩の人である。横光さんは大の鰻好きで、文壇にデビューしたとき、原稿料を全部使ったという。鰻丼(どんぶり)に囲まれて、なお鰻丼を食っている漫画を見たことがある。ぼくはたいへん可愛がられていたから、毎夜のようにいろんな店に連れて行ってもらった。鰻屋もむろんである。しかも鰻は鰻丼に限るという。ある夜、鰻丼をとって鰻を食べ、飯にかかろうとすると、飯はよせと言われた。もう一軒行くのだとのことでついて行くと、驚いたことにまた鰻屋にはいった。この話をよくするのだが、鰻のハシゴは聞いたことがないと言って、だれも信用しない。その癖、面白がって笑うのである。ぼくは懐かしくおもいだして、洒盃(しゅはい)を傾ける。蒲焼にはやはり日本酒がいいようだ。》 ついでに、森敦のいう《横光さんは大の鰻好き……》が本当の話だという証拠を、横光さんの書いたもので示したい。「私が初めて得た原稿料」のアンケート(「定本横光利一全集第十六巻」)に答えたものである。 《鰻を食ふ/最初の原稿料は日輪を出したとき、二百円。鰻ばかりを食べ歩いた。一ケ月で二百円鰻を食べて、下宿料が払へなくなつたのを覚えてゐる。》 森敦の大の鰻好きも横光さんの導きなのである。その鰻に寄せる想いの丈の深さは底なしであった。体調をくずして、何度か飯田橋の厚生年金病院に入院した。病院食をつまみながら、きまって私にこう言うのである。 「鰻を食べておいで」 厚生年金病院から神楽坂の「たつみや」まで歩いて五分でも、注文してから作るので食べ終わるまでたっぶり一時間はかかる。満腹になって病室に戻ると、さも自分が食べてきたかのように、ニコニコ顔でこう言った。 「美味しかったね」 森敦の導きで、私も鰻大好きになっていたので、毎日のように「鰻を食べておいで」と言われても、喜んで「たつみや」に通った。 死の直前ころは、鰻を食べたい気持ちを込めて、こう言うのだった。 「ぼくの代わりに、鰻を食べに行ってくれないかなあ」 食べて戻った私に、森敦は弾んだ声でこう呟いた。 「本当に美味しかったなあ。あそこの鰻はいつ食べても、うまいよ」 森敦の死して後も、私は「たつみや」で鰻を食べながら、森敦の身代わりのような気分で鰻を食べ、横光さんへの想いにひたっている。 |
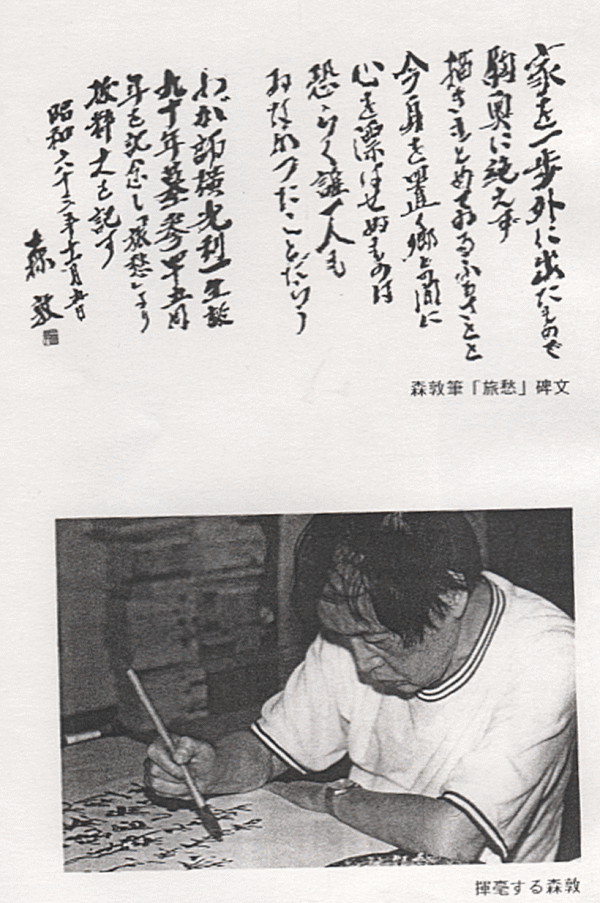 |
| ↑ページトップ |
| 娘・富子のエッセイ一覧に戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |