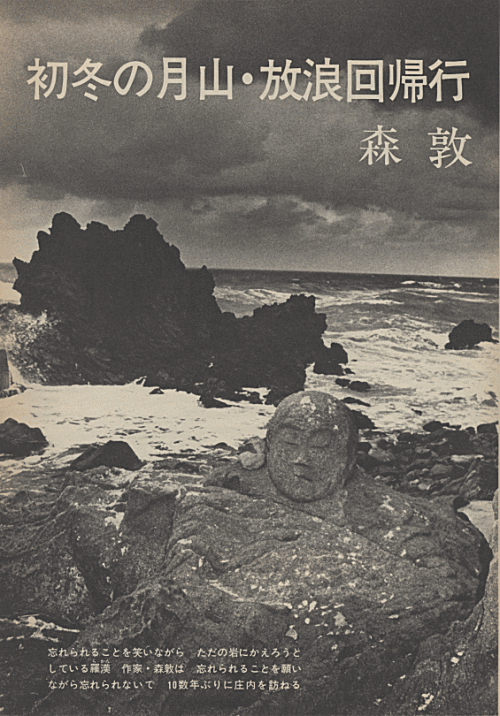


|
「月山」が芥川賞を受賞し つづいて「鳥海山」を書いたのに なぜか森さんはこれまで一度もここを訪れようとしなかった。
それをたずねると こんどの回帰行の思いつきの奥にはまるで触れないで 鳥海山と月山とその山ふところに抱かれた庄内平野 そして日本海を ただ語りつづけるのだった。
「ここにいたときは東京が夢か幻のように思えていたが ここまでくると東京が夢か幻のようだなあ」
海鳴りと対決するように大きな声で叫んだ。やっぱりこの人は ここがなぜか好きなのだ。烏が一羽 流木にとまった。森さんは小さな声でつぶやいた。
「日本海には烏が似合うなあ」
|
「大物忌神社のほうへいってくれませんか」森さんの注文で 海岸から山のほうへ行った。神社の角を曲がったところで 品のよい老婆をみつけた。森さんが車からころがるように降りて その老婆の手をにぎった。「おぼえてますか」「ンだ 森さんじゃろ 二階におっだ」「ンだ ンだ ばさまも元気だの」「ンだ わがくなったち(若くなリましたね)」
岡田さんのばさまで 森さんはこのばさまの家の二階に一年半いたという。ばさまはいま八十四になったとしきりに主張した。
「あがっで茶ァ飲んでげ」というばさまの手をふり切って また車を走らせた 森さんはウインドーからたびたびのり出して山をみる。鳥海山は その頂をいつも雲にかくして全容をみせてくれない。お互いはにかんでいるようだ。
|
「あの冬はあのたきぎで足りましたかの」
「おお 足りたよ 十分足りたよ」
二人は二十三年も昔のことを去年の冬のことのように話した。それが少しもおかしくなかった。
賢章さんはいまえらくなっている。酒田市にある海向寺の住職で 名も永恒と変えていた。
賢章さんもいっしょに注連寺を訪ねた。注連寺のある朝日村までの途中は すっかり道がよくなっていた。賢章さんは 道路が近代的になってしまったのがすまなそうに この道はついこの春完成したのだといいわけしていた。道路の左側に赤川が添ってくると 賢章さんは「月山」の一章を暗唱してくれた。
「赤川をさかのぼって落合で大鳥川と別れると 赤川は名川と呼ばれてようやく渓谷の様相を帯びて来る。この名川をさかのぼって大網に至り七五三掛の渓谷と別れれば 名川は更に梵字川と呼びかえられ……」
賢章さんはガイドもかねて 同乗者に聞かせてくれたのだった。月山の山すその紅葉は 狂わんばかりに赤く美しかった。
|
源助のばさまも ずしょのがが(嬶)も 与兵衛のじさまも 与吉のばさまも 立花のだだ(親父)も 亀さんも亀さんの野郎ッ子も 観正院も清京院も芳吟院も和光院も そして清蔵院も宝泉院も……。
ばさまは重箱や買物かごをかかえて じさまは一升びんをぶら下げている。
賢章さんが吹浦のある遊佐町の役場から情報をキャッチし 森さんがくることを連絡していたのだ。“寺の森さん”の大歓迎会が計画されていたらしく 寺の坊は宴会場に早がわりした。この坊で森さんは和紙のカヤをはって冬を過ごした。みんなが去年の冬のことのようにその話をはじめた。
ずしょのばさまは寺の森さんに気があった 寺の森さんはカンジキを逆さにはいて笑った あの野郎ッ子は寺の森さんのタバコを買いに雪の中を走った。
寺の森さんはヤギ(七十度近い自家製の地酒)を飲みすぎて 髪の毛が逆立ちして大騒ぎした……。
じさまもばさまも 森さんもだんだん酒がまわって 七五三掛の人がいっている言葉は 他国者にはさっぱりわからなくなった。
薄暗やみの中で 頂に雪をいただいた月山が 雲のかけらもかぶらずそびえていた。
文/山崎れいみ