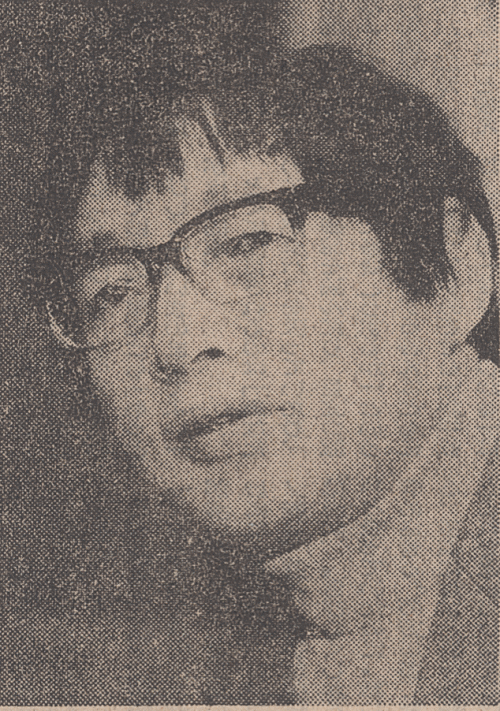
しかし二十代作家の出現の前はかなり長い間、中年か初老の新人ばかりが登場すると、文学の命脈を気づかうような声がつづいていた。それが、初老どころか、戦前横光利一に師事し、新聞連載小説を書いたことさえあるが、その後ぷっつりと消息を断っていた六十歳の老人が、どこに隠れていたのか、ひょっこり姿を現すなり、賞をさらってしまったのである。みなが唖(あ)然とするのも無理はなかった。
せっかちで粗雑なジャーナリストは、日本文学が未来への道を失い、過去の古めかしい風土への逆戻りするきざしではないかと心配して見せたりした。だが、作家にとって肝要なのは、いうまでもなく肉体の年齢ではなくて精神の年齢である。森は若くして文壇を離れてから、土木工事などに関係して日本各地を転々としていた。東洋流の遁(とん)世、聖(ひじり)の漂泊といった印象を与えなくはないし、事実、「月山」は、東北の雪の山の古寺にこもった一冬の記録いう素材からして、古風な心境小説めいた感じを呼び起こしもするだろう。しかしそれは外見だけの話である。
むしろここにあって、作品を深い所で支えているのは、そうした素材の輸郭をはみだして、生と死との関連の暗い不思議さを問いつめようとする、精神の運動なのである。その運動は、およそ、達観した老年の淡々たる心境などというものとは縁がない。
「月山」は、冬の山村のさまざまな奇妙な風俗や自然現象を描いているようでいながら、その精神の運動の進むにつれて、全体として、一つの死の世界、地獄の相をあらわにしてくる。月山を中心とする出羽三山は、本来、そこへ生が回帰しそこから生がはじまる死の霊域だが、この霊域の秘密を、地獄めぐりに耐えうるほど強い精神なればこそ探ることが可能だったのであり、そしてこのような強い精神は、本質的に若々しいというほかはないのである。
「月山」以外の森の作、短篇集「鳥海山」に収められた諸篇は、前者ほどの緊張をはらんではいず、よりおだやかな、のどかな趣があるけれども、しかしそこでも、生と死の循環を見据えようとする心の眼の動きは鈍っていない。生は死の仮相であり、その双方を一気にとらえることによって、世界全体の実相を直観するという、いわば、神秘哲字的な志向が、一見のどかな作品風景の背後に息づいていて、それが作品を、不気味に、しかも親密にゆらめかしている。
このところしばらく森は、作品を発表していない。回想風な交友記とか、思索的なエッセーとかは、それぞれ味のあるもので、また、文芸誌の座談会形式の時評の常連として、軽妙でもあり深遠でもある座談の名手の面目を発揮している。文学への観念の深さはそうした仕事の随所にひらめき出ている。ただ、「月山」に心をひきつけられた読者なら、その観想を集中して、もう一度、力のこもった作を読みたいと願いたくなるのも自然ではあるまいか。別の重要な漂泊地である「尾鷲」を書く用意があると聞けばなおさらのことである。
(竜)
(明治四十五年長崎市生まれ。旧制一高中退。著書「月山」「鳥海山」「文壇意外史」)