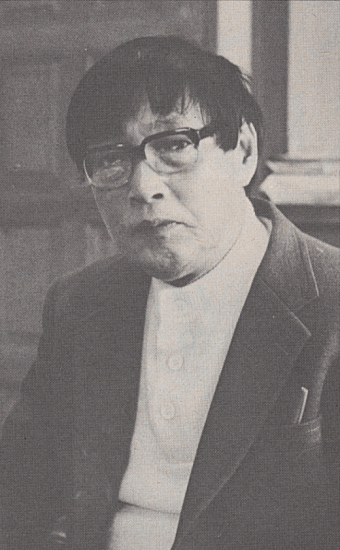
“粗製乱造”、“責任転嫁”の当世ですが、“訪れてくれるもの”を大切に、実が熟れるのを静かに待たれる先生のご日常には、私たちとて、生きているうちにもう一度思い出しておかなければならない何ものかがあるような気がするのです。
|
今日までに、あいにく月山へ行けなかったので、二度目の映画(『月山』)は、詳しく地形を調べてから、月山や鳥海山の形状だけは見落とさないようにと思いながら見てきました。
森 わかりましたか。
──ええ、と申し上げていいかどうかわかりません。正直のところ、おそらくという気持なのですが……。結局、今日は、それでお伺いしたようなものかもしれません。ただ、ハッと思うようなものはあったのです。
森 それはどういうようなことですか。
──先生が、ご本の中で、山へ入ったと思ったら谷で、谷だと思ったら山になっていて、ひとりでに谷で、また奥に山があるというふうに書いておられたあたり。さらに、先生が遠くでごらんになった山、また谷を分けてかなり奥へ進んでも、やっぱり同じように奥のほうに丸い、まどかな頂が見えるというあたり、ものすごく不思議な気がしましてね。
森 そうです。奥深い渓谷でも遠くから見たのと同じ形の山を見たわけです。たいてい、普通の山というのは、山の中に入ると形が変わるんですよ。それが全然、微動だにせず、あまり変わらないで、同じような形に見えみわけですよ。
──不思議ですね。
森 つまり、一番高い峰の部分だけについていえば、その近くに寄ると、おそらくこの部分しか見えないんだろうと思うけれども、この部分がまた遠くで見た月山の全景みたいに見えるわけです。
──稜線の全体の変化と部分の中の変化が相似的になっているんですね。おまけに、招き込むような地形です。ですから、部分が見えても全体を見ているように思えるわけですね。なにか、先生の「月山」を暗示しているような気がするのですが。
森 私が三十代のころ、かなり長い間、庄内平野に住んでおり、いつも月山や鳥海山を見ておった。あるとき、肘折の渓谷に行ったときに、部分が全体にみえることから、突然、ハッと思った。華厳経にあるとおりなんですね、月山が、まさしく。
──華厳経とは華厳宗の?
森 私は二十代の初めから、かなりの間、東大寺にいたのです。東大寺は華厳経による華厳宗で、その華厳経の中に一つの物語があります。蓮の葉っぱの上に玲瓏玉のごとき朝露が転がっておる。玲瓏玉のごときものだから、四方八方の世界を全部映し出しているというんですよ。四方八方全部映し出している以上は、その小さな露の中にも全世界があるからにちがいないというわけです。それが映ったといってもいいし、中にそういうものを蔵しているといってもいいですね。
──それは、こういうふうに考えてもいいですか。広い天地の中にある蓮の上の露という無限の大きさに対する小さい小さい部分、そんな小さな小さな部分である露に、それを取り巻く無限の全世界が写っている。他のものはいっぱいあるのに、その露だけが全世界を写している。それは露の側に何かがあるからであって、つまり、すべてはこちら側にそのもとがあるという……。
森 こちら側に内なるものがあり、宿しているものがあるから、そういうふうにみえる。だから、ちょうどゲーテが「君はどうして花を美しいと思うのか。それは君の心の中に美い花があるからだ」と詩った、それと同じ発想なんですね。
──美とか愛とかの世界ですね。
森 ええ。みんなそうです。こちら側にあるんです。だから、どんな部分にも、こちら側に見る力があれば、全体が見える。
|
で、十年以上も経って、月山で、部分に全体を見られたとき、奈良でのご体験と出会ったのですね。
森 そうです。「アーッ」と言って、しばらくぼうぜんとして眺めておりました。
月山は華厳経だったんですよ、実に!
──十年の時間と空間が、先生の中で一つになったのですね。その時から先生は、あの小説「月山」をお書きになろうと……。
森 いやいや、その時は夢にも考えていません。その時はただ、そう思っただけです。あのころの十年間は、庄内平野を転々として遊んでおりましたから。ただ、あの時『月山』は生まれるべく宿ったんですね、今考えてみれば。
──で、「月山」はどんなふうにして世に出たのですか。
森 ぼくは一高時代に、すでにものを書いていましたから──このころのことは、ぼくの「星霜移り人は去る」(角川文庫)にありますが──だいたい奈良の東大寺も、そんな関係の招きがあって行っていたのですが……。
文章の注文はあったのです。ただ書く気が起こらなくて、注文にも知らぬ顔をしていたんです。
ぼくは今まで、十年がむしゃらに働き、十年遊ぶという生活をしてきましたが、六十近くなって、ちょうど「月山」を書きたくなっていたんですね、きっと。そこへ友人のすすめがあって書いたというわけです。
──だから、世に「四十年の沈黙を破って」などといわれるのですね。あれは会社勤めをされながらお書きになったとか。
森 そういうことですが、だいたい昔、庄内で月山を見て「華厳経だ」と思ったときに、今考えると、あの「部分が全体」という感じがきまっていましたから……。
──先生の作品は、どこの部分、どこの一行をとってみても味わいが深いですね。心の中で口ずさんでいると「月山」があるんですよ。深夜、寝床の中で、外に月の出てくるような気配のするときなんか、枕元の「月山」をどこでもいいからあけて、一行か二行だけ読んで、空をみていると、湧いてくるんですね、“月山”が。
森 そうですか。それは……。そういう読み方をしてくださると……。
あれ、語り調で芝居をやるといいのです。
──やはり、二十年もの長い間あたためてお書きになったから、どの一行にも無限の時間と空間が宿っている。そういうものはめったにありません。
森 だから、リルケが言っていますね。作品をつくるということは、妊娠をして、そして出産をするのと同じだ。静かに、種が自分のお腹の中で熟するのを待って、そして出産をするのを待つよりしようがないんだ。それ以上の無理なことをしたって本当の子供にはならない。つまり作品にはならないんだってね。ぼくはそういう洒落たことは思っていなかったが、結果としてはやはりそれと同じような結果になったんじゃないですかね。だから待っていたというようにみえるかもしれませんね、機の熟するのを。
──そうなんですね。
森 そして、ひとりでに花が咲き、実をつけたというようなことになるんじゃないでしょうか。
──ああ、先生、思い出しました。「鳥海山」の中の「鴎」の中で、先生が鳥海山のふもとの吹浦の海岸で奥様と松ボックリを拾われているところでおっしゃっていますね。
「松笠はね、みずからの充実において静かな日に落ちるんだ」と。
あれお読みしたときに、なにかすごく象徴的な感じで、ズーンときて、先へ進まないで、そこのところを何回も読んで想っていたのです。
今、先生のお口から、作品というのは自然に生み落とされるのだ、ということをうかがって、あのとき、あの短い会話の中にも、先生ご自身がおられるような気がしていたのですが……。
感激です。なにか、とても。
森 そうです。「どんな風が吹いたって、それで青い実が落ちるということはないんだ。熟してきて、その日がくれば、ある日ひとりでに落ちていく」──。
|
──奥様とのことを……。
森 ええ。ぼくが家内のことを書いたただ一つの作品です。
庄内平野を家内と転々としていたころ、鳥海山のふもとの吹浦にいたときのことを、ずっとあとになって書いたんです。ぼくの鎮魂歌なのです、あれは。
家内は逝く少し前、病床であの最初の原稿をみています。
「鴎」を本にしようと思ってふん切ったのは家内が亡くなってからです。生きてる時は、私のことは恥ずかしいから書かないでくれと言っていたんですが、どうしてもあれだけは書いておこうと思ったわけで、書かなければいられなかった。
ぼくはわりあいに幸福な結婚生活をしてきました。家内と。どこへでもついてきてくれましたから。ちっともいやな顔をしなかった。十年働いて十年遊ぶというようなぼくに、お金がないとも言わなかったし、何とも言わないで黙ってついてきてくれたから、それだけに、逝ってしまうと、心の荷が重たいのですよ。
──あの作品。すごくすきとおっていて、ひとりでに涙が出てきてしまうほどです。悲しいとかなんとかではなくて……。あ、先生、先ほどリルケのことをおっしゃいましたが、リルケの詩なんかに、最後の一行でジンときてしまうようなのがありますね。
音楽でも、ときどき、そういうのが……。
森 ……。
……よかったら、ちょっと聞いてみませんか。ここに「鴎」があるんですよ。
(応接の中央のステレオを開けると、テープがセットされている)
電通の新井満さんが唄ってくれたんです。ギターで、ぼくの鎮魂歌を。
──……それは。ぜひ。
(テープ始まる。唄では会話の都分が一部リフレインされている。ここでは「鴎」の最終部分を引用)
| 「堤防へ?」 ぼくもそちらに目を返すと、堤防は波のしぶきが上がって、小さな虹が無数に舞っている。行けばそれなりさらわれてしまいそうなのに、人生をただぼくについてここまで来ただけのような女房が、「ええ。いまはきっと、満ち潮なのよ。待ってて。わたしが拾って来るから」 恐れげもなくムギワラ帽を首のうしろに、髪をなびかせながら走って行くのです。ぼくも行こうとすると、ぼくはもう羽風を切って寄ってきた鴎の群れの中にあるのです。ぼくは一瞬、ぼくが鴎になったような気がしましたが、不意に女房が「鴎になった!」といった言葉を思いだしました。そして、いまもまた両手をひろげて、波のしぶきの無数の虹の中へと走って行ったのを思い出しました。 ハッとして立ち止まると、鴎の群れが羽風を切ってやって来て、ぼくはふたたび鴎の中にあるのです。 「楽しかったわね。わたしたちはたとえどこに行っても、またここに来ましょうね」 「わたしたち? きみが人であることをやめたら、どうしてまた来ることができるのかね」 しかし、また鴎の群れは去って、なんの答えもありません。 「わたしたち? 」 きみがもし、ぼくをひとり残して、鴎になってしまったのなら、どうしてもう「わたしたち」などと言えるだろう。ながくただぼくについて、ここまで来たとしか思わなかった女房が、じつはそうした女房あるがために、ようやくここまで来れたのを知ることの、あまりに遅かったことに及ばぬ後悔をしていると、また羽風を切って鴎の群れが来、やさしい声がするのです。 「そのときも、きっと若い人たちがバドミントンをやったり、アコーディオンを楽しんだり、賛美歌を歌ったり、子供たちを集めて、イエスや使徒たちの紙芝居を見せたりしてるわね。楽しかったわ、本当に……」 |
それこそ、蓮の露ではありませんが、“月山”が見えたときのような気持になります。
森 どうぞ、何でも聞いてぐださい。
|
森 訪ねて来たのです。初めは女房の母が私を気に入ってくれて、娘を、と。
奈良では何も働いていませんでしたから、よほど私という人間を信頼してくれたのでしょう。正式に結婚したのは、それから七、八年後、東京でですが。奈良で約束しましたから、むこうもそれを信じていたんですね。やはり訪れて来てくれたんです。
──先生の作品を拝読しますと、“訪れてくる”ということに大変な意味をおいておられるような気がするのです。
「鴎」でも、突然訪れて来たSという人に、あなたが来てくれたお陰で、こんな気持でこんなすばらしい鳥海山が見られる、毎日見ている山なのに、そして、奥様との時間も、こんなに楽しく、もう何年も前、奥様と酒田から飛島へ行かれた時、海の上から見たような鳥海山をもう一度見られたという感謝をされているんですね。
森 ええ。事実そうだったし、そうであるからして、「月山」も「鳥海山」も全くそこのところに力点をおいているのです。たとえ訪れてくるのは普通の人であっても、こちら側に気持があれば、その時間、その事柄は生きるのです。すばらしいことになるのです。
──やはり、蓮の上の露に世の中が映って見えるんですね。
森 女房も人が訪れてくれるのは好きでした。ふだんはふたりだけで、静かに山を見たりして暮らしていましたから。
働いているときは、がむしゃらに働きましたから、相手にされない女房は寂しがって、あとで東京に来て勤めているときなんかは、もう一度庄内へ行って、何もしないで暮らしたい、なんて思っていたようです。私は何もしない時でも孤独ではなく、昔の友人がよく訪ねて来てくれましたし、家内も楽しかったんでしょうね。
──お住いを転々とされたのは?
森 “ここでないところ”で住みたいというような、ロマンチックな考えなんですよ。ただ、移るときは必ず、今いる大家さんに良い家を紹介してもらいましたから、ずっと皆いい方たちのところでごやっかいになっていました。もともと、女房が庄内の出で、最初は親戚の家でした。窓を開くと、月山や鳥海山が見えて……。
山というのは、毎日、刻々、変わりますから、四季の山を楽しんで、吹浦へ来たのも、酒田に住んでいる時、飛島へ行ってすばらしい鳥海山を見て、船の中で「あのふもとのあたりに住みたい」なんて言ったのが始まりで移ったのです。
|
土地の人の会話は皆、方言で入っているので、先生のおっしゃる、部分が全体という感じが端的に読み手に伝わってくるようですね。
森 方言というのは、深い時間と空間を持っていますからね。いまの標準語が悪いという意味じゃなくて、そのほうがいいですけれども、なんといっても時間と空間は浅いですよね。
──そのものしか伝えませんからね。方言を言ったあとというのは、ほかのことをしゃべっちゃいかんのですね。「月山」のお寺のじさまが「……だちゃ」とか言って、これは、じさまの前に先生がいらして、そのじさまが言った方言は、まさしくそのときしかない言葉ですね。言葉の内には、無限にその人のものが、来し方のすべてがあるわけでしょう。その人の考えがこめられていますね。聞く人は、このすべてを感じる。言うほうもそれがわかるからそういう言い方をする。
森 そうですよ。それで方言で書いたんですよ。方言のひびきは読む人にとっては古いですけどね。
──ただ、方言をやたらに文字にしておもしろく書いても、あれはただ表面上のものであって、本当の方言の意味は先生のような文学にしないと、わからないんじゃないかという感じがしたのですが。
森 そう言われれば、ぼくの口からはそうだと言いにくいですけれど、やっぱりそうだと思いますね。
|
森 生活なんです。それが。
ぼくは月山を死の山、鳥海山を生の山と書きました。しかし、生というものも、厳然たる死というものがあるから生なのであって、むしろ生は、はかなき主観かもしれないんですね。だから、死の山に登って、生き長らえることを祈るのです。
──それでやっぱり山は栄えるんでしょうかね、死の山であっても。
森 だから山は死であることがめでたいのですね、あの世にお参りしてきたということで。あの世に参るということを輪廻というんです。われわれは一生の間に輸廻を何回味わったかということで、その人は──死地をくぐるというでしょう。輪廻を人生に何回やったかということの多い人ほど偉いんですよ。
なぜならば、輪廻というのは浮き沈みなんですよ。だから、円をグラフにかき、その半経を廻わせば、浮き沈みを現わす曲線になる。つまり、浮沈というものと輸廻というものは関係があるわけです。
──先生は今、ラジオやテレビで人生相談やルポなどやっていらっしゃいますが……。
森 なりゆきです。人生相談では、こうこうしなさいなんてことは、人間言えません。よく聞いてあげることです。
──力づけてあげることは。
森 やはり聞いてあげることですね。それぐらいしかできないですよ。できるだけ、あるがままにおられるような気持にさせてあげる。これはぼくの体験上からそれがいいと思うのです。
──あるがままに、いわば十年遊んだとおっしゃっても、実はその間にすごい“充電”をしておられるのですから、先生は。
森 もうだいぶ長いこと、書かずに、マスコミとおつきあいを楽しませていただきましたけれど、今、こういうふうにきているのですよ。もう、そろそろ書きたくなりそうなんですね。だから、あまりインタビューなんかも受けたくなかったのです。最初しぶいご返事をしたのも、そのためです。
──今度はなにか、奥様のことでも……。
森 それもあるかもしれないですけれど、全然別のものも出てくるかもしれません。
いよいよ一九八○年で、月山(一九八○メートル)の年だとかいっていますから、登る人もきっと多いでしょうね。.
──ちょうど、実も熟する時なのかもしれませんね。ますますのご充実をお祈りいたします。ありがとうございました。
|