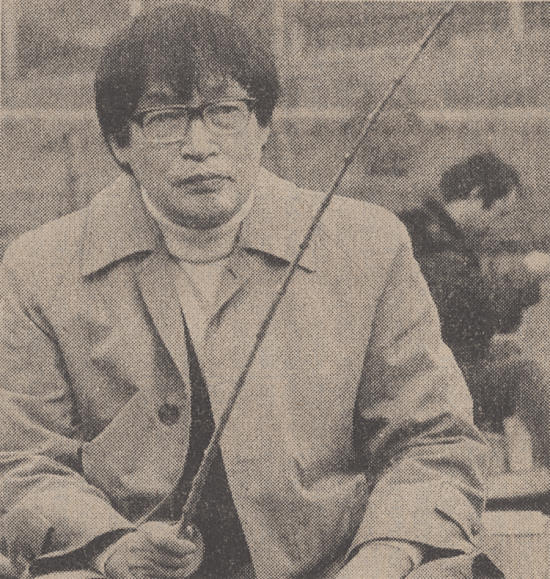
| 昨年十一月、川崎市で起きた二浪中の大学受験生による両親殺し事件は、現代の家族関係について、あまりにもむごい形で教訓をつきつけた。青少年の粗暴化は年々顕著になりつつあり、昨年一〜十一月の学校内暴力事件は千二百十件と前年同期比で八.二%増え(警察庁調べ)、五十三年一月から翌年八月までの家庭内暴力事件はわかっただけで千五十一件に上った(総理府の青少年問題研究調査報告書)。 |
私が育った大正時代に、スウェーデンのエレン・ケイという婦人教育家が「児童の世紀」という本を出した。それが日本にも入ってきて、外国式教育が花盛りになったんです。メンタル・テストとか知能指数をはかるなんてことも、そのころ始まった。
ところが、当時朝鮮の京城で漢学を教えていたぼくの親父は頑固(がんこ)一徹、幼稚園へぼくを行かしてくれなかった。代わりに行かされたのは漢文の素読を教える塾です。親父の考えは「自由教育などもってのほか。生徒が自分で勉強するなら、先生はいらんではないか。先生は教えるためにあるんだ」というわけです。また「幼稚園なんか行くと、先生に甘ったれるようになる。“教えて厳ならざれば師の誤り”。先生は常に厳然としていなくてはならん」。
まあ親父は時代錯誤だったんでしょうね。しかし、親父が言ったことは全く当たっていないわけじゃない。子供の自殺がふえたり、親を殺したり、先生をなぐったりするのは、先生や親がピシッとしていないからではないか。
| 十三〜十八歳の子供の約四割が自分の両親を「自分の考えを理解して、いろいろ教えてくれたりする」と言う。しかし、母親については、三二.九%が「自分のやることにいちいち世話をやく」と受け止めている(総理府調査)。親が日ごろ子供に特に注意を払っている事柄は「服装や髪型」が最も多く、次いで「健康状態」「外出先、遊びの内容」「勉強の仕方や時間」といったことが中心(東京都教育庁調査)。 |
親父は、“落ちこぼれ”なんて当然だ、と言うんです。「わしらの時代には、医者と坊主の子はみんな神経衰弱になっちまった」と。つまり、医者と坊主はわが子に後を継がせようと、資質に関係なく、いやがるものをむりやり勉強させるから、ノイローゼになる。ところが、百姓や商人の子は神経衰弱にならない。学校なんかへ行くことはないというわけだ。今、家庭や学校で起こっているいろんな事件もノイローゼが原因ではないか。知識だけを習っても、その知識を支えるモラルがなければどうにもならない。
終戦後、突如そうなった。戦争中には、ともかく目的観があった。飢えれば、イモの葉でもカボチャの茎でも食おうとする。それでも満足する。今の学校には、そういう内からの欲求も満足感もない。
親父はね、「神経衰弱になったら休学させて、新聞配達させるのが一番いい」と言ってました。第一に朝早く起きねばならぬ。第二にそのころは自転車なんてないから、かけ足、つまりジョギングをしなくてはならぬ。これを一年ぐらいやれば、神経衰弱などふっとんでしまう、というんです。実際、ぼくの兄が神経衰弱にかかった。すると学校をスパッとやめさせた。当時は小学校でも落第は珍しくなく、むしろ、中学へ進む子の方を落第させたのです。だから、一年間休学させても、そう突飛なことではなかった。それでまた親父ですが、担任の先生のところへ盆、暮れにあいさつに行っては、「鉄は熱いうちに鍛えよです。甘い点をつけないでいただきたい。言うことをきかない時はぶんなぐって下さい」と頼んだ。ぼくは往生しましたよ。母がまた母で、日露戦争当時、赤十字の従軍看護婦をやった人ですから厳しい点では父親とまったく同じで、逃げ道はありませんでした。昔のやり方がすべていいとは言いませんが、現状の解決策のヒントはその辺にもあると思います。
| 親だけでなく、学校や社会に対する親近感、信頼度も希薄になっている。高校生の六四.九%が悩みや心配ごとを友人に相談するが、教師に相談する者はわずか一.八%(日本リクルートセンター調査)。高校生活の中で、授業以外での教師との接触を「全然ないし、あまり重要でない」と思う者が六三.九%を占めている(日本青少年研究所調べ)。 |
ぼくの中学時代にも暴力はあった。ただ根本的に違うところがある。生徒に対する愛情です。殴られた先生のところへ遊びに行く。すると奥さんがオシルコを出してくれて、八杯もペロリと平らげて、「メシ食っていくか」と言われると、「ぼく少食なもんですから」ともじもじしてる。先生が「じゃあシコ踏んでみろ、ゆすって詰めればもっと食えるよ」。今、先生のところにシルコを食べに行く子いますか。
ぼくは、この世の中には二つの大学があると思う。一つは、いわゆる大学と呼ばれる学校、もう一つは目には見えないけれど世間で学ぶ大学です。部長、課長と言われる人たちがテンプラ屋のおばさんに、頭ごなしにやりこめられて参る。そのおばさんの「ひと理屈」というのは哲学です。
大学では理科であれ文科であれ、それなりに何か一つつかんでこなくてはならぬ。その哲学が人間を形成する。二つの大学を出ることは確かに理想です。だが、一つの大学を出ただけでもメシぐらいは食える。問題は、学校に進んでも実社会に出ても、一つの哲学をつかもうという心がないことだ。だから無目的になる。神経衰弱にもなる。“やさしさの時代”“いたわりの社会”なんて、ロクな事はありません。