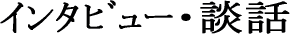 |
| 091 もっこす外野席 母に見る熊本の女の気丈さと順応性 |
| 出典:熊本日日新聞 昭和56年1月10日(土) |
 |
|
|
| 本籍は天草郡富岡町(現苓北町富岡)だが、実際に生まれたのは長崎市。五、六歳で朝鮮に渡り、戦後は東京だから天草に住んだことは一度もない。しかし、幼いころから度々富岡を訪れていてよく知っている。「僕らのころは、西の海は危ないといって泳げなかったものだよ」等々。前町長の森実さんとは幼なじみで、話の合間に「実くん」が何回か出てきた。 |
| × × |
| 「徴兵検査は原籍地で受けることになっているから、僕は本渡まで行きましたよ。二十歳の時だから一高生だった。あのころは八代から船で行くんだが、船の中で、そう若くはないが、おばあさんでもない女の人につかまった。どこから来たかというから東京からだというと『東京から来た人なら政治の話ば聞かせろ』というんだね。中年の女が政治の話を聞きたがるぐらいだから、熊本県人というのは、よっぽど政談が好きなんだね。京城にいたころも両親の友達が来て、ほとんど九州、特に熊本の人だったんだが、やっぱりさかんに政治の話をしていた。それも批判ばっかり。たとえば清浦奎吾の話をしているんだが、役せんやつだとかね。たまたま派が違っていたのかもしれんが」 |
|
|
氏にとって最も身近な県人は両親である。「これが僕の母親だよ」と見せられたのは百料事典の従軍看護婦の写真だった。従軍看護婦を説明する項目にあり、説明の終わりに「作家森敦氏の母」とあった。そろそろ七十という人から、二十代の母親の写真を誇らしげに見せられると、エディプスコンプレックスというのは死ぬまで男につきまとうものかと思わずにはいられない。
「母は面白い女で、気が強くてこっけいなところもあった。あれが、だいたい熊本の女じゃないのかな。母はね、僕が一高に入ったのをものすごく自慢していた。会う人ごとに“ああ玉杯”を知ってますか、そうですか、うちのバカが間違って“ああ玉杯”に入ったんですとかなんとか息子の自慢をタラタラしてたわけだ。ところが、僕が一高をやめるといいだした。僕は一高にあこがれて入ったんだが、入ってみたらつまらんということがわかったし、新聞に連載小説を頼まれたりしたこともあって、学校をやめて文学にかけようと思ったんだ。それで母親にいったら、志があってやることかというから、そうだ、志は大いにあると答えたら、そんならいいっていうんだね。ふつうの母親だったら息子が一高(いまでいえば東大だからね)やめるといったら落胆するよね。それだけじゃない。僕が文学をやるとみるや、天眼鏡を持ち出して、ドストエフスキーやフロベールを読みはじめた。もう五十代の後半だよ。僕は横光利一や菊池寛にかわいがられていて、だからこそ連載の話もきたんだけど、その二人のところへいきなり出かけていって、ドストエフスキーは世界一の作家だとかいって肝胆相照らしてきたり…」
どんな立場に立たされても、それを切り開いていく気丈さと順応性を熊本の女は持っているのだと…。
「東北人も九州人も酒を飲みます。でも飲み方が違う。南の人は飲むと大言壮語します。それも堂々と九州弁で。熊本の人というのはでもそれに匹敵するだけの精神の強さがないような気がしますね。割にチョロい。弱いものには強いが、強いものには案外弱い。もちろん熊本人だけがそうというわけじゃないんだが、熊本人はいさぎよい言葉を使うからなんとなく目立つんですよ」 |
|
|
「飲み屋で飲んでても、大きな声でやっているが、○○さんと名前で呼ばずに『課長』とか『部長』とかいっている。『まあ一杯』とかなんかいうから、おごってくれるのかと思うと結局は金はこっち持ちだったりね。一見剛毅(き)に見えるが、その実計算高くて、なかなかこすいところもある」
独り者の老作家の住まいは、予想に反して瀟洒(しょうしゃ)な白い洋館、部屋もきちんと片付いていた。話の合間にキッチンへ立って行ってすばやく紅茶をセットして入れてくれた。
「オレがオレがという熊本人の血は、実は僕にもあるんだなあと思うことがよくありますよ。だからあまり県民を怒らせん程度に書いといて下さい」 |
| 〈樹〉 |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |
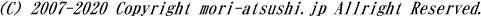 |
