| 095 直言曲言 人づくりには、「力」の行使を恐れるな | ||
| 出典:企業実務 4月号 昭和56年3月20日 | ||
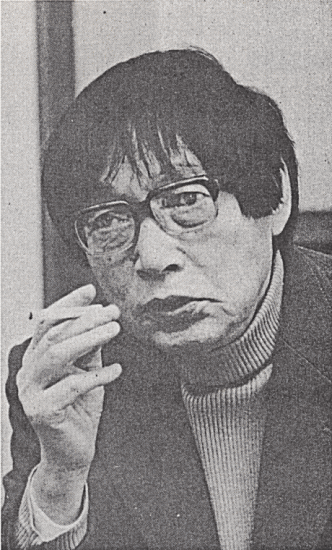 |
||
| 略歴 明治45年1月、熊本県天草に生まれる。本年69歳。旧京城中学を経て旧制第一高等学校中退。在学中の処女作を菊池寛に認められ、横光利一に師事する。昭和48年、「月山」で第70回芥川賞を受賞した。寡作の本格派作家として知られる。 |
||
| 学内暴力は全国どこかの新聞に載らない日はないくらいで、いまや国会で論議されるほどの重大な社会問題化している。その発生の根源を作家の目は次のように分析し、「教師や父兄は力・権威を回復せよ」と説く。
|
||
| いま、青少年の非行が大きな社会問題になっている。激増する少年犯罪、家庭内暴力、学内暴力、少女売春、暴走族等々…。ことに学内暴力問題など国会でまで論議される時代である。 これら青少年非行問題の根は、今日の社会のあらゆる断面に深い関わりをもっている。より直接的な関係にあるものは、教師の質の低下、結果としての師弟の断絶、日教組、父兄とくに母親のあり方、親子の断絶、PTAのあり方等々である。これらについての戦後の歴史的背景から必然的に今日の事態を招いていると私は考える。 |
||
|
||
| 昔、小学校の先生は訓導、中等学校では教諭と呼んでいた。訓導とは読んで字のごとく、「訓え、導く」人であり、教諭は「教え、諭すべき」人であった。つまり、小学校・中等学校の先生は「子供たちを全人格的に導き、その人格の形成を手助けする」という崇高な役割を担っており、事実、その使命感、責任感も旺盛だった。 一方、今の先生はどうか。学問知識を子供たちの頭に叩き込んでおりさえすれば、職務は果たしていると思っている。一人前の青年に対して、高度な専門知識を伝授する大学教授とその姿勢において自分たちを同列に置いている。そこには大学とちがって子供たちの人格の基礎を形成する小・中学校の先生として最も重要な人格の陶冶、自己規制の必要性についての認識が薄い。その結果が、道徳的・人格的に生徒の範となるべき先生のハレンチ行為、不行跡が全国各地で発生することになっているのである。 この間、大阪の小阪中学校の先生たちが集団で授業放棄したことがあったが、あれなど今日の教師が教師としての責任の重大さを自覚していないことを端的に示した好例である。自己中心的で独善的で、まったく甘ったれた行動というほかはない。 今日、多くの教師は、自分を聖職者とみるどころか、一般社会の職業人と同じく労働者であるとして、自らその誇り高い地位、使命を放棄している。しかし、もし労働者であるとするならば、あのような暴挙は民間企業では絶対許されないところだ。長期欠勤の二人の女教師なども、とっくの昔に解雇されているところである。親方日の丸で、日教組にガードされていてこそ可能なわがままであり、甘えというほかはない。それにしても、「自分は先生である以前に労働者だ」として、自らの職務を深く考えることもせず、権利ばかりを声高に叫び、生徒のことよりまず自分自身のことを考えるやり方が、教師自らの社会的評価に著しくダメージを与えているのは事実である。「ああ、労働者かね。工場で働くオレたちと同じだね」となり、生徒たちが敬意を払うべき特殊な存在として先生を見なくなるのも必然の成行きというものである。それが結果として「子供たちに殴られ、ブッ倒される哀れな今日の状態」につながっているのである。 昔の先生たちは、生徒たちからはもちろん、父兄からも一種畏敬の目で見られていた。田舎では知名人だったそういう関係では、生徒が先生に対して暴力を振うなど論外で、もしそういう生徒が現われたら親も社会も学校も厳罰で臨んだ。そういう凛たる厳しさが秩序を保っていたことを、この際すべての関係者が思い起こすべきではないか。当時の教師たちは「教えて厳ならざれば、師の誤り」という信念で教壇に立っていたのである。 生徒に対する愛情の欠如が校内暴力を生んでいる面もあるようだ。いまの教師の中には授業の進行を気にするあまり、「お前には関係ない」「お前は眠っておればよい」などという冷たい暴言を吐きつつ、授業をする人もいるらしい。 また、学校が終われば、私生活は完全に区分し、家に生徒が訪ねてくるのを迷惑がる先生が多いという。そしてせっせとアルバイトに精を出す。そういう先生に生徒を引きつける魅力があるはずはない。師弟の断絶が生ずるのは当り前である。 昔は、先生宅には多くの生徒が訪ねて迷惑をかけていた。奥さんも快く歓待してくれていた。その触れ合いの中に教育があった。そういう師弟の触れ合いが何故なくなったのか、私はそこに、精神的価値観をあっさり捨て去り、物質至上主義になった戦後の世相、欲望過多時代のどうしようもない弊が現われているように思う。まったく、根は深いところにある。 そういう上下関係の断絶は一般の会社、職場にも多いと聞く。上司は部下を自宅に呼びたがらない。部下も訪ねてゆきたがらない。これでいいのだろうかと、うすら寒い思いをするのは私だけだろうか。 師弟の断絶というが、教師間の断絶もあるようだ。一人の教師が生徒に暴力を振われても、自分に関わりがなければ、見て見ぬふり、知らん顔をする。敢えて関わって自分も殴られたり、あるいは下手をして職を失ってはかなわないからだ。こうなっては、教育現場の荒廃も救いようがない。 また、こうした教師たちの態度が教師に対する生徒の侮りとなり、イラ立ちを誘い、次の暴力へと発展してゆく。生徒たちはこの場合、教師たちが真正面からブツかってきてくれることを密かに待ち望んでいるのではないだろうか。 |
||
|
||
| 学内暴力については教師自身の責に帰すべき点も多いが、同時に私は、戦後22年から施行された学校教育法、そしてPTA、父兄とくに母親の側にも大きな原因と責任があるように思う。 まず、学校教育法はその第11条で体罰禁止規定を設けているが、これが教師の手足をしばり上げ、生徒に足元を見すかされることになった。それまでは男子教員のすべてが、とくに柔剣道の教師などが全校生徒に睨みを利かせていたが、これがまずできなくなったのである。 同時に、それまでは教師の側に立っていた父兄も、今度は逆に教師を監視する立場に回り、教師がもし体罰でも加えようものなら、それを問題として取り上げた。 PTAについては、戦後の一時期、学校運営資金の一部をPTAが援助し、それによって先生たちの給料の一部が賄われていたことがあったが、「これでは先生たちはPTAに頭が上がらない」と言われたものである。果たせるかな、そのため、先生たちはまるで妾のようにPTAの顔色を窺わざるを得ないような状況になってきた。 そして、そのPTAの最大勢力が母親たちである。その母親たちが、戦後になって子供の教育問題について大きな発言権を持つに至ったことも、今日の事態と深い関わりがあるように思う。 母親たちは自分の子供に教師が手をかけたとなると、それがどの程度のものであれ、また、どんな意味をもつものであっても、「暴力」という言葉で十把一からげにし、寄ってたかってその教師を「暴力教師」としてヒステリックに糾弾してきた。これでは教師が信念を以て生徒に当たれるわけがない。生徒たちは教師の制裁を恐れる必要もなくなり、鎖を外された狂犬のように勝手な行動に走るようになったのである。 母親の罪はこればかりではない。母原病といわれる言葉もあるとおり、過保護、甘やかし、教育ママ、いろんな面で子供たちの心身をスポイルしている。先述した教師の「知識教育偏重」にしても、それはとくに母親たちが教師にそれを求め過ぎることが一端の原因になっている。教師としても、母親の非難・中傷を無視することができず、やむなく、受け入れざるを得ない面もあるようだ。 生徒に対して押えが利かないのは教師だけではない。父親たちも息子・娘たちを支配できずにいる。その最大の原因は、戦前の父親にはあった凛とした厳しさが戦後の父親から欠落してしまったことである。友だち親子もいいだろう、パパと呼ばれての団欒もいいだろう。だが、子供から尊敬され、畏れられることもなくなった現実、子供を支配できなくなった父親の権威の失墜は厳しく考え直すべきである。母親の甘さに父親の甘さまで加わったら、子供たちが放縦に走るのは当然である。 父親は家庭のみならず、職場においても自らの識見・人格・実力で部下を統率できず、借りものの権威に頼っている人が多いという。問題は複雑に絡み合っているように思える。 今の時代、「やさしさの時代」だとか「いたわりの社会」などと言っているが、別の見方をすれば、それは「女性化の時代」「男・総骨抜きの時代」とも言えないことはない。皆が子供たちを撫で回す。放縦のなかで育った子供たちは大人の手に負えな<なる。暴れ回る子供たちに対して、教師たちは「さわらぬ神に崇りなし」で逃げ腰の構えをとり、誰も彼らをまともに受け止めようとはしない。戦後教育を受けた教師が大半の今日、「敢えて…」の価値観をもった教師など最早いないということだろうか。 |
||
|
||
| 今日まで、教師の体罰を非難し、「暴力反対」を呼びつづけてきたPTAや父兄、とくに母親などは、学校の今日の事態をどう解決しようというのだろうか。何にもできはしない。やがてその責任を学校、教師、また不特定の社会一般に転嫁しようとする。そして結局のところは警察力に頼ることになる。 その警察力とは何なのか。結局、それは「力」以外の何ものでもないPTAや母親たちは、その力と暴力とを同列においてきたのである。企業社会においても秩序を乱す者に対しては各種の制裁が待ち受けている。ところが、彼らには、集団の秩序を守り、統制をとるには力による抑止、制裁が不可欠であることが分かっていないのだ。師弟の間におけるこの制裁は、また生徒を鍛え、人間の触れ合いを生むということを頑なに認めようとしない。 逆に、昔の親たちは、子供が非行に走ったりした場合、むしろ親側から先生に対して愛の制裁をお願いしたりしたものである。そういう師弟の関係を、PTA、父兄、ことに母親たちは「暴力反対」の叫びによって長い問スポイルしてきたそれが現場の教師たちに、大変な苦痛、屈辱、苦悩を強いてきたことを、今こそ思い致すべきではないだろうか。 学校でも運動部などが比較的統制がとれているのは、そこにはリーダーがいて、秩序を乱す者に対して制裁を加えるからである。したがって、こういう制裁まで暴力としてただ闇雲に禁止し、反対することは決して賢明なやり方とはいえない。今日の学内暴力問題を解決する方法は結局そこに見出すしかないと私は思う。 しかし、こうして生徒たちへの制裁を主張したり、PTAや母親たちを非難したりすれば、各方面からの抗議がくる。教師のあり方を批判すれば、日教組が逆に攻撃してくる。だから、誰も本当のことを言えずに、適当にお茶を濁す程度でとどめてしまう。「そんな甘ったれた小僧たちなど、少年院に入れるとか、自衛隊でシゴキ回せ…」などと、言おうものなら、社会党、共産党あたりが押しかけてくる。これらはすべて、いまの目本ではタブー(禁忌)になっているからだ。 憲法第九条、自衛力増強、靖国神社、道徳教育……その他、いまの日本はまさにタブーで満ち溢れている。そして皆が皆、それらタブーを避けて通ろうとする。避けて通って問題が解決すると思っているのだろうか。タブーをタブーとしていつまでも残しておくからこそ、矛盾・対立はますます増幅・複雑化し、解決をさらに困難なものにしてしまうのである。 体にデキモノができたとき、見当外れの治療をしたり、周りを撫でただけでは治りはしない。そのデキモノにズバリ、メスを入れれば治りも早い。どのようなタブーであれ、そのタブーを真正面からとらえ、その間題の本質にナゼ迫ろうとしないのか。本当のことが言えない社会、これは将来にわたって大きな禍根を残すだろう。 ともかく、事態は最早、悠長なことは言っておれない時期にきている。先生はじめ世のすべての親たちには、いまこそ子供たちに制裁を加えるという「これまでのタブー」に敢えて挑む勇気と心構えが求められていると思う。そうして大人たちが身を以て示すこと自体が、子供たちにとって教育上、良い結果をもたらすと私は信じている。 |
||
| (談) | ||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||