| 132 「奥の細道」を旅して | ||
| 出典:学び方教室 昭和59年10月10日 | ||
 |
||
| 「奥の細道」を歩いて私が身をもって感じたことは、芭蕉の文章構成のすばらしさと、見た目を巧みに使って、人間の内面を描く見事な筆致であり、学ぶところが多かったと思う。 | ||
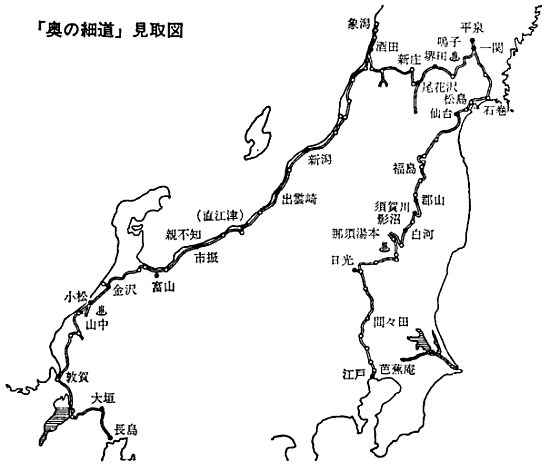 |
||
|
||
| 「女性が美しく見えて、毎日毎日が愉快なら、それにこしたことはないでしょう。それが病気だというのなら、私もそんな病気になりたいものです」 と、医者はいうのです。そのとおり、私は、年をとるにしたがって、来る日来る日が、愉快でたまらないのです。訪ねてくる女性は、どの人も美しく見えます。これは、脳神経に異常をきたしたのではないか、あるいは老人ボケが起こったのかもしれない。それとも、私は長年お寺さんにおりましたので大悟徹底したのかもしれないなど、あれこれ迷った未に、病院にいって看てもらったところ、医者にいわれたのが冒頭のセリフなのです。 振り返ってみますと、私は十年間単位で、何か一つのことに打ち込んできました。ここ十年間は、ラジオ、テレビに徹底的に出演しました。どこかのラジオ、どこかのテレビにほとんど毎日のように出演していました。 それが今年で十年目に当たりますので、そろそろやめようかと思っていた矢先に、NHKから「奥の細道」を回ってくれないかという依頼を受けました。 私自身も、一度は芭蕉が歩いた「奥の細道」を辿ってみたいという密かなねがいがありました。この機会に、今日では古典といってもいい「奥の細道」を再度勉強し直そうと決心しました。 芭蕉が歩いた往時と比べれば、交通事情は雲泥のちがいですが、「奥の細道」はいまも相当な山坂で、しかもこの脚で一歩一歩、歩いていかなけれは、意味がありません。訪ねてくる女性が美しく見えるとか、毎日が愉快だといっても、耄碌しているかどうかさえわからない体で、果たして行けるかどうか気がかりでした。 ところが、NHKの方では、私の心配をよそに、企画がどんどん進行する。私もついには、断ることもできず「奥の細道」の企画に乗る決心をし、資料を集めはじめました。「奥の細道」は、原稿用紙にして百枚足らずの短いものですが、研究された資料はおびただしい数にのぼることがわかりました。しかも一点、一句についての詳しい研究がされているのです。 調べてみると、研究している大先生にもランク付けがあり、ナンバーワンはこの先生、ナンバーツーはこの先生というように決っているのにも驚きました。 最初私は、「奥の細道」のみならず、芭蕉に関係ある膨大な研究物を読破して、この企画に臨もうと思っていたのですが、資料には一切目を通さずに「奥の細道」の一句を読んでは旅をし、また一句を読んでは──というように、裸でぶつかっていこうという気持ちになりました。実際にそうしたのです。 気分はずいぶん若々しく張りつめていましたが、体の方がいうことをきいてくれません。放映されたテレビの画面に、ヨタヨタした足どりがクローズアップされると、「森は、あんなにヨタヨタしていて大丈夫なのか」という投書がきました。そうかと思うと、初めはヨタヨタしていたけれど、後はすごい迫力があったという投書もありました。それには次のような訳があったのです。 栃木県に雲巌寺という大変奇麗な寺があります。この寺には長い石段があり、テレビの画面にその石段をスタスタと上がっていく私の姿が映りました。それを見た視聴者の方が、「『奥の細道』がスタートしたころ、あんなにヨタヨタしていたのに、たいしたものだ」といったそうです。なるほど、画面ではそう見えますが、実をいうと、私が石段を上がったのは最初の二、三段で、後は私の目線の位置でカメラアングルを上に上げていくのです。そうすると、私が石段をスタスタ上がっていくように見えるのです(笑い)。いわゆる“見た目”というやつです。 この“見た目”というのは、文学の世界でも非常に大切なことなのです。文章を目線の高さで書く、ということをよくいいます。この手法で書くと、文章に立体感ができ、人間を内面から捉えて描くことができるというわけです。 雲巌寺の場面でいうと、私が石段を二、三段上がって後はカメラが見た目で傾斜を追っていく。その間に私は石段の下にある自動車で上までいき(笑い)、今度は、上から二、三段下りてくれというから下りたのです。テレビを見ている人たちは、森はすごいなあ、あの長い石段を息も切らずに上がっていったとほめてくれたのです。こんなトリックがあるとは知らずにです。 この手法は、みなさんが文章を書くときに覚えておかれるといいと思います。芭蕉自身、この奥の細道を歩いて「奥の細道」を書き上げたのですが、ただ歩いたあとを平板に書いたのでは、誰も読んではくれないでしょう。芭蕉は、この“見た目”を使って文章を書いているから、「奥の細道」がいまも読まれているのです。私たちは、いま、こういう文章が残っているから、目線の高さで、などといっていますが、芭蕉は自分でいろいろ鍛練をした結果、この手法で書いたのだなあ、ということを私は悟りました。 奥の細道の出発は「芭蕉庵」からです。芭蕉庵というのは墨田川と、小名木川が合流するところにあったのです。いまは、家が立ち並び、見るかげもありませんが、お稲荷さんの祠のあるところが芭蕉庵であろうといわれています。 「奥の細道」を歩くのですから、芭蕉が旅立ったところから私も出発しました。この芭蕉庵というのは、鯉屋杉風という魚屋を営む人が持っていた生簀の番小屋だったそうで、それを芭蕉に提供したのです。 ところが、この芭蕉庵は、火事で焼けてしまいます。その火事というのは、芝居などでご存じの八百屋お七が恋人吉三に逢いたさに火をつけたものだといわれているあの江戸の大火をいいます。その火事が墨田川にも拡がり芭蕉庵も焼けてしまいました。誤解のないようにいっておきますが、江戸の大火は、お七が火をつけたものではありません。あれは、井原西鶴が『好色五人女』のなかで、八百屋お七を書き、その火事にことよせてストーリをつくったのです。ですから、本当は八百屋お七の火事ではないのです。 芭蕉庵が火事で焼けて、芭蕉は信州の方にいきます。何年か経て、杉風がまた芭蕉庵を提供してくれました。その芭蕉庵で席の温まる間もなく、芭蕉は奥の細道を歩いてみたいと覚悟を決めました。それが有名な「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらへて老をむかふる者は、日日旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。……」という文句になるのです。そして、何かの呼ぶ声に誘われるように、旅に出ないでおられないという気になって、杉風が用意してくれた芭蕉庵を売り払ってしまいました。奥の細道の旅の路銀の足しにと思って売ったのでしょう。この庵を出ていくときに、 草の戸も住替る代ぞひなの家 という旬を詠んでいます。ここまでが「奥の細道」の序文です。 芭蕉は、志の非常に高い人といえます。その志を貫き通し、より高い山の頂上を目指しているような人です。そういう人は、ニーチェがいうように孤独なのです。 ……我ひとりゆく秋の風 という句からもうかがえるように、芭蕉には孤独感があります。そしてまた、庶民の暮らしにもあこがれていました。庶民を離れて俳句の修業をしようと思ったにもかかわらず、なお自分も普通の人のように結婚し、子どもを持ち、ひな祭りにはひなを飾るという生活にも憧れる気持ちが、はじめの句によく表れています。 私などは、高い志を抱いて、ということはとてもありません。それでも、普通の人のように家を持ち、普通の人のように子どもを持ち、世間並の苦労をして、普通の人のように死ねたらどんなにいいだろうなと思う心がまったくないとはいいません。芭蕉にはそういう思いが強烈にあったでしょう。 |
||
|
||
| 先にお話ししましたように信州から戻った芭蕉は、もう再びここには帰ってこないぞという固い決意で、芭蕉庵を売り払いました。そして、すぐに旅立とうとしたのですが、一度千住にある杉風の採茶庵に移ります。そのときに、 行春や鳥啼魚の目は泪 と詠みます。この句を、漢詩からきたという人もいます。俳句というものは、みな何かわけがあって作っています。どうも鳥啼きの方はわかりませんけれども、魚の目に泪というのは、杉風は魚屋ですから、自分の許から去っていく芭蕉に対して泪を流したという比喩が魚の目は泪となったのではないでしょうか。 昔は、旅に出るといえば、水盃をしたものでした。旅に出てしまったら、明日の命はわからないものです。だから、おそらくは、杉風の泪を、魚の目は泪という表現におきかえたものと思うのです。 芭蕉は、その千住を旅立って、草加に泊まったと書いてありますけれど、どうもそうではないらしいのです。本当は粕壁(春日部)で泊まったらしいのです。曾良という人が芭蕉のお供をしていて、この人がそう書いています。 奥の細道の旅に、芭蕉は曾良ではなく、路通という人をお供に連れて行きたかったのです。路通は、乞食だったけれども、よく俳句を詠みました。ただ、路通は、酒癖が悪かったので、曾良に決めたのです。 この曾良は、どこをどう行って、何があって、天候はどうだったとか、どこに泊まったとか、ということを、驚くほど詳細に日記に書き留めています。『奥の細道随伴紀行』といわれているものです。曾良の日記によると、草加には泊まらず、春日部に泊まっています。そこには、いまも仁王門が残っていますが、観音寺があり、芭蕉はそこに泊まっているのです。 面白いことに、芭蕉が観音寺を通りかかったころ、円空が、そこに彫刻を残しているのです。円空は、ナタで庭木を倒して、一刀彫で仏像を彫る人です。おそらく、円空が彫っているのを近所の人たちが見ていて、そこを通りかかった芭蕉もー緒に見ていたのではないかと想像するのです。 円空は実にスケールの大きい人で、百五十万体の仏像彫刻を宿願に、北海道まで渡りました。いたるところに仏像を彫って功徳を施そうとした人です。 もし、観音寺で円空と芭蕉が逢って、何らかの会話があれば、面白いと思うのですが、そのような事実は『奥の細道随伴紀行』にも見られません。 これは日本だけでなく、西洋にもこれと似たような話があります。西洋の最大の哲学者といわれるヘーゲルがベルリンの二階屋で下宿をしているときに、その下の階にアーベルという若者が住んでいて、よく騒いでいました。年老いたヘーゲルは、馬鹿騒ぎに腹をたて、口もききませんでした。その階下の若者こそ二十七歳でこの世を去ったノルーウエーが生んだ偉大な数学者アーベルだったのです。もし、この二人の対話がひと言でもふた言でも残っていたら世界は益すること大だったろうといわれています。このように、もし円空と芭蕉との間に対話があれば、円空の思想ほ芭蕉の哲学に影響し、芭蕉の考え方は円空に伝わらないわけがないと思います。あの観音寺でどうして二人が逢わなかったかと、残念でなりません。 芭蕉は春日部から、白河の関所に向かって旅を続けました。須賀川に住む、相楽伊左衝門という人からの手紙で、北国は寒いですよと教えられていました。芭蕉が全国各地の人と手紙のやりとりを沢山しているところをみると、当時の郵便は発達していたと思います。 芦野に「遊行柳」というところがあります。多くの人がこの「遊行柳」というところに立ち寄っています。ここは、朽ちかけた柳があるというだけの何の変哲もない場所です。それも何代目かの柳です。 私は、その柳のところに立って周りを見回しました。周りは山々に囲まれ、山ひだのなかに集落が見え隠れしています。 「焼きいもー、焼きいもー」 という、焼きいもを売る声が聞こえます。農家の人たちも、最近は自分の家で焼きいもを焼いて売りに回っているらしい。面白いなと思って、NHKの人に、それを収録してくれといったのです。それこそ遊行柳にふさわしいと思ったのです。ところがNHKは、待ってくれという。芭蕉の奥の細道なのだから、といって、焼きいも屋が通り過ぎるまで、ずいぶん長い間待たされました。 考えてみると、これは、私(森敦) の「奥の細道」であって、芭蕉の「奥の細道」を研究しなくてもいいのですよ、ということが前提だったのですから、焼きいもー、という声を聞きながら柳の傍に立っているところを撮ってもらいたかったと、今も残念に思っています。 仙芭蕉はここで、 田一枚植て立去る柳かな という句を読んでいます。大先生の説によりますと、芭蕉がここを訪れたときは、田植えの最中だったので、田を一枚植えて立ち去ったと解釈しておられます。 私は、田舎を放浪し、自分の好むところに住んだりしましたが、そう簡単に田植えをさせてくれるものではありません。田舎の人に親切にしてもらったお礼に何かしたいと思い、猫の手も借りたい農繁期に田植えを手伝うといったら、それはありがたいが、その気持ちだけで結構ですといわれました。素人が田植えをしたら、かえって農家の人は困るのです。このことから考えても、芭蕉が田植えをしたということはないと思います。 この句の大切なところは、田植ての「て」にあります。「て」によって、主語が変わってきます。私は、早乙女が田一枚植えて、芭蕉が立ち去る、というのではないかなと思うのです。そういう例は沢山あります。これは、俳句のみに許された文法上の約束ごとです。 NHKでは、若い女の人を集めてきて、その人たちに一枚だけ苗を植えてもらいました。ところが、いくら待っても焼きいも屋が立ち去らないのです(笑)。その間に田植えはどんどん進んで、焼きいも屋が行ってしまったときには、田植えは終わっていました。私は、ただ田植えの終わった田を眺めているだけということになってしまったのです(笑)。 |
||
|
||
| 私たち一行は、白河に行きました。白河の関所には、松平楽翁公(定信)の建てた蹟碑があります。松平公は『花月草紙』を書いた人でもあります。ここの関所は大変なところで、昔の人は白河の関所を越えるときには、ああこの関所をいま越えるぞ、という特別な気持ちで、衣冠を正して、通ったそうです。芭蕉一行も、「心許なき日かず重るままに、白河の関にかかりて旅心定りぬ」といっています。 芭蕉一行は、着た切り雀で旅をしているのですから、いっぱい咲いている卯の花を頭に挿して、衣冠を正すつもりで関を通ったと、曾良は、 卯の花をかざしに関の晴着かな と詠んでいます。 NHKでは、その情景が撮りたくて、前もって白河神社の宮司に卯の花はなんとかなりませんかと聞いていたのです。とても寒いときでしたので、卯の花など咲いていません。けれども、なんとかしてくれというので、宮司は卯の花にビニールの袋をかぶせて、煉炭などで温めた。苦心の末、小さい卯の花が一輪咲いた。それを私はよろこんで頭に挿しました(笑)。 芭蕉に来た須賀川からの手紙に、北国は寒いぞと書いてあったといいましたけれど、私たちも須賀川に足をのばしました。須賀川には相楽乍憚(等躬)という人がいました。現在でも相楽家は名門です。芭蕉が相楽等躬のところへ行くと、白河の関を越えられるについて何か感想はありますか、といわれました。私たちは人に逢うとまず挨拶をします。俳句の世界では人と人との触れあいのなかで句を詠むのが本当ですから、俳句にとって挨拶は非常に大切なことなのです。そこで芭蕉は、 風流の初やおくの田植うた と詠みました。 現在、須賀川に田植え歌保存会があるというので、芭蕉の句にある田植え歌をうたってもらうことにしていました。ところが伝達が不十分で、来られたのはおばあさん一人でした。でも、そのおばあさんは一人で、田植え一生懸命歌をうたってくれました。 そのとき私は考えました。先の「遊行柳」のところで“田一枚植て立去る柳かな”という句が出てきましたが、またここで“風流の初やおくの田植うた”と、田植えが二度出てきます。文章や小説の世界では、同じ情景描写が二度、三度と重なるのはまずいことですから、不思議に思っていました。 昔は、田植え前線というのがあって、その前線は日本列島を南から北にのぼっていく。ですから、芭蕉が、遊行柳から須賀川に着くまでに、円植え前線が移動していたのです。私は今度の旅をして、身をもってそのことを知りました。 須賀川を出た芭蕉は、松島のおぼろ月を見るために北に向かって旅立ちますが、途中、平泉に寄ります。どうして平泉を回ったのかというと、芭蕉は源義経が好きだったのです。芭蕉はもともと武士の出ですから、武士の心を忘れてはいないのです。当時俳句の旗頭といわれた檀林風に反抗して蕉風というものを立てようとした人です。そういう意味では、一世の風雲児だったのです。 この風雲児というのほ、歴史的にみても悲劇性を伴って、私たちに語りかけてくる。肝胆相照らすというか、芭蕉が義経を好きだったという理由もそのへんにあったのではないでしょうか。 悲劇の風雲児、源義経についてはいろいろな伝説が残されています。平泉で死んだのではないという人もいますし、大陸へ渡ったという人もいます。私の若いころは、義経は成吉思汁だという本まで出版されました。源義経を、ゲンケイキと読むとジンギスカンに似ているからです。それに黒龍江の人たちは、いまもゲンケイキを神様として祭っているといいます。 私は、その事実を確かめるべく、北海道からサハリンに渡ってみました。サハリンの南に行ったところにナヨロという町があり、そこまではアイヌ人が暮らしていて源義経は義経なのです。 ところが、ナヨロから北へ行くと、タライカというところがあり、そこでは義経と弁慶は違う人物なのです。言葉は完全に理解できませんでしたけれど、そこの人たちに聞くと、義経は大変偉いといいます。どこが偉いのかと訊くと、義経は大きな躯をしていて、村という村を征服したというのです。 では、弁慶はどうだと訊くと、あれは駄目だ、力がないというのです。 芭蕉は平泉で、 夏草や兵どもが夢の跡 と詠みます。それにかわって曾良が、 卯の花に兼房みゆる自毛かな と詠んでいます。兼房はどういう人かというと、義経の北の方の乳人、増尾兼房のことです。乳人というのは普通は女がなり、男の後見役は傅といいます。この増尾兼房は義経の最後を見届けて火を放ち、敵陣に飛び込んで奮戦して死んだといわれています。 曾良の句に、卯の花が出てきますが、白河の関を越えるときの句にも卯の花を詠んでいます。これは、田植え前線と同じで、卯の花にも、卯の花前線というのがあるのです。白河では宮司が卯の花を咲かせようとやっきになってくれたのに、平泉を私たちが訪れたときにはもう花は終わっていました。 |
||
|
||
| 山という字は象形文字でいえば、山が三つくっついた形です。出羽三山がそれに符号します。山の字の左側に当たるところが羽黒山で、真ん中が月山、右側が湯殿山です。湯殿山は、非常に大きな渓谷です。仏教では聖域を山と呼んでいます。 こういう面白い話があります。戦時中、アメリカ空軍が日本を爆撃しょうと思い精密な地図を作製しました。そのときに何々山とあるから、山と訳した。ところが実際に飛行機で飛んでみると山ではなく、寺だったという話もあったくらいですから、神聖な場所には山を冠したのです。寺というのはもともと山と深い関係にあり、それがやがて修験道と結びつくのです。 さて、平泉を後にした芭蕉は奥州の象潟に抜けます。芭蕉は、松島の描写も大変なものがありますが、象潟の描写にも大変な力を込めています。松島と象潟を対照させています。ある場所とある場所を対照させて描くことを文学では対応といい、大切なことなのです。 例をあげて説明しますと、松島は笑うが如し、象潟は恨むが如しと、対応させた表現をしています。「奥の細道」の構造形成は、この対照の妙によって綴られているといっても過言ではないでしょう。だから、いま、みなさんが何かを書こうとするときは、必ずこの対応を心にとめておくと、しつかりした文章構成になります。これは、文章を書くときの秘訣といってもいいでしょう。世に名作といわれる作品を読んでみますと、この対応には非常に気が配られていることがわかります。 芭蕉は象潟から酒田へ入りました。そして、酒田から出羽三山に入るまでを詳しく書いています。芭蕉が歩いた道というのは、近江商人がかつて歩いた道でした。 近江商人たちは、俳句のたしなみがありました。そのころの一般庶民は俳句など詠みませんでした。俳句などに熱をあげていると、路通のように、末は乞食になり果てると思われていました。 私にもそのような思い出があります。私が田舎を放浪しているときに、ある立派な家を訪ね家訓をみると「博打、俳偕すべからず云々」と書いてありました。 芭蕉は酒田から新潟に向かいます。ところが、山形を過ぎたころから文章が残っていません。俳句だけは詠んでいます。 あら海や佐渡によこたふ天河 がそれです。文章のないことについては、いろいろと論争があります。芭蕉が、何か不愉快な目に遇ったとか──。私は、そうではないと思っています。 新潟から親不知にかけては、ご承知のようにとても景色のよいところです。NHKでは、その親不知を撮影するというので、カメラマンが機械をかついで断崖をおりていきました。ところが風が強くて、機械は飛んでしまう。電源車が、強風を受けて横に動きはじめる。カメラマンは、撮影を断念してあがってきました。そして、 「森さんが、強風のなかですごい空を見上げているところを撮りましょう」 という。だいたい私のように普通でもヨロヨロしている人間が、電源車を動かしてしまうような強風のなかで立っていられるわけがない(笑い)。そのことはNHKにもわかったのでしょう。 「考えますから、ちょっと待ってください」 という。そして、近くに共同便所があるから、そこまで行ってください、と。で、私の右手に一人、左手に一人、足も危いというので右足に一人、左足に一人、計四人の人間が私を支えて共同便所の横に連れていったのです。そこで椅子に腰をかけて、「ワァー、すごいなあー」といっていただけのことです(笑)。それで、ともかく親不知の荒海の撮影は無事終了ということです。 |
||
|
||
| 芭蕉が次に行ったところは、市振です。そこに泊まったら隣の部屋に遊女が寝ていました。遊女は、こんなに落ちぶれて、明日もしれない暮らしをしている、せめて生きている間にお伊勢参りをしたい、と一緒の部屋の人に話しています。その話を芭蕉がもれ聞いて詠んだのが 一家に遊女もねたり萩と月 という句です。ここで言う遊女とは、新潟でのことです。新潟を強く出すために、親不知を出して、市振を出して、遊女を詠んだのです。先程、芭蕉は酒田を出てから文章を書いていないといいました。しかし、遊女というのを新潟でのことと考えたら、私は、芭蕉は文章を書いていたと思うのです。芸術家というものは、その土地で不愉快な思いをしたから、文章を書かなかったということはありえないと思うのです。 芭蕉には、別に「銀河の序」というのがあります。 あら海や佐渡に横たふあまの川 という句はそこに出てきます。 「奥の細道」では、新潟のところを外してしまって、市振を強く出しているのです。この市振から、芭蕉は小松に出ます。そこに多田八幡があり、木曾義仲によって納められたという甲兜が祭ってあります。 むざんやな甲の下のきりぎりす と詠んだくらい多田八幡は荒れていました。私たちが訪ねたときは、きれいになっていました。そこに祭ってある兜をNHKは私に被せるという。兜を被りました。鉄の鋳物でできていますからとても重いものです。首が曲がりそうで、こんなに重い兜を被って昔の人は走っていたのかと驚きました。 斎藤別当実盛という人は、はじめ源氏に仕えていました。源氏が滅びると平家に仕えました。斎藤別当実盛は、木曾義仲を子どものときからかわいがっていたので、討ち死にするよりほか申し訳が立たない。ところが、斎藤別当実盛は、髪のまっ白なおじいさんだったので、討ち取ってもらうことができません。そこで髪に墨を塗りました。この話は私どもの小学校時代には国定教科書に出ていました。実盛の首を木曾義仲が首実験します。顔は実盛だが、自分の覚えている実感は髪の毛がまっ白だったはずだというので、水で洗います。そうすると、やはりまっ白な毛だっという話です。 ここで私が、教科書の話を引用したのは、次のことをいいたかったからです。 曾良が、平泉で、卯の花に兼房みゆる白毛かな、という句を詠んでいます。そして、むざんやな甲の下のきりぎりす、の甲は実盛の被っていた兜で、その髪の毛はまっ白だった。二つの句は、白で対応させています。これは大変なことなのです。 大垣へ行きますと、 蛤のふたみにわかれ行秋ぞ と詠んでいます。「奥の細道」は、行春ではじめて、行秋でピシャリと押さえています。春から秋と、行く春、行く秋で押さえています。これも対応の見事さです。そうでなければ、「奥の細道」というわずか百枚ばかりの原稿で、あんなにも立派な構成をつくることはできなかったでしょう。 ところがその芭蕉が、弟子と別れて、一番最後に伊勢にいきます。市振で、遊女はお伊勢参りをするといっていました。芭蕉はそれを振り切って大垣まで来たのです。私たちの凡庸な頭では、伊勢といえば市振の遊女をまず連想します。それは小説の世界です。ところが、芭蕉の非凡なところは、これまでにあれだけいろいろと対応させながら、ここでわざわざそのことを外しています。これは、私にいわせると大変なプロです。見事な対応の妙をみせながら、どこかでスポッと抜かしてある。 先生がたが子どもを教えるとき、ビッシリ教えることを子どもも親も期待しているでしょう。しかし、どこかで息抜きの時間をつくることも大事なのです。「奥の細道」が大作品たるゆえんは、実に見事な対応と実に見事に抜かしてあるところだと思います。抜くことをせず続けて書いていけば小説にはなりますが、後世に残る作品にはならなかったでしょう。 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||