| 150 人物日記 森敦 作家 七十六歳 |
| 出典:バッカス7月号 昭和63年7月1日 |
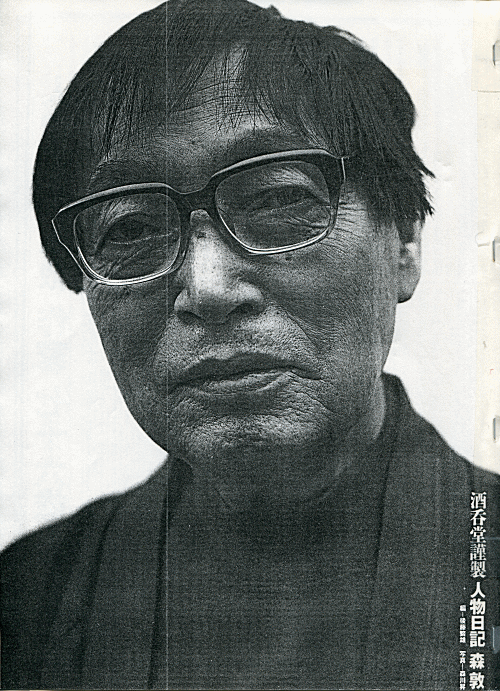 |
| 一九八八年五月の雨の日、私はカメラマンの森川昇氏と市ヶ谷の森先生のお宅におじゃました。先生と親しい、京大人文研の浅田彰氏に案内をお願いした。森先生は放浪の人である。そして稀有な魂の巨人である。先生の描く『月山』の世界、『われ逝くもののごとく』の世界は、おそらく超一級の世界文学と言えるだろう。先生の話は酒田に住んでいた頃、飯田橋の印刷屋時代、その独特のリアリズム論へと展開した。この『人物日記』は、ヒトとモノとトキの興奮を記録する。さてその話の一部をお楽しみいただきたい。 『月山』では金剛界を書いたんです。“月輪”の世界です。それに対して『われ逝くもののごとく』の場合は胎蔵界、“日輪”の世界ですね。胎蔵界大日如来というのは女性ですから、万物を生み出し、万物を破壊する。“一即一切”という言葉があるんですが、それで『月山』を書いた。それで今度は、“一切即一”で『われ逝くもの』を書いたんです。ちょっとむずかしいことをいきなり言ってもいいですか?“一即一切”の一はね、1/nの1なんですよ。それから一切即一の一はn/1の1なんです。1/nとn/1は逆数ですから、掛け合わせると必ずnは消えて1になるんです。だから「一即一切、一切即一、一即一」というんです。これは華厳経のいうところなんです。つまり“1=1/n×n/1=1″ということなんですね。一は単位であると同時に全体です。大日如来は一切のものを生み出して、一切のものを破壊する。そうしてくれないと万物は流転してくれない。その流転を書いたんです。だから、サキっていう若い女の子が小説の中に出てきて巡礼するのは、つまり善財童子ですよ。ボロブドールっていう塔がジャワ島にありますよね。あの塔は善財童子が53人たずねてまわるのを表しているんです。塔をずっとあがって行くと、最後には善財童子もなんにもいなくなって「私」だけになってくるわけですね。『われ逝くもの』はこの塔からイメージしてるんです。 注連寺の横に梵字川という川があるんですよ。それは、湯殿山の温泉から湧き出たきれいな川なんです。その川がキラキラと光ってるわけですね。「われ逝くもののごとく」という題名は、もともと「逝くものかくの如きかな、昼夜をおかず」という孔子の言葉からとったものです。そんな言葉は、孔子のように、人生とか歴史を一体感できる人が言うことで、われわれから見れば、キラキラの「キラ」の方は見えるわけですね。キラキラの一人には僕はなっているわけです。だから「われ逝くもののごとく」なんです。キラキラというのは、現れたと思うと消え、消えたと思うと現れるからキラキラなんです。孔子まではとてもじゃないが僕には行けんけど、キラぐらいはできるんじゃないかと思うんです。それで、僕の生活そのものが「われ逝くもののごとく」の生活ですから。ヴァレリーの「テスト氏」みたいな生活をやってきて、浮身で来とったんですからね。般若心経の最後の方に「ギャテギャテハラソワギャテ……」という合唱する部分があるんですが、あれは、「行かんかな行かんかな、彼岸に行かんかな」ということですから、だから孔子が考えたのが横軸だとしたら、それと直角に交わるところの縦軸が般若心経なんです。だから、仏教と儒教は90度回転させると同じなんです。それで一方は道徳になり、一方は宗教になる。 さきほど1/nの話をしましたが、僕は『われ逝くもののごとく』を書く時にだけ考えたものなんです。僕らはもう、耄碌してますからね、早くからそういう信念をもって書いとったんじゃないんです。二十歳頃、僕は奈良の瑜伽山というところにおりまして、そういうことを考えとったんです。もう忘れとったんです。そしたら書いとるうちに、「あっ、これにはまるな」と思ったわけです。で、そのnは役目を果たしたら1=1になって消えちゃうんですよ。それがここに書いた「われ逝くもののごとく」という名前のついた男の役割なんです。この歳になりますと、新しく発展するちゅうことはもうできないです。だから僕の原稿ほど迷惑をかけるものはないですよ。どんどん書き直すし、思い出したように電話してつけ加えますから。時間的観念も忘れてしまって夜の夜中に編集者の自宅に電話してしまうしね。「われ逝くもののごとく」というのは、キラキラの「キラ」であって意味じゃないんです。変容するもの、人によって違うものです。出版社の人がそんなものをまた書かそうとしているんだけど、そんなところに僕の考えはないんだから。もういやなの、そういうむずかしいことは。なんでもいいからね、これからはバカげた滑稽なものを書きたいんですよ。モーパッサンがね、「ああ、オレはゴール人のバカ笑いを書きたかったんだ」と言って死んじゃったんですよ。今や僕もゴール人のバカ笑いに到達したわけですよ。だから何も期待するなと。哲学もなければヘチマもない。みんなとにかくおかしくて笑ってくれるようなもんだったらなんでも書くんだ。夏目漱石ははじめバカげた滑稽なものを書いとったでしょ。それがだんだん『明暗』に至った。だけど偉いですねえ、漱石というのもつぶれそうでつぶれなかった。でもあの人ほどむちゃくちゃな字を使ってる人もいないですからね。「ばんやりと空を眺めた」とあるんですが、お盆の盆に槍で「盆槍」と書く。そんな「ぼんやり」があるかっていうんです。僕は漱石の逆ですよ。 ピカレスクロマン(悪漢小説)なんていうのは大変なもんです。書けるものなら書いてみろって言いたいようなもんですよ。いやんなっちゃったなあ。このあいだ何とかっていう偉い人が書いたのを寝ながら読んどったんですけどね、突然カウボーイが皆が愉快に飲んでるところにやってくる。テーブルの上に立ちあがって、「皆様、大いに愉快に飲んでください」と──。お金はみんな僕が払います。なんの心配もなく飲んでくれって言うんだ。そして、飲んでおって、誰に迷惑をかけたわけでもないんだけれど、コロッと死んじゃったんですよ。そしたらそこに医者がいたんですね。脳の医者で、あいつのアタマはすこしへンだったから見てみようというんで二人がかりでノコギリで頭をひき出したんですね。ところが、ひけどもひけども骨なんですね。脳がない。それで最後にウメボシみたいな脳がでてきたんです。それで何て言うかと思ったら「モンテーニュの曰く、幸福であるというのは、脳ミソの少ないことである」。でも、そんなコトバはモンテーニュにはないんです。言ってない、ウソなんですね。それまでウソっていうのが面白いんです。こんなことが書けるのは大家ですよ。あんなバカなことを書いてくれって言われたって書けるもんじゃない。 昔は今の比じゃないほど飲んでましたから。朝から一杯焼酎を飲まないと何もやらないという具合だった。戦争中、僕は軍需工場で働いとったんですが、空襲になると軍人たちがふせろって言うんです。あれどういうのか知らんが、軍隊手帳のようなものを額にくっつけてふせとるんです。みんな女の子は騒ぐわけでね。僕一人だけが悠然とこしかけておる。そうすると、女の子はその悠然たる人の手を持ったり、足を持ったりするわけですよ。するとこわくないわけですね。ところが本当は僕は立てなくなっているんですよ。というのは、その頃さかんに福生の工場から航空燃料をもらってきでましたから、その燃料を朝から水で割って飲んどったんです。だからもはやその時はコシがぬけとるんでね。立とうといっても立てないんですよ。こっちもあわてちゃってね、逃げたいんだけれど逃げられないんですよ。偉い英雄みたいに言われたんだけど、コシがぬけとったんです。僕のうちに訪ねてくるときは焼酎ひとビンと、イワシの缶詰を持ってこないやつは入れないことになっておった。で、部屋に焼酎がいつもあったんです。そうしたらある時、若い人がやってきたんだけど、「ちょっと悪いですけど帰らしてもらいたい」って言うんです。焼酎の蒸気が暖房であったまって彼は酔っぱらつてしまったんですね。 朝起きるとまずアスピリンを飲むんです。アスピリンというのは体に非常にいいんだそうですね。つまり血管の先端を開いとるから脳溢血にならない。中学校の2年ぐらいからずっとですね。なんで飲むようになつたかというと、顔面神経痛になったんですよ。風が当たっただけで痛い。ところが、アスピリンやっとると痛くないですからね。もう戦中・戦後問わずです。さっきもお昼にちゃんと飲みましたよ。いつも飲んどるもんを飲まんと調子悪いですから。僕は無頼派じゃないですよ。太宰治や檀一雄らといっしょに遊んどったというだけでね。僕は彼らとろくに付き合わんうちに瑜伽山の方、東大寺へ行っちゃったんですから。まあ、だけど東大寺の方が無頼だったかもしれん。おかげさまで祇園とか宮川町とかに詳しくなっちゃったから、別にお経も読んだりはしなかったけれど、さっき申しあげたように、一即一切、一切即一というようなことは頭に残っている。よくおぼえていないけど頭に残っている。プルーストなんて失われた時を無限に思い出すんじゃないですか。三次元空間に時間が加わると四次元空間にだんだんなっとるんですね。だから骨董なんてほっとけばなんとなく四次元空間になっとるんですよ。だから非常に昔のものをわれわれが見て、今描いたんではとても感じられないものが感じられるのは、三次元に時間が加わって四次元になっているんです。 僕は天草の人間です。だけど、いまや山形の人も僕のことを月山の人だと思ってるんですよ。でなければあんなこと知ってるわけがない。地元の人より知ってるって言うんですよ。そりやそうですよ。普通は道を歩いていても、こういうところから鳥海山がどういう姿で見えるなんて見ないですから。それを書かれると「ありゃっ、よう書いとるのー」ってことになる。だけど、それはウソかホントかどうかはわからない。僕のイメージにあるものなんてホントかウソかわからない。実在の人も出てきますからね。だけど、実在でないものをこの写真だとか、勝手につくって見せてくれる人がいるんですよ。本当だっで彼らは思ってるんですよ。やっとみつけたって。いまやもうそれこそ事態はゴール人のバカ笑いに至ろうとしているんです。 |
|
▼一九一二年、一月一日。すなわち明治四十五年正月に森敦は生まれた。ものごころついた頃、韓国のソウルにいた。二十歳の頃、横光利一の推挙で毎日新聞に「酩酊船」を書く。しかしそれから「月山」までの40年間、彼は作品を発表することなく全国を放浪する生活をおくるのだ。奈良の瑜伽山に住み結婚はしたものの、一人で樺太に渡ったり、漁船に乗り込んでカムチャツカヘ行ったりする。あるいは山形の庄内平野を転々と移り住む。吹浦・狩川・酒田・大山・湯野浜……ほとんどが『月山』や『われ逝くもののごとく』でお馴染みの場所だ。月山の山ふところにある破れ寺、注連寺の隙間だらけの2階に紙の蚊帳をつくり、風をしのいで冬を越したこともある。また、ある時は尾鷲のダムの工事場で働き、またある時は飯田橋の印刷屋で働いてきたのである。なんという自由奔放ぶりであろうか。 ▼森先生の奥さんは、森先生が働くのをいやがった。「働いてくれるなというんです。普通のまったく逆でした」と先生は語る。そして10年働いて10年遊んで暮らすという森夫妻の生活がはじまったのだ。ちょうど10年たったその日に先生は仕事をやめ、そこを去っていく。その生活の様子やエピソードはエッセイの中にたくさん入っているが、とれも微笑ましく、気持ちが洗われるものばかりである。一読をあらためて乞う次第である。 ▼さて、今月号よリ、このバッカスの中に不思議な別紙ページが出現することになった。名付けて酒呑堂謹製「人物日記」。精神的にも物質的にも飽食化した東京で、かけがえのないヒトとモノとトキを編集してまわろうという企画である。一種のライフ・ワークと私は考えている。森先生の話の中の善財童子ではないが、これから私には53人の逢うべき人、話をうかがいたい人がいる。これからが楽しみでしょうがない。 ▼第一回目に森先生をうかがうのは本当に緊張の面持ちであった。しかし、先生は非常ににこやかに玄関に現れた。話は居間でうかがった。その日は、あいにく朝から雨で、撮影がうまくいくかのせとぎわであった。私たちは、自然光でポートレートを撮り続けようと考えていたのである。森川氏は特製の持ち運びのホリゾントを持ってやってきた。インタビューのあいまに、路上にセッティングした特設スタジオで先生のポートレートは撮られた。撮影の時だけ雨が止んだのである。「先生、やさしい顔をして下さいよ」と森川氏がいえば先生は、「僕はニラム男なんだよ」とおっしゃる。周りを車が通ろうが人が通ろうが、毅然とした一瞬であった。 ▼「今年8月の終わりに月山祭があるからいってらっしゃい」と先生は何度もくり返した。今年の夏は月山に行ってみようと思う。理由はわからないが、私は非常に幸福な気持ちである。 ▼「われ逝くもののごとく」は講談社より。3200円。 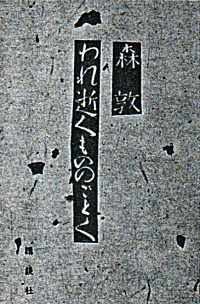 |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |