| 152 物語としての特性 対応と構造から明かす 「われもまたおくのほそ道」を書いた森敦さん |
||
| 出典:西日本新聞(夕刊) 昭和63年10月19日 | ||
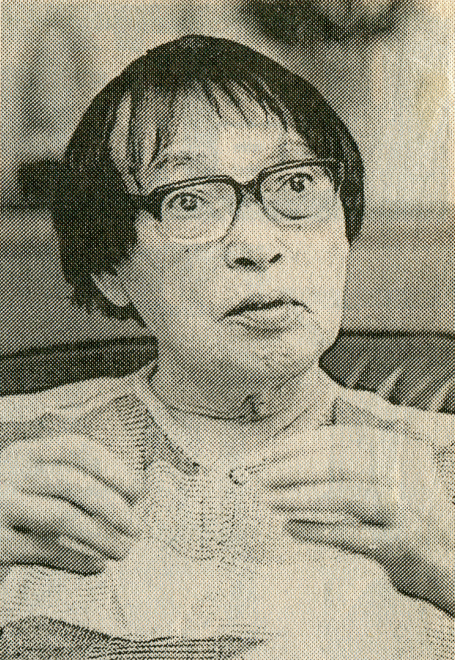 |
||
| 「対応と構造が実に巧みにつくられている」と話す森敦さん | ||
|
||
| 松尾芭蕉が元禄二年に「奥の細道」を旅して、来年でちょうど三百年になる。この間おびただしい注釈書や評論が出ているが、作家・森教さんが「われもまたおくのほそ道」(日本放送出版協会・一、五〇〇円)をまとめた。従来の評論が、多くは俳諧と芭蕉の精神を対象としているのにたいし、森さんは物語としての特性を明らかにし、「物語の本当に良いものは、対応と構造によって成り立っている」という持論を、「奥の細道」に重ねている。 いつもは校正に四、五回も朱筆を入れる編集者泣かせの森さんだが、今回は「僕の放浪した所と芭蕉の足跡がほとんど重なっており、懐かしくもあって一気に書き上げた」と言う。 奥の細道は五年前、NHKテレビの企画「ふるさと歴史紀行」の取材でたどった。 「何冊かの本を読んだが、どうも胸にすとんと落ちてこない。芭蕉も、これは旅行案内記ではない、と言っていることを思い出し、ぶっつけ本番で臨んだ」 |
||
|
||
| それが結果的には良かった。第三章の“草加”を取材中、スタッフが「実際は草加(埼玉県)に泊まらず、粕壁(春日部)=埼玉県=に泊まったのだから、そちらへも回りましょう」と誘った。 「オヤッと思った。なぜ、粕壁を草加としたのか。そこで草加の章をみると“痩骨の肩にかゝれる物、先くるしむ”とある。ハハァ、意識を痩骨へ向けるため、そうかという音を必要としたのだな」 これで構造の仕組みが、一つ解けた。対応と構造の糸口がみつかると、乱麻のような「奥の細道」がするするとほどけていった。 |
||
|
||
| 「月日は百代の過客にして」という書き出しは、李白の「夫、天地ハ万物之逆旅ニシテ、光陰ハ百代之過客ナリ」から採られた。ところが、李白は天地と光陰(月日)とを対応させているが、芭蕉の方は「行かふ年も又旅人也」とつづけて、月日と対応するものがない。 「しかし、芭蕉はけっして忘れてはいない。最終の大垣(岐阜県)では、多くの人に迎えられながら、すぐまた別れる。会者定離です。芭蕉は“月日は百代の過客”に“会者定離”を対応させ、天地よりももっと大きな世界観を示したのです」 森さんは句もまた、第二章の「行く春や鳥啼き魚の目は泪」と最終の「蛤のふたみにわかれ行秋ぞ」が対応していると言う。 |
||
|
||
| 奥州─越前の旅を「奥の細道」にまとめるまで、芭蕉は六年の歳月を要している。この間、芭蕉は「猿蓑」によって“軽み”に達したといわれる。 「奥の細道に旅立ったとき、芭蕉の頭には既に何を詠むかがあった。彼が最も心を砕いたのは、それをどうまとめ上げるかで、まとめたものは現実の紀行文ではなく、手法をこらした芭蕉の世界になった。技巧に徹した芭蕉が“軽み”へと進んだのは当然ではないか」 「奥の細道」で、とりわけ森さんにとって懐かしかったのは、酒田(山形県)から象潟(秋田県)に向かう途中の吹浦の海岸(山形県)である。 芭蕉は「あつみ山や吹浦かけて夕すヾみ」の句を置いているが、森さんはここで新妻の暘さんと新居を構え、松かさや流木を拾っては薪とするような生活を送った。暘さんは働かないでほしいと懇願したという。 「ぼんやりしている私のそばにいるだけで満足しているような女だった」と言う。がむしゃらになりがちな夫を見るのがつらかったのだろう。「亡くなって十数年ですかね…」。森さんの目が遠くを泳いだ。「会者定離、みんな逝ぎてゆきますねぇ」 もり・あつし 明治四十五年長崎市生まれ。旧制一高中退。「月山」「われ逝くもののごとく」など。東京都新宿区市谷田町三ノ二〇。七十六歳。 |
||
| (竹原元凱記者) | ||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||