| 011 永劫回帰の作家 森敦 受賞作「月山」とその周辺世界 高橋英夫 |
||
| 出典:週刊読書人 昭和49年3月11日(月) | ||
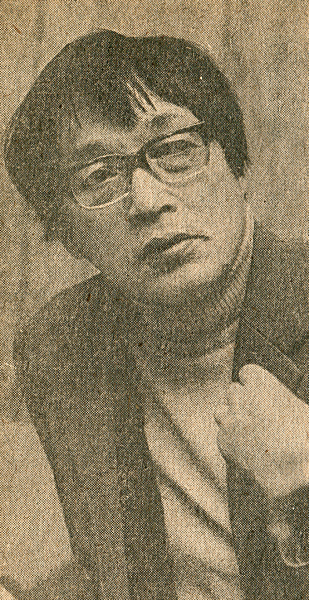 |
||
| 森敦氏。横光利一に師事し、その推輓で昭和九年に処女作「酩酊船」を毎日新聞に連載したが、その後まったく、文壇に登場せず、昨年、突如として四〇年の空白を破って再登場し、たちまち、芥川賞受賞。最近では型破りの作家である。その経歴と六十歳を超えてのデビューは作品の質とともに文壇の話題をさらった感がある。そこで、森敦氏の文学について、文芸評論家の高橋英夫氏に論じてもらった。 (編集部) | ||
|
||
| 森敦氏の登場は大きな話題をよんだ。六一歳という年齢は芥川賞受賞の最年長記録だという。また昭和九年、いまを去る四十年の昔、横光利一の推輓で東京日日新聞(現在の毎日新聞)に「酩酊船」という連載小説をのせたあと筆を絶ち、それ以来の復活というのもたしかに驚かされる。新人という枠をあてがえばもとより桁外れであるが、新人とか既成作家とか言うことを抜きにしても、何か特異な雰囲気が漂ってくることも否めない。それはいったい何から発しているのだろうか。 「月山」のしめくくりに「わたし」の友人が登場し、一冬を月山の雪に閉じこめられたまま古寺ですごした「わたし」は、友人と一緒に山をおりてゆく。そのとき「振り返ると、抜けるように晴れ上がった青空のもとに、皓々と月山が臥した牛のような巨大な姿を見せている。しかも、もう鷹匠山や塞ノ峠、仙人獄ばかりか、朝日山塊と呼ばれる遥かな山々の極みまで、新緑に湧き立っている」というのは、すでにこの世ならぬ別のあの世、死の世界としての月山が掻き消え、「わたし」が再びこの世に帰還したことの徴と読むことができる。おそらくここに森敦氏の世界の独特な回帰性というものを認めてよいであろう。芥川賞選評を読むと、この「月山」の結尾は不用意であり、作品の印象を乱しているという意見が目立った。確かに技術的にはなお工夫の余地はあったのかも知れないが、一旦向うの世界に潜入した人間が、行き倒れのミイラのように二度と帰ってこないのではなく、死から生に復帰したことによって「月山」は霊的な別世界たりえたのだと思う。われわれが真に目を留めるべきであるのは、そんな帰還者、回帰者という人間のありかたである。 |
||
|
||
| 「もし現在に視点を置いて、過去を顧みるならば、それは単に思い出と終るであろう。しかし、過去の任意の時点に視点を置き、今日へと遡るならばいわゆる反復となる。反復は実存哲学の課題とするところであるが、それを実現することができるのは文学である。したがって、文学はいわば人生を二度繰り返す可能性を与えてくれるもので、その生命はいかに現在感に満ち満ちているかにかかっている。」(「受賞のことば」) 四十年ぶりの帰還であると共に死からの生還でもあるという二重の意味で二度目にやって来た人物森敦の面目を、これくらい正確に自解したものはなかろう。「月山」をはじめとして、その姉妹篇とも言うべき「天沼」や、三月号の各文芸雑誌に発表されて、霊峰月山に連なる山なみのような感じのする「鴎」「初真桑」「かての花」にいたるまで、反復のモチーフは精巧に装置されている。たとえば「初真桑」では「わたし」は、かつて芭蕉が来遊して句をよんだ鐙屋という酒田の宿に泊って「取り残されている時間」に身をひたすかと思えば、山容をどこからどう仰げはその本体がとらえられるのか判らない「もどき、だましの鳥海山」の山裾を走る田舎の汽車に身を托して、レールの継目までが「もどき、だまし」と呟きつづけるのを聴きもする。「生だいうても死のもどき、だまし、死だいうても生のもどき、だましなんでねえでろか」という想念のなかで、反復は時空のかまちを超え、巨大な関連に拡大されてゆくのである。「月山」や「天沼」で、雪に埋もれた部落の人々や寺のじさまの動作や言葉が、気の遠くなるような昔から変ることなくこうであっただろうと思わせるのも勿論反復である。「部落の衆はどういうわけかみな小さく、どこがともなく似ているばかりか、じさまになるとなお似て来るのです。それで声を掛けられてもどこかで出会った気はするものの、どこで出会ったか思いだせないことが多いのです」というのも、反復の不気味な翳でなくて何だろうか。月山がもし過ぎし世をあらわしているなら、月山には歴史の反復がある。それなら、それだけでもはやこの世界は単に土俗的幻想の世界ではありえない。さらにもし月山があの世、他界をあらわしているなら、月山には死の反復があると言わなければならないだろう。 |
||
|
||
| 森敦氏は人間の生存が二重の場所と二重の時間とから構成されていることを、作品を通じて語っているのである。ただこの二重性の内容は更に規定し直す必要があるかも知れない。単純に相反する二つの特質、たとえば昼と夜といったものが組み合わされるということではないからである。そこに見出されるのは生と死の綱引きのようなものではなくて、生が死の場所に入りこみ、死が生のなかに異物のように、時には岩塊のように位置を占めるという変幻であり、その不可測性への驚きである、と言うべきだろう。これは単なる死の恐怖とは類を異にする心の襞のかげであり、むしろ「死こそはわたしたちにとって、まさにあるべき唯一のものでありながら、そのいかなるものかを覗わせようとせず、ひとたび覗えば語ることを許さぬ、死のたくらりみ」なのだと述懐されているものが、おそらく恐怖のようであって恐怖でない死の位相の微妙なぶれであり、そのぶれにおいて森氏の独自性が雪間の花のように,日本海から吹きつける浜風に舞う鴎のように、目に飛びこんでくることになる。 人生は繰り返しであるという森氏の言葉には、意識的無意識な含意が二重どころか三重四重に折りかさなっている、と言わなければならない。文学はいかにも人生をもう一度生きるものであろう。しかし当の人生こそ文学以上に反復であるというのは、過去の忘れ難い何かをただ反芻すればそれで反復だというわけにはゆかないからである。同じことを反復したとき、白分が決定的に過去とは違う別の自分になっているのに気付かされることが、本質的に反復なのであり、そのとき人はあの「死のたくらみ」を意識する。二度目にやって来たのも確かに最初のときと同一人物のこの己れである。しかしそれにもかかわらず、この二度目の己れはもう以前のあの人物ではない。これは解決不能な生の根本的矛盾であるが、「月山」を主峰とする森敦の作品世界と森氏の人生流離は、そういう生の矛盾それ自体をあらわしていることは疑いえない。反復は生の表標にはちがいないが、そこで反復が成立するのはたとえば子が父を継続し、父が祖父を継承するといったパターンの模倣と拡大によってであり、そうである以上は反復それ自体のなかに、生のみならず死が含まれずにはいないのである。死を排除した反復は、では永劫回帰であろうか。しかし私には、永劫回帰こそ死を含有した反復を意味するのではないかと思う。「わたしはあの肘折のまどかな月山が、いよいよまどかになるというのを思いだしながら、ふとまたここでも、こうして眺めていたことがあるような、気がして来るのです」と物語られる月山の尽きせぬ秘奥の感じこそまさしくそのようなもののシンボルである。 |
||
|
||
| 生が死を模倣し、死が生を代行する転換の構造と同じように、文学と人生のあいだにも、人生を言葉の内部に封じこめる置換操作を通じて文学が成り立つということを、ここで言い直す順番であろうか。しかし文学による反復が成立する条件は、生における反復の条件よりもいっそう厳しいのかも知れない。生におけるそれが普遍的条件だという意味では、文学のそれは完全に特殊な条件だからである。「月山」を主峰とする一連の作品は、言語的統一と爛熟によって、森氏が自分の特殊性を見出したことを、つまりそう言ってよければ天分を発見し了ったことを示しているが、たまたま四十年前の作品「酩酊船」が復刻されている(「サンデー毎日」二月十日号)のを読むと、青年森敦が文学における反復をすでにその時、苦しい姿勢で手探りしているのが知られ、この問題がこの作家の根本問題であったことを確認せざるをえない。「酩酊船」においては、旧制一高を中退した主人公は絶望からの脱出のために伊豆大島に旅に出、船中知合った島の茶屋の女と親しくなるが、女の身上話によって元の自分に突きおとされてしまう。そしてその女だけでなく、過去に知合った女たちの幻を思いうかべながらランボオにならって「酩酊船」という小説を書こうと決心するというのがその荒筋である。おそらく相当に体験的事実に拠っているであろうが、それ以上にこの小説は一高中退だという森氏の先輩にあたる文学者たちの、あまりにも大きな影響を露呈しているのを感ぜざるをえなかった。希望と絶望の交錯のなかでの伊豆や小笠原への脱出は藤森成吉、川端康成、小林秀雄にすでにあったものである。中島敦の初期作品にも「下田の女」があった。(因に、中島敦は森氏と同じ京城中学出身である。)そして引用されているランボオは勿論小林秀雄訳である。終章で主人公が下宿の窓から隅田川のポンポン蒸気を眺めるのも余りにも小林秀雄的ではなかろうか。そして「酩酊船」を書こうとすることで「結末ならぬ結末」を奪取しようとする「酩酊船」は言うまでもなくジイドと、横光利一なしでは考えられない。しかし、このことは逆に、若き森敦は余りにも直接的な反復に破れたのだと見ることを可能にするであろう。反復の条件を熟させるには青年は性急にすぎるにちがいない。 「成程、私は生活に犠牲と目的を高調して、酩酊船を書かうとしたのだが。私は一塑像家としてその主人公を、心のなかで、紙の上で、作りあげてゆけばよかったのだ。それに私は、いつのまにかその主人公自身にまで、ならうとしたのだ。」 それならば森敦氏は最初から何をどうすべきかを知っていたのだと言える。それが判っていても、実際その通りに出来ないのが文学的条件だからである。こうして森氏は、文学の捨象においてつねに主人公自身である道を、登場人物である道を選びとり、四十年が過ぎていったのである。しかし今、皓々たる月山の雪景に立つ「わたし」は「一塑像家」であることと「主人公自身」であることの二重の役割をぴたりと重ね合わせて、流石に陰翳のふかい生そのもののすがたのように眺められる。それは再び換言すれば、文学と人生の関係もここではすでに「あそこからすればここが彼岸、ここからすればあそこが彼岸」(「鴎」)という変幻に達したということでもあろう。(たかはし・ひでお氏=文芸評論家) |
||
|
森教の主要作品 ◇「月山」は「季刊芸術」26号に 掲載、芥川賞受賞後「文芸春秋」三月号に。さらに河出書房新社から「天沼」(「文芸」新年号)と併収し単行本「月山」 (七八〇円)となる。 ◇「初真桑」(「文学界」三月号) ◇「鴎」(「文芸」三月号) ◇「かての花」(「群像」三月号) ◇処女作「酩酊船」は「サンデー毎日」2月10日号に抄録。 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 書評・文芸時評一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||