| 013 死からの再生描く傑作 森 敦著 月山 |
| 出典:サンケイ新聞 昭和49年3月25日(月) |
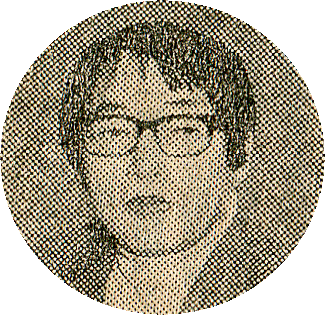 |
| 森教氏の『月山』は、すでに諸家の間で名作の評判が高く、この上わたくしが何をいっても、なくもがなの蛇足に終ることだろう。若き評論家の谷崎昭男氏は、このごろの評論家はどんなすぐれた作品に対しても「傑作」という折紙をつけることを躊躇(ちゅうちょ)するようだが、自分は敢えて『月山』を近来の傑作といいたい、という意味のことをいっているが、老作家の私もそれに賛成したいと思う。 私はこの作品を読みながら、ふと羽黒の「秋の峰」の行事を思った。それは羽黒権現(いまの出羽神社)の大先達に導かれて、月山の沢や渓谷を他界(死の世界)と想定して巡歴する修行であり、その期間はいまは十日ということになっているが、古くは秋の初めに山に入り、冬を経て、春になって山をでてこの世に再生するのであった。森氏の『月山』の主人公の「わたし」も、月山を死の山といっているが、その死の山に秋の初めに入り、冬の間はカンジキをはいて吹雪に抗しながら沢や渓谷を経めぐり、春になって山を出るが、それはいかにも「秋の峰」の行事によく似ているではないか。「わたし」はそのことを知ってか知らずにか、秋から冬にかけて他界(死の世界)での修行を終り、春になって山をでてこの世に再生することになるが、わたくしにはそのことに興味の尽きないものがあった。「わたし」が冬の寒さをしのぐために和紙で蚊帳(かや)を作り、繭(まゆ)のなかの蚕のように蚊帳のなかで暮しているという話も、さながら彼が死を演じているようで感銘が深い。 しかしこの小説の何よりの面白さは、「わたし」が寄寓している七五三掛(しめかけ)という部落の住民の生態が、漱石のいわゆる「非人情」に近いような眼で挑められ、巧みにいきいきと語られている点にあるだろう。しかしそのことに就いて詳説している暇はもうない。なお本書には、同じく月山のことを書いた『天沼』という作品が収録されている。 |
| (河出書房新社・七八〇円) 作家 中谷 孝雄 |
| ↑ページトップ |
| 書評・文芸時評一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |