| 074 日本人の基層描く長編 森 敦著 われ逝くもののごとく |
| 出典:日本海新聞 昭和62年7月6日(月) |
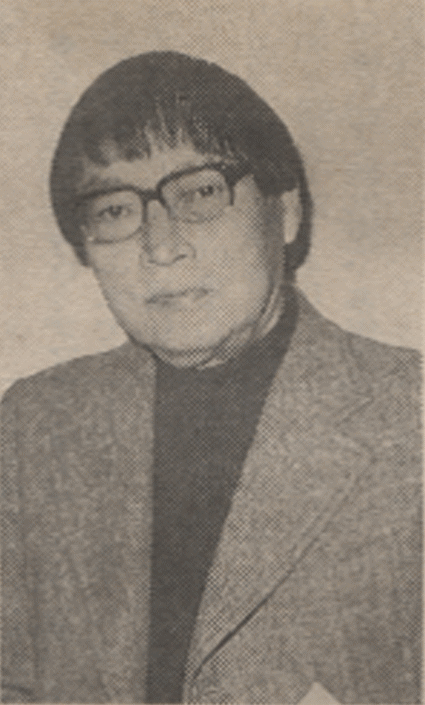 |
| 作者は小島信夫氏との対談で、この長編小説では「善男善女」のことを書きたかったと語っている。ということは、特定の人間を描くのでなく、「人々」のことを描かなければならない。 それだけでなく、特定の人間の身の上に生じた悲劇や喜劇をではなく、「人々」のただの生き死にを書くのでなければならない。作者はこの作品において、そうした困難さに挑んでいる。 作品の舞台となっているのは、山形県の庄内平野の一角にある加茂という町である。 その町に住む若き父親の「だだ」が出征し、戦死してしまうところから、この物語は始まっている。だが「だだ」は、この作品の中での主人公ではない。彼の死は、この作品の中に次々と出てくる死の中で、たまたま一番目のものであったにすぎない。 息子「だだ」の死を信じることのできない「じさま」は、その真相を神様にうかがってみようと思って、庄内平野のあちこちを回っているうちに死んでしまう。続いて「だだ」の母親である「ばさま」が死に、さらに「だだ」が結婚前に関係したことのある遊女の「お玉」が、「だだ」の後を追うように自殺する。 論語から採られた「われ逝くもののごとく」という題名は「死」を意味しており、その言葉の通りに、この作品の中では「善男善女」たちが、ポツリポツリと死んで行く。だが作者は、そこに何かの意味やテーマを見いだすことなく、「人々」の死を淡々と記述して行くだけである。 その点でこの作品は、柳田国男の「遠野物語」や深沢七郎の「笛吹川」に似ている。この作品の直接の舞台は庄内平野の各地に限られているが、それを超えた広がりがここにはある。その点でこの長編小説は、日本人の基層を描いたものと言えるだろう。 ここでは、ソロではなくオーケストラの方法が採用されているが、これも「人々」の死を描くという作品の意図にかなっていると思われる。 (講談社、B6判、六九二ページ、三二〇〇円) |
| ↑ページトップ |
| 書評・文芸時評一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |