| 080 文芸時評 土着性離れて流体化 森 敦氏 『われ逝くもののごとく』 |
||
| 種村 季弘 | ||
| 出典:朝日新聞 夕刊 昭和62年7月27日(月) | ||
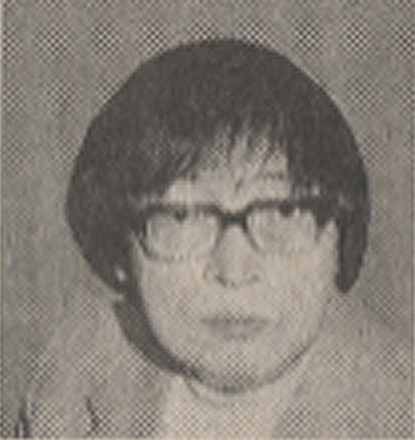 |
||
| 森教の長編『われ逝くもののごとく』(講談社)は、大まかにいえば月山と鳥海山に南北をはさまれた庄内平野の、それも日本海に面した庄内砂丘が舞台であり、おそらくはまた主人公でもある。主人公とひとくちにいったが、小説を最後まで読めば、かりに土地を擬人化するつもりなら「ヒロイン」のほうが正確であると知れよう。 ただしヒロインはほぼ不動のままに最終部まで隠されている。それを隠されたままにして、ひとまず物語の前面を庄内平野のすみずみまで駈(か)けめぐるのは、サキというローティーンの少女である。これは、庄内平野を背景にした少女の通過儀礼の物語とも、アリスとともに見聞きする不思議の国の庄内版とも、いえようか。 |
||
|
||
| おびただしい数に上る人物が登場する。しかしどれだけ人物の数がふえても、それは、「われ逝くもののごとく」という奇妙な名で呼ばれる、たった一人の人物の微分的な分身にすぎない。というより人物たちは「われ逝くもののごとく」に自覚的に同化することをうべなった瞬間に、次つぎに、はためには唐突に「逝ぎて」(死んで)しまう。すなわち死を自覚しない数人を例外として、庄内人たちはみるみる「われ逝くもののごとく」に感染して、その生と死との閾(しきい)を往き来する軽やかな足どりをまね、持ち前の土着性を離れて流体化してしまう。 こうして庄内弁のばさまたちの茶飲み話の話体で語られる人物たちは、堅固な大地を離れておやみなく流れるものとなる。ほとんどすべての人物たちが、「われ逝くもののごとく」をはじめとして、文字通りの流れ者、やっこ(物乞い)、捨て聖、娼婦、漁師、闇屋、行商、のような人びとからなるのも、理の当然であろう。土地に根づく豪商、小作は、かえって風の便りのなかの消息の人のように遠のき、ゆるぎない農作地帯の庄内平野が、農耕文化以前の原初のゆらめく流体空間の上に蜃気楼(しんきろう)のようにはかなく架かっている。われ逝くもののごとく。 流れるものが堅固な大地を支えている。しかしそればかりではない。手入れの行き届いた大地母体がなければ、それに寄生する流れ者も生きてはいられない。なにごとも一筋縄ではゆかず、作者の別のところでの発言を借りるなら、「命題たり得るものは、つねに相反する意味を孕むものでなければならぬ」。だからこそ善男善女が流れ者をミイラに仕立てて、それをショウ化しては人寄せしたりするのだし、彼らの聖山信仰が善男善女をして、共同体の外からは悪としか見えない共同体内部の祝祭を焚(た)きつけたりもする。 |
||
|
||
| こうして8の字状のメビウスの帯に沿って、読者は聖地巡礼行におけるように、外部から内部へ、内部から外部へと物語空間をくまなくへめぐり、やがていつしか物語の外へ出て、それが戦中戦後から高度成長期前までの、すでに「逝ぎた」時空の出来事であったことを知るのである。いま三十年の歳月をへて、当時の善男善女の魂をたばねていた寺社は観光化され、代わって彼らの冠婚葬祭をとり仕切るのは、「軽薄な合理主義者」の経営する仏壇屋、レストラン兼結婚式場コンツェルンである。資本主義化された庄内平野。あの不動のままに隠されていたヒロインも、いまは個人の記憶のなかに隠されているにすぎず、記憶の保持者の老いにつれて、それも「逝ぎ」、消滅するだろう。 物語の終わりに語り手は、一人の土木工に変身して、土地の源泉たる鳥海山中の十二滝を破壊する。破壊、であって同時に、かつての流体空間はこのとき一気にこの小説の言語空間そのものへと転換され、こうして作品は、大らかに開いたまま閉ざされるのである。 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 書評・文芸時評一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||