| 086 小説 ことしのベスト3 自らの信念に集中 『われ逝くもののごとく』華厳経的世界観 |
||
| 高橋英夫 | ||
| 出典:読売新聞 夕刊 昭和62年12月15日(火) | ||
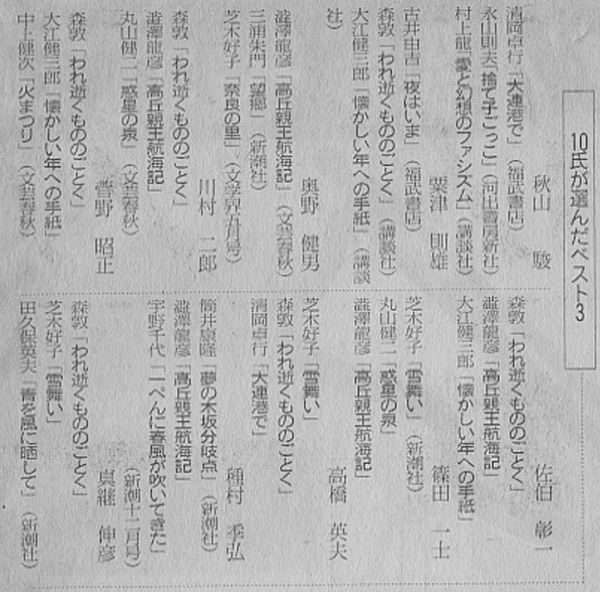 |
||
|
||
| 数年来、目立った現象として誰もが口にしたのが女流作家の活躍、二十歳代の新人作家の進出である。今年をふりかえってみて、同じような傾向が続いていたといえそうにも思われる。しかし十人が選んだベストスリーの作品を集計してみると、それらはそれほどはっきりとは表面に出ていないというのも事実だろう。女流作家では芝木好子、宇野千代の二人が入っているが、両氏とも大ベテランで、近年マスコミの話題となることが多かった中堅以降の女性の作家とは異なる。また若手ということでは二十代の作者は一人も挙がっていない。一番若い村上龍にしてもすでに三十代半ばに達している。そこで人によっては、このアンケートの集計結果を保守的と取るかもしれない。 一面ではそう見られるのだが、しかしこれは今年の特徴を暗に物語っているだろう。既成の、方法と文体を確立した作家たちがそれぞれに持てる力を揮(ふる)い、実質に富んだ作品を提出したのが今年であった。いたずらに右顧左眄(うこさべん)せずに、自らこれが文学と信ずるものに集中していった作家のすがたが透けてみえる感じがする。 一番多くの支持を集めた森敦『われ逝くもののごとく』がその好例である。一即一切という万物融合の華厳経的世界観を物語として表したのが『われ逝くもののごとく』で、舞台は山形県の庄内平野──こう記せば、これは森教を最初に印象づけた『月山』を連想させる。『月山』で文壇に浮上したとき既に確立していた世界観を、より大きな規模でえんえんと語ったわけである。この世界観が現代人に愬(うった)えかける力は大きい。と同時に、方言を駆使した太い声のひびきには一度耳にしたら忘れられない調子がある。 加えて三つめの特徴として規模の大と関連した形式無視ないし八方破れの進行が指摘できる。たとえばそれまで舞台裏にいた作者の「わたし」が、最後になると作品舞台にとうとう上ってしまう、といったことである。しかしこうしたハップニングも今日の人間が積極的に求めているものに他ならない。また静止状態のときには無形式に見えるものも、生きた語りの流れの中に入ると破綻(はたん)でなくなるという意味からも、この作品の現代性を読者は感じとったのではないか。(以下略) |
||
| ↑ページトップ | ||
| 書評・文芸時評一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||