| (文 森富子) |
| Part 18 |
|
|
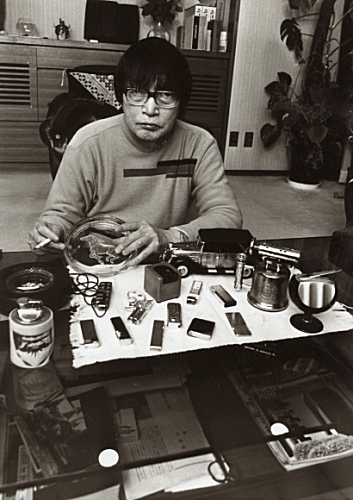 |
| ライターを前にした森敦(71歳ころ)。 |
| 撮影者不明。グラビアを飾った写真と思われるが、掲載誌を探し当てられなかった。 「森敦遺品覚書」Part10に「*ライターの数々」の写真と同じライターが並ぶ。手に持つ灰皿の左手前の紐つきライターは、NHKのTV〈森敦おくのほそ道行〉のロケの際に、「ライター、ライター」と騒ぐので、ディレクターの伊丹政太郎氏がライターを土産店で買って、首にぶら下げたという。民芸調で首に下げられるとあって、家の中でも愛用した。撮影は、第1回が昭和58年(1983)5月5日~9日、第2回が同月27日~30日、第3回が6月7日~11日、第4回が同月13日~17日に行われた。 手に持つ灰皿と左前の灰皿は、「森敦遺品覚書」Part9の「*灰皿」④と①に同じ。 エッセイ「私の趣味 ライター」(昭和51年12月23日号、「週刊現代」、注・『森敦全集』未収録)の全文を掲げる。 〈ぼくの煙草はテレビ局でも公認になっている。台本にも「煙草を持って登場」とあるだけで、ぼくのには科白はない。一日に二百本も吸うと言うものだから、こんな次第になったのだが、原稿を書くときなど、一口吸うだけで揉み消すこともあれば、一口も吸わずに灰を伸ばしていることもある。正確には、日に二百本火をつけるというべきで、机にはいつもライターがごろごろしている。国産品はむろん、ブラウン、ダンヒルと海外にまで及んでいるので、テレビ局のひとたちはライターの収集がぼくの趣味だと思って、競ってライターを持って来てくれる。ところが、そんなひとたちが煙草を吸おうとして、机のライターを取り上げても、どれも火がつかない。つかないはず、ガスが切れると机におっぽって置くので、そんなときにはニッコリ笑って、ポケットから新しいライターを出し、ぽっと火をつけてやる。じつは、これがほんとのぼくの趣味なのである。〉 放浪中に寝煙草で布団に火がつき、外に出して水をかけたが、火はなかなか消えなかったと、煙草の火の怖さを語っていた。しかし、首にかけたライターで家のあちこちで煙草に火をつけて、一服するとロッカーや暖房器具の上に置いた。吸い口だけ置くので、床の上に落ちて、煙草の形の灰が残った。灰を取り除くと、煙草の灰の長さの焦げ跡。その焦げ跡が、暖房器具があったトイレやロッカーのあった廊下に、いくつも残った。書斎や応接室にも灰皿からこぼれ落ちた煙草の焦げ跡がついた。「見てごらん、これ煙草の記念碑?」と、指差しながら言ってもそ知らぬ顔をした。 勤務していた会社から家に近づくにつれ、家が火災で焼け落ちているのではという不安に駆られた。急坂を上ると十字路がある。左に曲がるとわが家だが、立ち止まって首を伸ばして左をのぞく。「あっ、家があった」と安堵して、家に向かったものである。 やかんや鍋の空焚きをしたり、煙草の火の不始末をしたり、それでも失火しなかった。森敦は火災に運のいい人であった。 |
 |
| 対談中の森敦(65歳ころ)。その一。 |
| 撮影者不明。対談か座談会かでの一齣。テーブルの上にご馳走が並んでいるが、ほとんど食べなかったという。帰宅すると、いつもどおりに晩酌をし、素材料理を食べた。料亭料理を食べてくればいいのに、なぜか食べてこない。「どうして、手をつけてこないの?」と訊くと、応えた。「ぼくはね、一流料亭の料理は、一生分食べたからね。電発で土地交渉をするのに、毎晩、尾鷲の料亭で飲み、食べていた。飲んでいるうちに、交渉相手が酔ってくる。すると、電発の若者が囁く。森さん酔ったふりをしてください、と」 同席している記者や編集者のみなさんには迷惑をかけたようだ。「サンデー毎日」に対談「問答縦横」を連載していたとき、担当記者と京都に行き、記者とともに超有名料理店で会食したときの話だ。一品ずつ出された料理に箸もつけない森敦に、料理長が「食べないのなら、出て行きなさい」と怒鳴ったという。 東京築地の灘万での対談がすんで帰宅したときの話だ。ご機嫌で家の中に入ってきて、「美味しかった!」と笑顔だ。空耳かと、「えっ?」と訊くと、「なんとも言えず、美味しかったよ」と声を張り上げた。信じがたく、「そんなに美味いなら、食べに行かなくては!」と言って、帝国ホテルの新館にある灘万に行った。帰宅して「本当に美味かったわ。舌音痴ではなかったのね」と言った。 常々、南天の葉などを飾りにしたり、付け合せをのせたりしてはいけないと言った。料亭やレストランの真似の禁止だ。 一口食べてまずいと残し、言葉では言わない。「明日、食べますか?」と訊くと、「捨てなさい」と言う。食べられるものにお詫びをこめて手刀を切って、「では、捨てさせていただきます」と台所に運んだ。 トンカツを多く作って、翌日、煮た玉葱の中に、切ったトンカツを入れ、溶き卵を半熟状にして出すと、「昨夜の残り物は食べない」と言う。 注連寺で一冬過ごしたときの大根の味噌汁がつらかったらしく、大根を煮るような料理は食べなかった。漬物は食べなかったので、大根おろしをどんぶりに入れて出すと、汁だけ吸って、かすを残した。栄養は、かすにあるという理屈だ。 |
 |
| 対談中の森敦(65歳ころ)。その二。 |
| 前掲写真の一連のもの。上着を着ている。
|
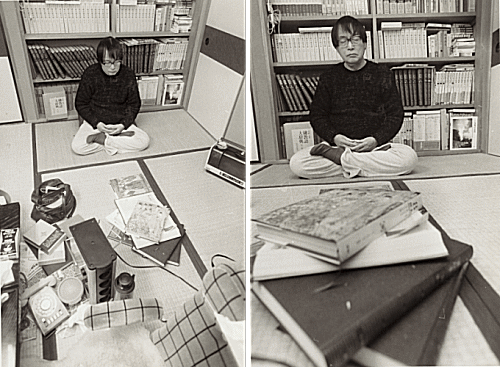 |
| 書斎の書棚前での森敦(71歳)。 |
| 撮影者は鯵坂青青氏。読売新聞(昭和58年3月5日夕刊)のコラム「マイ・サイドライふ 31」に増永俊一氏の文とともに掲載。 全文は「森敦インタビュー・談話」に載せるが、インタビューの一部を掲げる。 〈「瑜伽とはいま流行のヨガのことなんですよ。ぼくは逆さまになったり、ねじったりはしない。黙って座るだけです」 「結局、華厳の境地は恍惚感と心機高揚なんです。人間が朝起きて日がよく照っていて、明るい朝を向かえると、目覚めは何ともいえない気持ちになる。お釈迦さまはある日、夜明けにはっと気づいた。それを大いなる目覚めという。われわれも小さいながら、天気に恵まれると、瞬間的恍惚感に入るんです。ぼくは原稿の締め切りが近づくと、瑜伽をやる。すると、華厳でいう美しい目覚めに合致するようになり、書く意欲が出てきて、一気に書くんです。」〉 |
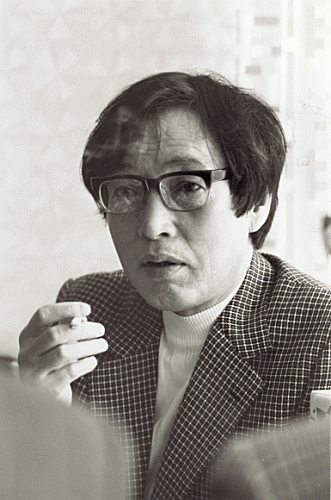 |
| 談笑する森敦(65歳)。 |
| 撮影者不明。 身につけるものいっさい、むすめが選んだ。ダンディーだと自称していた。弊衣破帽はバンカラな服装で、バンカラはハイカラをもじった言葉。ダンディーとは、バンカラでハイカラかと理解した。 珍しく好みを言った。「ハイネックのセーター、それも白がいい」と。一日で襟が真っ黒に汚れるのだ。家での撮影は、「カメラマンは上半身しか写さないから」と言って、家庭着のトレーナーの上に上着を羽織っていた。顔写真を見るたびに、ズボンがわりのトレーナーが思い浮かぶ。 森敦の言うダンディーとは、なんだろう。 |
| ↑ページトップ |
| アルバム一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |