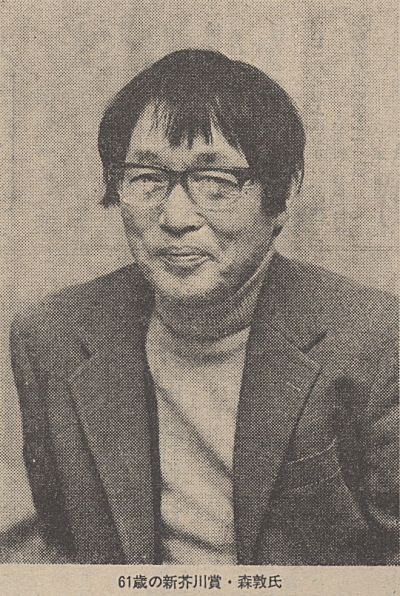
当時──といっても、同人雑誌が氾濫した戦争直後の一時期だけを指すのではない。正確にいうと、その教祖歴たるや、昭和10年代にまでさかのぼって行く。
なにしろ、デビューが早かった。当時、文壇の大御所といわれた菊池寛、横光利一らに見出され、旧制一高中退後、毎日新聞に「酩酊船」を連載したのが十九歳のとき(昭和10年)。文学者仲間には、太宰治、檀一雄氏らの名がみられ、とくに師事した横光利一とは、
「本当に彼をかわいがっていましたね、横光さんは。だいたい寡黙なんだが、彼が行くと饒舌になり、毎晩のように銀座を飲みに連れ歩いた。横光邸なんかでも、文学者仲間があつまると彼がいちばんいい席に座っている、といった具合にね。中山義秀さんなんかはそのころまだ苦しい時代だったから、おもしろくなかったでしょうが」(友人の話)
思想家。数学のできる人。奇才。柔道の達人。雄弁家。漢学者。哲学者etc……が、このころ森敦氏にたてまつられた形容詞。──その“横光門下の俊秀”がなぜ筆を絶ったのかは後述するとして、戦後の教祖ぶりを、もうひとつ紹介しておこう。
ふたたび島尾氏の話。
「戦後、新しく加わったのは斯波四郎、小島信夫氏らですね。とくに小島氏は、『アメリカン・スクール』(注、昭和29年下半期芥川賞受賞作)を書くときそのころ大久保にあった森さんの下宿をたえず訪れ、たとえば作品の冒頭で『まがった道……』うんぬんの個所を、“まっすぐな道としたほうがよい”という森さんのアドバイスで書き改めたといいますね。さらに、『島』を書くとき、当時、酒田にいた森さんを訪ねて教えを乞うた、ともいわれています。だから、小島氏が芥川賞をとったとき、受賞式の自分のとなりの席をあけておいてくれ、といったくらいなんです。森さんは、しかし、姿を現わさなかったですが……」
とにかく、こんな具合で、森氏が放浪していたころは、「彼の所在が知れると、東京の文学青年たちがそのあとを追いかけまわす」(島尾氏)といったありさま。──昭和34年春、三重県尾鷲へ電源開発工事の取材に行った三好徹氏(作家=当時、読売新聞記者)は、そこで渉外係をしていた森氏とはじめて会った。
そのときの印象。
「夜、お世話になったお礼にと一緒に飲んだのですがね、昼間は“いい人だな”くらいに考えていたのが、だんだん“これはただの人じゃないぞ”と思うようになった。変りもの、といった感じじゃなく、むしろ天衣無縫で、なにものにも束縛されない自由人、という印象だったですね。酒好きの、放浪癖の強い人ですが、知識は古今東西、ギリシャ悲劇から中国の古典にまでおよんでいる。ただ、なんというか、とらえどころがなくてボクは“現代の仙人”とよんでいますがね」
とらえどころがない、という点では、まず第一にその正確な経歴がわからない。以下、ご紹介するのは友人、知己の話を総合したもので、ご当人にはまったく記憶がない。というよリ、そういう年代記的な話には興味がないのである。
たとえば、インタビューにたいする森氏の返答はかくのごとし。
「電源開発?……ウーン、あれはいつだったかなあ。ええと、そう、三好君に会った年だな。あれは……どうだったかなあ。月山? ……ハイ、行きました。年ですか? あれは……昭和ですよ。昭和……何年だったかなあ……。25、いや、26年かな。(申しわけなさそうに)そうです。そういうことなら小島君に聞いて下さい。小島君なら、いちばんよく知ってくれていますよ」
小島信夫氏にたずねてみなければならない。小島氏によると一高受験のため浪人していたころ、森氏の「酩酊船」を読んだ記憶があり、また、当時受験雑誌として名をはせた『考へ方』の臨時増大号(受験小説特集)で、「一高生森敦」が受験生を相手に雄弁をふるった講演速記をも読んだことがあるという。
小島氏がこう語る。
「とにかく、ひとくちにいってしまえば、前代未聞の人です。ボクが森さんと知りあったのは同人雑誌『同時代』をやっていたころでね、昭和24年ごろから親しくなった。横光さんの弟子だというが、むしろ横光さんのほうが影響をうけたんじゃないかな。いろいろな伝説のある人で、柔道が強くて達人だとか、数学にこっていて、本棚には数学の本しかないとか、あまりに俊敏すぎてウワサも多く立つ。
ボクは森さんが小説を書かなかったのは、能力がありすぎてかえってなにか小説に足りないものがあったから、と思っているんです。たとえていえば、あの人は江戸時代の三浦梅園(注=儒医、天文、物理、医学、経済など諸学に通じた人物)みたいな人物ですよ。大げさにいえば中国の孔子。──それに、六十一歳という年齢にしても、下世話なことにはまったく関心がなくて、たえず宇宙はどうかなどと考えてきた人だから忘れはてていたのじゃないかな。気がついてみるとそういう年齢になっていた。だから、『月山』という作品にしても、なぜ年をとってからあんなに若々しい作品が書けるのかとみなはフシギがるけれども、ボクにしてみれば当然のことなんですよ」
風変り──という点では、まず父親がそうだった。
明治45年、能本県天草生れ。四人兄弟の三番目。一家をひきい、京城で大陸浪人の生活をおくった父親は、
「よく、この世のなかでオレは軍人と芸者以外はみなきらいだといってました。なぜか、とききかえすと、この連中は返事と姿勢がいいからだと。そのくせ女房にもらうなら、女郎はいいが芸者はいかんどいいましてね。まったく矛盾撞着したことをいってましたよ」(森氏)
京城中学に進み、ここでまず第一の《伝説》ができあがる。
いわく、
「中学校の柔道選手権で、大将戦に出場。惜しくも敗れたが、その相手はのちに柔道の天才といわれた木村政彦氏(拓大コーチ)」
昭和9年春、旧制一高入学。
「文科甲類」といえば英語が主のクラスで、将来は高文をパスし高級官僚を夢みる志望者が多いのだが、そのなかで、「ボロボロの帽子をかぶり、ラッパズボンに両手をつっこみ、ロイドメガネごしに人の顔を穴のあくほどみつめる。校内を闊歩しては、『新青年』に原稿をたのまれただの、横光さんの親友だなどといってボクらをケムにまいていた」(同級生の太田克己氏=都立深川高校教諭)
という森氏はまったく異色。風貌は当時でも三十代にみえ、「ボクらがまだ幼かったせいもあるが、森君だけはたいへん大人びた印象」(山之内一夫氏=学習院大教授)だったらしく反発するものも多かったが、逆に心酔者も少なくなかった。
「授業にはほとんど出なかったですねえ。森君は出席日数が足りなくて教授会で“放校処分”になったのですが、これなんかいかにも森君らしいと思っています。──当時、一高には丸山通一というドイツ語の名物教授がいましてね。この授業では彼はいつも三百枚ぐらいの原稿用紙を机のうえにおき、毎日新聞の連載を書いていた。丸山さんはひとこともいわなかったですが教授会では“断固、森を追放する”といきまいたそうですよ」(同窓の北川悌二氏──東大教授)
文学の若手旗手としての気持の昂揚もあったのだろう。ここでも、また《伝説》があって、
「一高同窓生のうちで行方不明が二人いる。そのひとりは共産党員だった伊藤律で、もうひとりが森敦」
事実、前述の太田氏によると一緒に雑誌『新生』にたずさわっていた昭和24年ごろから消息がわからなくなり、森氏がやっとクラス会に顔を見せたのは昨年11月。「二十五年ぶりのことだ」という。むろん、その間、文学的にも空白の期間がある。
東大寺・上司海雲管長の話。
「あれは、戦争がはじまる前のことで、志賀(直哉)先生のお弟子が“横光さんのところにいる天才児だ”といって森さんをつれてきたのが最初です。少し変っているな、という印象でしたな。いい小説を静かな環境で書きたいと、半年ばかり毛筆で丹念に原稿を書いていました」
この作品は、モノにならなかったらしい。とにかく、ここでも一風変っていたことは「華厳、律などの経典は本職の僧侶よりもくわしかった」ことだったという。
そのころ、奈良で知りあった旧家の娘と結婚。「横光さんの媒酌で式をあげたとき、本人が行方をくらましてしまった」(前述の島尾氏)のも奇矯だが、それ以後、小林多喜二の『蟹工船』が真実かどうかをたしかめるために樺太に渡ったり、持ちまえの放浪癖からカツオのつり船に「何となく乗る」のもどこか風変りではある。
友人の島尾氏によると、森氏が本当に筆を絶ったのは昭和26年だという。
「そのころ、森さんは一つの作品を書いたんです。これがさっぱりわからない。“ついに頭が変になった”などと批評されたもんです。森さんは“キミらの頭がおかしいんだ”といっていたが、時間をおいて自分で読んでみるとさっぱりわからなかった。──当時、森さんはカストリを飲みすぎて中毒気味となりそのせいではないかと思って、ガクゼンとしたそうです」
その直後、ひとりで山形県の月山へ。それから丸二年、月山の山中で何があったかは知らない。「あいつはどうしたんだ。まさか永住するつもりじゃ」と案じた東京の文学仲間を代表して、秋田嘉雄氏(TVKテレビ営業部局長)が迎えに月山の注連寺に行ったが、
「本堂の暗闇から出てきた彼の姿をはじめてみたとき、“幽霊だ”と思いましたね。ドテラのような粗末な着物で、雪の寒さをしのぐため寺の過去帳をあつめてカヤをつくり、その中で冬を越したといいますからねえ」
もっとも、ここでも《伝説》ができており、「注連寺という寺はミイラ寺なんです。しかし、どうも実物のミイラはニセモノくさい。それに加えて、本堂に縁起絵巻と称するものがあるんですが、これはどうやら森さんの作らしい。あの人、細密画はうまいもんですからね」(東京新聞学芸部・渡辺哲彦氏)
芥川賞受賞作『月山』はこのときの体験をもとに、ふもとの寺で一冬をすごす幽玄的な作品だが、これが世に出るキッカケは古山高麗雄氏(『季刊芸術』編集長)の骨折りによるもの。
森氏は十一年前に放浪生活をやめ、目下、「近代印刷」(東京・新宿区)に勤務。朝8時から午後4時まで働き、無遅刻、無欠勤。原稿は都下調布市のアパートを出、通勤する山手線の車中でワラ半紙に書いた。
選考委員の丹羽文雄氏は、
「じつに清冽な作品だった。書きたいものを書いている、といったさわやかさを感じさせる。ああいう作品を世に出せるのは選考委員の冥利ですな」
といい、吉行淳之介氏も、
「いろいろ弱点はある。反対する人もいたが、文章の力が圧倒的に他の作品とちがっていた」
夫人は病気療養中のため、六畳と三畳のアパートでひとりぐらし。装飾品もなく、まるで学生下宿のような部屋に大さな机がひとつ。この人の場合「“苦節×年”なんていう表現はあてはまらない」(三好氏)のも理解できる。──そこで、ご当人に前述の《伝説》の真偽についてのみたずねてみた。
「さあ、すべての知識も本も捨てましたから、いっさいを忘れてしまいましたねえ……」
こちらも、ヤボなせんさくは止めておきましょう。