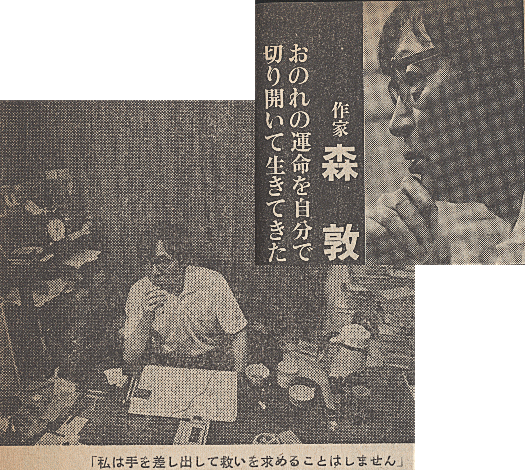
|
世にぼくのことを伝えて沈黙と放浪の四十年などというが、ぼくは十年光学関係の会社に働いては十年遊び、十年土木関係の会社に働いては十年遊ぶといったふうにして伊豆に行き、奈良に行き、東北に行き、尾鷲に行き、北陸に行き、また東北に行きしていたので、厳然といるべきところにいた。
『文壇意外史』に、自身こう書いているように、森さんの言動はつねに自信にあふれているふうにみえる。
秋の夕暮れ、森さんを訪ねる。
森さんは竹薮を背にした一室で、専売特許(?)のおかっぱ頭と人なつっこい微笑で迎えてくれた。受賞後、本業の小説のほかに、エッセイ、対談、テレビ・ラジオの人生相談、歌謡番組のゲストなど、森さんの毎日は多忙をきわめている。しかし気さくな森さんは、六十歳をこしたとはとうてい見えない若わかしい風貌と声で、開口一番、次のように語ってくれた。
『酩酊船』を書いて以後、一高をやめたのは、自分で学校を放校したのですよ。教授などは、ひどいものだった。自分の研究はちゃんとやっておったようだが、生徒にはなんの学問も教えてくれんじゃないか。同じ気持ちの友人、四、五人とともに学校をやめました。
こんなエピソードが伝えられている。
ある日、友人と一緒に菊池寛の家を訪ねよういうことになった。行ってみると「新聞記者雑誌記者以外の方は面会お断り」と貼り紙がしてある。森さんは、これではどうにもならないと思ったが、このまま引きさがるのはシャクだと思い、呼び鈴を押した。すると、のっそりと菊池寛があらわれた。
学校はどうだい、と菊池寛にいわれて、森さんはこういった。
「どうもこうも、百年一日のごとしじゃないですか。おそらく、菊池さんがいられたころの教授がいまもい、いまもそのころとまったくおなじことを喋っているんじゃありませんかね。これじゃ、余っ程の忍耐がなければ、学校なんかにいられるものじゃありませんよ」
|
中学時代、クラスで一番になったことがあります。なかでも学科では数学が得意で、数学なら何人にも負けないぞ、という自信があった。スポーツなら柔道で、わたしの左はね腰にひっかからないものはまれだった。だから、自信のもてない人は、なにかひとつ、数学でも英語でもいい、これだったら奴にかなわん、というものをひとつもつことが、肝じんだと思う。一角をくずせ、ということですよ。そうすれば、数学のできる頭が、英語ができないはずはないということになるのです。しかし、この一角をくずすのは、そう簡単ではない。まず一年は泣くつもりでやることです。
さて、こうして獲得した自信は、人生に対する自信につながることはいうまでもない。
私が放浪しておるとき、“森は生きておるか死んでおるか”などといわれた。何人かの者は不遇だなどと思ったかもしれない。だが、私は、カラフトで北方民族とともに生活しておるとき、鰹船にのって太平洋をゲタばきで歩いでおるときでも、じつに、愉快だった。吾、健在である。ここにおるぞ、という気持でした。
森さんが『酩酊船』以後小説を書かなかった四十年間、文学仲間の檀一雄、太宰治などの活躍を遠望しながら、「コンプレックスと嫉妬で苦しんでいた、などと思う人は、みずからの気持の卑しさを恥じなげればならない。「コンプレックスや嫉妬など夢にも思わなかった」と森さん自身語るとおり、<おのれの運命を自分で切り開いて生きている>という自信が森さんをつらぬいていた。
いろいろ放浪していて、死ぬかもしれないと思ったことはないですか、という私の問いに、「死んでもともとでしょう」と平然といってのけられる森さんに、私は〈おのれを捨ててすべてを獲得する〉仏教の思想の実践者をみた。
そうなのだ。『月山』をよんだ人は、その世界の独特の透明で濁りのない清潔感、心の広さ、それでいて人間を愛している暖かさに眼をみはるにちがいない。これは、俗世間的な出世とか、金銭欲名誉欲など、こせこせした世俗を超越しているところにしか生まれはしない。
あるひとつのことをすることは、前途がプラスかマイナスか、わからんですよ。運命に賭けるのですから。結果がわかっていることには興味がありません。道に挑むということは、プラスと出るかマイナスと出るかわからんことに、挑むということです。人生の生きがいとは、これじゃないかな。
また、森さんはこうもいう。
困っているときでも、私はコンリンザイ手を差し出して救いを求めることはしません。頼むのはいやですから。しかし、だれかしらが手を差しのべてくれた。だから私は人との出会いをたいせつにするのです。いつも一期一会の気持でいましたよ。
自信とは、決して他人によってあたえられるものではない。自分が苦しんでつくりだしていくものだ、そして本当の自信を支えるものは、人生への愛、人間への無私の愛ではないか──森敦さんの生き方は、私たちにこうおしえているように感じられるが、どうであろうか──。