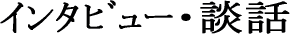 |
| 062 私の人生ノート |
| 出典:読売新聞 昭和52年10月15日(土) |
|
|
|
ボクは一高を一学期で退学したが、一般に伝わっているように放校になったわけではない。そのころ、無茶苦茶に本を読んだ。何万冊という数だったと思う。ところがあるとき、本などいくら読んでもムダではないかと思うようになった。知識なんか捨てる方が本当の知恵に至る。いまはそうは思わないけど、当時はそんな気持ちになったんです。そうすると、学校に行っても意味がない。「信ずる所を学び、信ずるように生きればいい」と思ったのです。
学校をやめるとき、ボクは二つのことを覚悟した。一つは、仕事を選ばないこと。もう一つは、同級生などがどんなに偉くなってボクがその下で働くようになっても、決してひがまないということ。いまは学歴社会だと言われるが、昔の方がよほどひどかった。官立以外はまるで冷遇されたからね。でもボクは学士じゃなかったから、どこでも働く口はあった。いまでも、大学出てると給仕になろうと思ってもなかなか雇ってもらえないんじゃないですか。
十九の時に新聞に連載小説を書いたが、もともと作家になる気はまるでなかった。菊池寛や横光利一らと交際があって、彼らが推薦してくれたんです。ある人が横光さんにボクのことを「本当に書けるのか」と聞いたら、彼はこう答えた。「ツラを見ればわかる」──。 |
|
|
退学後は、奈良の東大寺に住み込んだり、樺太(サハリン)で原住民と暮らしたり、ボンヤリと過ごした。なぜかと言われても、行きたかったからという以外ない。そこにはたいてい先輩や友人なんかがいて、歓待してくれる。カネは持っていたから居候じゃないんです。当時は先輩がカネをくれるのが習慣だったんですよ。たとえば、あるときは菊池さんが八十五円、横光さんが四十五円、そしておふくろが二千円くれたりした。大学卒の初任給が四十円ぐらいだったかな。ボクが一高をスパッとやめたり、新聞に小説を書いてその後いっこうに書かなかったりしたので、面白いヤツがいるなんてかわいがられたんですね。だが、いつかは書くだろうと皆思っていたらしい。放浪したり、遊んで暮らしているのも文学の材料にするのだろうと。
そのうち戦争も近づいてきたし、いつまでもボンヤリしているわけにいかないから、光学関係の会社に入った。仕事は選ばない主義だから、その点はどうにでもなる。ボクは、実際の学校以外にもう一つ目に見えない学校があると思っている。会社に入ればこれも一つの学校だと思って、光学の本を読んで勉強した。テンプラ屋のオヤジにも(別にテンプラ屋をバカにしているわけではない)哲学があり、見識があるはずだ、というのがボクの考え。そうでなければテンプラ一つ揚げられない。 |
|
|
ボクの哲学は「心の欲するままに」。波の流れのままに木の葉のように“浮身の術”を使う。そうすれば狂乱怒濤(どとう)がきても流されず、浮いていられる。他人は放浪なんていうけど、ボクにはそんな意識はない。定住の場所を時々変えるだけ。
それも、たいてい女房と二人なんです。四年前に死んだ女房はずっと病弱で子供もできなかったし、神経的にも弱かった。それでボクはほとんど女房のことは書いてないし、話もしなかったから一人で勝手なことやっているように思われたり、「病気の妻を残して放浪の旅に出た」なんて冷酷無情な男のように書かれたりもした。
でも、ほんとはボクほど女房の犠牲になった男もいないんですよ。田舎に行くのも女房の希望。その方が一緒にいられるので女房も喜ぶ。もちろんボクの希望でもあるし、彼女がボクに感化されたということもある。彼女はいつまでも若く、童女みたいなところがあった。他人には人見知りだが、ボクといるときはすごくほがらかで、こっけいなんだ。小説書くときはボクが怖い顔して一室にとじこもるから彼女はいやがった。酒飲んで笑ってる方がいいんです。 |
|
|
戦後は、「そろそろおカネがない」と女房が言うから、三重県尾鷲の電源開発のダム工事で働いた。これは大会社で、偉くなった同級生や下級生がたくさんいた。ボクは、もし彼らがいばるなら、自分は甘んじて小さく控えていようと思ったのだが、ここでも厚遇してくれた。
給料もたくさんくれたけど、ボクは肉体労働などできるわけがないから、ふだんは大酒飲んでゴロゴロしているだけ。でも、やるときはやる。事故があったりすると、一番早くから、夜遅くまであちこち飛び回る。どこがどうなってるなんていう情報も一番よく知っている。 |
|
|
自分で小説家だなんて言ったことはないんだが、有名な作家が訪ねて来たりするし、掛け軸なんか読めちゃうでしょ。それで「タダモノでない」ってことになる。ほんとはタダモノなんですよ、ボクは。
父親は早く死に、母親は看護婦。この母がまるでボクの応援団なんだ。その点はいまの教育ママと似ているが、ボクを信じ切っていて、何をやっても平然としている。「おまえが本当にやろうということなら何でもいい」という。一高に入ったときはすご喜んでくれたけど、やめても反対はしなかった。いよいよボクが文学をやると思って、自分も文学の話に夢中になっていた。一緒に酒飲んでは談論風発という感じなんです。
こうして考えると、ボク自身は岐路だとか、曲がり角だとか意識したことはないですね。岐路に迷うのは選ぼうとするからです。いい方を選ぼうとか、部課長になろうとか、選び過ぎるんじゃないですか。そのまま受け入れようと思えば岐路はなくなる。まあ、ボクは楽観主義ではあるだろうね。「仁者は憂えず」と言うでしょ。ボクは仁者じゃないけど、そう言って笑っているんですよ。 |
森 敦さん 明治四十五年、長崎市出身。旧制一高中退。昭和十年、処女作「酩酊船」がいきなり毎日新聞に連載されたが、その後小説は書かず、各地を放浪。その間も多くの作家と交流して影響を与え、小島信夫氏らが文壇にデビューするさい陰の力になって、“伝説の人”とか“幻の作家”などといわれた。ほぼ四十年ぶりに発表した「月山」で四十八年度下期の芥川賞を受賞。その特異な経歴とキャラクターで、ラジオ、テレビの対談などにも引っ張りダコ。「もう放浪はできそうもない」という。 |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |
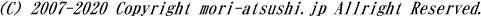 |