| 127 ぼくの青年時代の夢を実現してくれたこの一作 中上健次「地の果て至上の時」 指導 森敦 インタビュー 沖山明徳 |
||
| 出典:文芸図書館 レ●ロマン 昭和58年8月30日 | ||
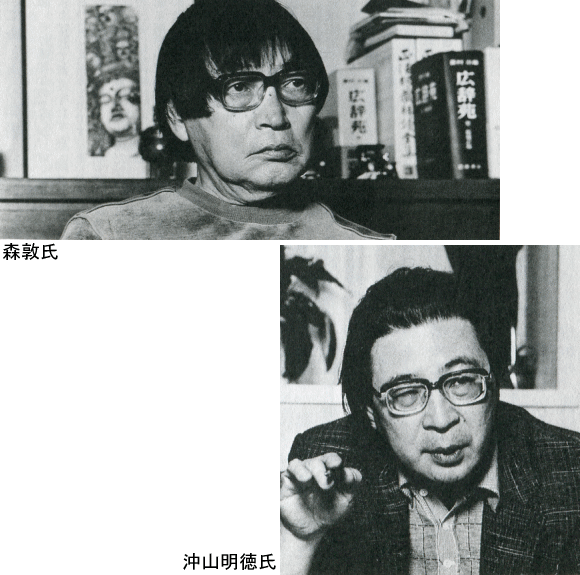 |
||
| 『地の果て至上の時』 あらすじ | ||
| 白いふようの花が咲く夏の初めの朝、紀伊半島のある町の駅に、一人の青年が降り立つ。彼──竹原秋幸は、ふとした偶然から腹違いの弟秀雄を殺害して服役、昨日、三年の刑を終えて出所して、帰郷したのである。 彼は、新宮の路地という被差別部落の生まれだが、いろいろと複雑に入り組んだ血縁を背負っており、土方をして暮らしてきたのだった。彼の実の父である浜村龍造は、いまでは木材業を営んで、土地の有力者となってはいるが、強奪、殺人、放火など悪虐のかぎりを尽くした過去をもっており、蝿の王、蝿のクソの王などといわれておそれられている。かつて、三人の女を妊ませたまま服役したこともあり、その一人から生まれたのが秋幸であった。 秋幸は、この実の父に、深い憎しみを覚え、殺意さえ抱いていたが、養父のもとで土方を続けることを拒み、龍造のもとにきて、木材業に専念しようとした。龍造は秋幸の帰郷をよろこび、息子秀雄を殺されたことも気にしないように、他の子供を差しおいて、秋幸を自分の後継者として遇していた。 秋幸が服役していた三年の間に、彼を育くんだ路地は地域開発ブームで消滅し、草原と化してしまっていた。秋幸は深い違和感をかくすことができない。空地には浮浪者の一群が住みついて、火を放っては立退きを拒んでいた。その頭目ともいうべき男は、かつて父の龍造と組んで暴虐を働いていたヨシ兄である。 そのヨシ兄の子の鉄男は、秋幸といっしょに山歩きについて廻っていたが、彼は町の不良少年らの蔭の親分でもあった。 龍造と秋幸らがシシ狩りに行った夜の酒盛りの場で、鉄男は龍造を殺そうとする。ヨシ兄がかばうと、鉄男は「裏切者」としてその父を射つ。その始終を見ていた龍造は、ヨシ兄を入院させた翌日の早朝、秋幸を自宅に招き寄せて、彼の目の前で縊死を遂げる。ヨシ兄も死ぬ。そして、秋幸は路地の跡地に火を放ったのち、いずこかへ消えていく。 新潮社 |
||
|
||
| 沖山 中上健次さんの『地の果て至上の時』を読み、その迫力に圧倒されるとともに、大へん感動しました。あの本の挾み込みの小島信夫さんとの対談の最後で「現在、小説が衰弱したとか何とか言われているようだけれど、何をとぼけたこと言ってるかと思う。」といっておられますが、たしかにそんな感じも受けました。 実をいいますと、私はこれまで中上さんの作品を読み通したことはなかった、というよりできなかったのです。あのエネルギーあふれる文章に、どうしても耐えられなくて……。体力的にも参ってしまうんです。つまり、私自身も衰弱した読者だったのでしょうね。 森 中上さんという人は、相撲の高砂部屋からスカウトされたことがあるというぐらいの方ですから、人並みすぐれた体力をもっているんです。気力もあるし、体力もある。また腕力もある。だから、当然のことに、文体にも腕力がある。遠慮会釈なく、書きまくるわけです。 ふつうの人は、波がくると──ぼくは昔、船に乗っていたことがあるからよく知っているんですが──いつも、波に直角に直角にと向きをかえてかわそうとするんです。しかし、中上さんは気力も腕力も強いので、堂々と、小細工なんかしないで、真向からぶつかっていく。 沖山 なるほど。これまでというか、現在でも、私たちは文学者とか芸術家というと、どうもすぐ芥川龍之介のような人を思い浮かべるのではないでしょうか。ほっそりして、いかにも神経質でひよわそうなタイプですね。繊細さそのものといったような。そして、体格のいい、がっちりした人にはうさん臭そうな眼を向ける、この人ほんとうに作家なのかしら、それにしては……などと。 そんな点でも、中上さんという方は、これまでの“小説家像”から大分はみ出してしまう、スケールの大きな方、というわけですね。 森 それから、もう一つ。 ぼくはかつて、中上さんに原稿をみせてもらったことがあるのです。それは、ふつうの原稿用紙ではなく、細い縦罫が引いてある大きな罫紙なのですね。さあ、ふつうの原稿用紙にすると七、八枚分くらいはあるでしょうかね、それに、小さい、ちょうど活字みたいに四角な字で書いているんです。 ぼくは、それをみせてもらって、実は大へんびっくりし、かつまた、大いにわが意を得たわけです。 沖山 というのは? 森 ぼくは昔から、まわりの人たちに、原稿用紙には書くな、罫のない紙に書け、としきりにいっておったからなんですよ。 沖山 なぜですか? 森 原稿用紙だと、つい構えてしまってよくないからなんです。罫も何もない紙に、手紙を書くようにどんどん書け、ということなのです。だから、中上さんの原稿をみてびっくりし、よろこんだというわけです。 沖山 そういえば、たしかに、森さんもワラ半紙のようなものにお書きになっていましたね。 森 ですから、中上さんの文体、筆の勢いというのは、ああいう大きな原稿用紙に遠慮会釈もなく書いているということもあるわけです。だから、彼の文章に慣れない人には、とまどいを与えるだろうし、あの怒濤のように押し寄せる文章に、びっくりするのだろうと思います。 沖山 丹念に読んでいきますと、ところどころによくわからない文章もあります。また、いいたいことを一気に吐き出そうとするせいか、一つのセンテンスのなかに二つも三つものことをムリに詰めこんだような箇所もないではない。しかし、勢いに押し切られて読みついでいくと、そんな些細なことはどうでもいいような気がしてきます。あの内容にふさわしい文章だ、といえるのでしょうね。 森 勢いが大せつなんですね。 沖山 それから、小説の内容のこともあるのではないでしょうか。いま読まれているほとんどの小説は──日本の場合ですが──都会を書いていますし、出てくる人物もたいてい都会のインテリ階級が多い。やっと生きているというか、仕方なく生きて、何かこちょこちょいじましくやっているという風な──中上さんにいわせると、衰弱した人種でしょう。 ところが、中上さんの場合は、熊野という太古のままの大自然と、その自然のなかから生まれてきたとでもいうような──あるいは、神話のなかの人物たちといっていいかもしれません──荒々しい人間たちを描いていらっしゃるわけで、私のような、つつましやかな私小説やどこか頼りなげな都会の小説に慣れているものには、その自然のままのエネルギーにも圧倒され、吹きとばされるような感じを受けるわけでしょうね。 |
||
|
||
| 沖山 ところで、最近作である『地の果て至上の時』をお読みになって、森さんはこれまでの中上さんの小説のなかで、何が一ばんいいと思われますか。 森 それは、『地の果て至上の時』ですね。(以下『地の果て』と略す)本人も自信をもっていらっしやるようだし、事実、その自信に十分応えた作品である、といっていいと思います。 とくにぼくが感心するのは、『岬』から必然的に『枯木灘』が生まれた。また、その『枯木灘』なくしては、この『地の果て』も出なかっただろう、という点です。 もちろん、こうして、一つの作品を踏まえ、それをさらに発展させて次の作品を書いていくというのは、どの作家の場合でもそうなんですが、中上さんの場合には、それが実に立派にできているということなのです。 それは、ぼくが思うに、これまでの日本の作家ができなかったことをやっている、ということなのです。 音楽にたとえるとソロ、これはいままでの日本の作家にもできたわけです。だけれども、オーケストラはできなかった。そのような作品もないでしょう。しかし、中上さんは『岬』のときからすでにオーケストラ的なものをもっており、それをさらにオーケストレーションしていって『枯木灘』をお書きになった。そして『枯木灘』をさらにオーケストレーションして、『地の果て』にきている。こうして、一応、『地の果て』で全うした、といえるのではないでしょうか。 沖山 実は、私は 『地の果て』を読んだあとで、これまで読んでなかった『枯木灘』を読み、さらに『岬』へとさかのぼって読んでみたのです。小説の背景はつねに熊野であり、そこにある都市の一画の路地というところに住む人たちが出てくる。竹原秋幸とか、その実父で蝿の王といわれている浜村龍造であるとか、おそらく中上さんの文学の読者ならおなじみの人々が、きまって出てきます。しかし、その内容たるや、しだいに深められ高められ、濃密になってきている。息づまるような緊迫感をもってくる。力技だけでは決してない、魂のドラマとでもいった感じを受けました。 ことに、最後のほうで、父の龍造が、自分の分身ともいうべきヨシ兄が息子の鉄男の手で撃たれるのを目撃したのち、秋幸を自宅に招きよせ、その目の前で縊死を遂げるところ、あそこは、正に圧巻でした。 さきほど、森さんはこの作品をオーケストラにたとえられましたが、そのオーケストラのフィナーレを告げるドラムの音か何かが、突如鳴りひびいたというような感銘を受けました。しかもその音は、たんなる終焉ではなく、なにか次を予感させるものを含んでいるようです。 森 結論めいたことを先にいいますが、ほんとうの文学というもの、ドストエフスキーとかトルストイなどの書いているようなもの──中上さんの出現は、それらに太刀打ちできるようなものを書くことができる最初の人ではないか、という期待を抱かせるし、ぼくはその意味で高く買っているのです。 これは、決してぼくのひいきめばかりではない。友人のところからも、『地の果て』についていろいろと電話がかかってきました。で、ぼくが、いよいよ中上健次はオーケストラを完成してきた。といったら、全くその通りであると合槌を打つ人ばかりなのです。 つまり、中上さんという人は、Aを書いたら次にラージAを書き、さらにラージA'を書く。しかも、それらが一貫して自分の肉体をもっている。生まれ育った風土をひたすらに追いつづけていながら、その世界を深め、高めていくことによって、新しく、大きなものにしていっている。こんなことは、日本の作家としては、空前のことといっていいのではないだろうか。 もちろん、小説というのはソロだってかまわないわけです。オーケストラでなくたっていいんです。ぼくは、日本人の体質としてはオーケストラは作り切らないと思っていたし、鑑賞するにもソロのほうを愛するような体質をもっているものと思ってはいた。しかし、ぼく自身は若いときから、小説はオーケストラでなくてはいけないと思っていた。が、ぼくにはできなかったのです。 それを、中上さんという人が思い切って体当たりして、オーケストレーションできる力をみせてくれたわけです。自分の青年のときの夢が実現したといっていい。 しかも、もっと驚くべきことに、オーケストラでありながら、大きな意味での私小説でもあるということです。私小説の可能性をあそこまで追求していったのです。 沖山 秋幸と龍造にみる親と子の関係とか、血縁の問題という観点からみていくと、私小説というみ方もたしかにできますね。逆にいいますと、こういうような問題こそ、日本の私小説がもっともお得意としてきたもので、いうならば、私小説はそれらの問題を描く唯一の方法として生き残り、珍重されてきたわけですね。ところが、中上さんは、それを私小説ではない方法で、しかもあざやかに描いてみせてくれた、といっていいかもしれませんね。 それからまた、路地という土地に対する、あるいは路地に住む人々に対する、中上さんのいちずな愛情の告白という意味でも、私小説的な何かが感じられますね。白い夏ふようの花というのが、再々出てきます。私はここに、中上さんの郷愁といったようなものを感じるのですが……。 |
||
|
||
| 森 その路地なのですが、ぼくは中上さんによばれて新宮をたずね、講演させてもらったことがあるのです。そして、つぶさにみてまわりながら、ああ中上さんはこういうところを書いているのだなあ、とつくづく思ったものでした。講演には、ぼくの前に瀬戸内寂聴さん、石原慎太郎さん、佐木隆三さんらがいかれているようでしたが、みんな中上さんに頼まれていかれたのです。 中上さんは、路地の人々の精神構造を高めるということを考えておられるのでしょう。映写機を買って映したり、本にしたりなどしてみんなに配り、聞かせる会をやっていました。路地の人々を書くと同時に、ものすごく高い次元の意味で、そこの人々を啓蒙しようとしているのでしょうね。あの人は、ぼくらが思っているのとはちがった意味で、啓蒙ということを考えているのかもしれない。 もちろん、中上さん自身も話をするんです。いっしょの飛行機のなかで、これから話すための原稿を書いていました。そのときに感じたのですが、あの人は古典が好きなようでしたね。『諸国物語』か何かを読んできて、そういった話を盛んにしていました。彼自身も自分の文章を書くことによって、自分を掘り下げようとしているのではないかと思います。 沖山 秋幸は実の父である龍造に対して、底知れない程の憎悪をもっていて、殺意さえ抱いている。それは親と子という乗り越えられる者と乗り越えなければならない者との対立や、また顔や体付の似ていることに対する嫌悪感などさまざまなものが形をとっているわけですが、あの憎悪は、それこそ親子の絆、愛情の裏返しでもあるような気もしますが。 森 中上さんは、どの作品においても、血の濃さに対するひじょうなる愛情を書いているわけです。こういったことを書こうとした作家が、いったいいままでいましたか。島崎藤村はどうか。徳田秋声はどうか。少なくとも、ぼくが読んだ範囲では、土俗と血の問題をあそこまで掘り下げ、拡げていった人は、他にはいないのではないだろうか。 一見すると、中上さんはたんに路地のことを書いているようにみえるかもしれない。事実、書いています。そして、その路地たるや実に小さいところであり、彼が書いたのも小さい世界であるが、とにかく彼は、「一つの世界」を構成してみせたのです。それが「一つの世界」を構成しているという意味では、大きいも小さいもない。中上さんは、その構成された「世界」のなかで、日本人の原型というものをえぐり出してみせているわけです。 ぼくは、極端に聞こえるかもしらんが、決して冗談でも冷やかしでもなく、はじめて、外国に対して、日本にもこういう作家がいるぞ、といってみせていい作家が出た、といっていいし、ノーベル賞をとってもちっともおかしくない作家の最初の出現である、といっていいと思うんです。 とにかく、『地の果て』を読めば、新宮の路地がわかるばかりでなく、日本人の愛憎というものまでわかってくるのです。だから、ぼくは中上さんは、日本文学はこうしたものだといって世界に紹介できる資格をもった何人かのうちの最初の人である、と思っているのです。 なんといっても、大きなことは、「一つの世界」を構築しているということなんです。「一つの世界」を構築しているからこそ、日本にも世界にも通じる作品となっているわけです。 |
||
|
||
| 沖山 森さんが最初に読まれた中上さんの作品は何でしたか。また、いつごろだったでしょうか。 森 さあ、何でしたか──いろんな短編を読みましたね。『赫髪』や『水の女』……などを読んで、ふつうの人では到底出せないものを書いたな、という驚きがありました。 とにかく、以前から家へきていた編集者の人が、いい、いいといっていたので、そんなにいい、若い作家がいるのかと思っていました。──それらの短編がきっかけとなって読みはじめたのでしょうね。『岬』もよかったし、『枯木灘』もよかった。『枯木灘』はちょうどぼくが文芸時評をやっているときで、ひじょうに感心したことを覚えています。 中上さんは、古典をよく読んでいるらしいが、いったい、いつ、どこで勉強したのか、わからないんです。また、『地の果て』もどこで書いたか聞いてみたところ、あの何割かは韓国やアメリカで書いたということです。そういうふうに、あっちへいったりこつちへいったりして書いているんでしょうね。韓国とかアメリカにいて、自分をみつめるということが、自分の小説のみ方をもひじょうに深くしているのではないだろうか、と思います。 沖山 挾み込みのなかで、中上さんがおっしゃっていますよ。「ジンギスカンのことを書いたのは、この小説の初めの四分の一を韓国で書いた影響があるかもしれませんね。書き終えたのはアメリカですから、韓国─日本─アメリカという土地の三角(トリプル)関係もきっとあるはずです。」と。 森 実は、中上健次という人はですね、演歌が実にうまいんです。これはもう、ただならぬうまさである、といっていい。 ぼくのところにレコード会社の人がきて話すには、中上さんの演歌をレコードに入れる計画があるということです。ところが、さっきもいったように、日本にいない。韓国にいってしまうし、韓国かと思うとアメリカにいってしまっているということで、なかなかつかまえることができない。それで、いまだに企画が実らないでいるのだそうです。だからいつの日か、必ずや中上さんの演歌が出るはずです。 沖山 例の挾み込みに、この『地の果て』をアメリカのアイオワで脱稿し、嬉しくてならない。そこで、「絵を描いてみたり、ロスアンゼルスへ車で突っ走ったり、ハワイに寄ってクラブのボーイをしている昔の友達を訪ね、酒を飲みながら八代亜紀の唄も歌った」 とありますよ。声量はありそうですね。 森 あの文体で、演歌なぞ想像できないでしょう。それから押して考えると、どうも中上さんはぼくらの呼吸のし方、息のし方とはちょっとちがうのではないだろうか、という気がしますね。 韓国には演歌の源流のようなものがあって、彼らはみんな実にうまいんです。だから、中上さんがああいうメロディーにうまく入っていけるというのは、なにか、それに近いものが、あるいは潜在しているのではないか、と考えてみたくもなりますね。 それと同じように、彼の小説がオーケストラであるという意味では、オーケストラの芯になっているメロディーというものが、彼のなかにあり、それをさらにさらに複雑化しているのではないだろうか、とも考えられますね。 |
||
|
||
| 沖山 私は一ばん最初に、中上さんの小説をこれまでは読みつづけることができなかったけれど、こんどは (こういう仕事のために) はじめて読み通したと申しあげました。 これは中上さんの小説とは関係なく、一般的なこととして申し上げるのですが、小説の読み方には、自分の好きなものだけを楽しく読むという読み方もあれば、たまには自分に読むべしと課して、読みつづけるという読み方もあると思うんです。そして、私が中上さんの小説を何とか読み通して、それだけの甲斐があったと満足したように、満足することもあると思うんですが……。 森 いや、ぼくは小説はそんなにムリして読まなくてもいいと思う。特種な人、批評家のように読まなければならない職業の人、小説を必要とする人だけが読めばいいと思います。いま、たくさんの人が小説を書き、しかも、売れないで発行部数は減っている。それなのに、性懲りもなく本が出る……。 ……それは、まあいいでしょう。でも、小説が何の役に立ちますか。それより、論語でも読んだほうがずっとタメになる。あるいは、仏典を読んだほうがいい。 ああ、そうだ、あるいは、中上健次は、仏典に興味をもっているかもしれない。 中上さんの小説を読むとわかりますが、仏教説話の原典が、ああいう問題を踏まえているんです。 経典には、ある人間的な問題に関するいろいろな設定があって、それに対してお釈迦さまが説くわけなのです。だから、中上さんが経典をお読みになっているかどうか知らないが、もし、お読みになったとしたら、その設定──人間の原型をさぐるという──に、きっと驚かれるのではないでしょうか。中上さんも、人間の原型を書こうとしているのだから、きっとよろこぶかもしれない。 沖山 『岬』『枯木灘』『地の果て至上の時』ときて、さて、これから、中上さんはどんなふうにすすまれると思われますか。 挟み込みのなかで、中上さんは次のようにのべられています。「こんな言い方をすると倣慢かも知れませんが、僕はこの『地の果て至上の時』を書き上げて、今初めて、本当に小説を書いたという気がしているんです。小説はなんと面白いのだろうと、嬉しくてならない。」また、「僕は昭和二十一年の生れですから、今三十六です。この『地の果て至上の時』は、この齢の人間が書くにふさわしい、欲張りで、元気一ばいの小説です。」と、大へん意気軒高なのですが。 森 中上さんの小説は、同じ場所、同じ名前、そして同じ人間が出てきて、どうも同じようなものを読んだような気がするかもしれないが、これから、まだ、ますます拡がり、深まっていくのではないだろうか。 中上さんは、すでに書く方法というものを会得されたわけだから、これからもオーケストレーションしているうちに、ぼくのいっている「意味の変容」がおこって、別世界が開けてくるのではないだろうか……そういうことを感じるのですけれど。 大成を期待しているんです。 中上さんはふしぎなことに、『岬』のときはそれなり大成していると思った。『枯木灘』のときもそうでした。しかし、こんど『地の果て』をまた書いた。だから、いつも、そのように中上さんは絶えず自分を拡張していくのではないでしょうか。 それも、場面の変化で拡張するのではなく、同じところで拡張していくんです。──延長するのでなく、掘り下げていくことで──。 |
||
| 『岬』 あらすじ 二十四歳になる秋幸は、母の三度目の夫を親爺とよぴ、その子供を兄とよんでいっしょに暮らしている。そして、母の前夫の娘の夫の組に入って土方をしていた。 そんな環境にあって、彼はつねに実の父である「あの男」を意識し、絶えずその男に見られているような気がしていた。また、「あの男」が女郎に生ませた腹違いの妹が、娼婦として新地にいるという噂をきき、会ってみたいとひそかに思っていた。母の前夫の法事のことでいざこざが起き、また親戚同士の刺殺事件が起こり、錯乱した妹が仏壇を壊そうとしたり、鉄道自殺をしようとする。彼はそれらのできごとを見つめながら血縁の愛憎を思い、孤独感を覚えては自分とは何だろうかと悩む。 彼は自分を生みつけた「あの男」に出会い、雄同士として決着をつけたいと望む。 そして、何か酷いことをしでかして、「その男」に報復してやろう、いや、自分の身に酷いことを被わせてやろうと、新地へ行き、妹を抱く。 文春文庫 |
||
| 『枯木灘』 あらすじ 秋幸は、義兄の経営している土建請負業竹原組の人夫頭をしている二十六歳の屈強な青年である。彼の実の父親である浜村龍造は、いまは木材業を手広く営む土地の有力者となっているが、かつては野獣のような男であった。 町に火をつけ、三人の女を妊娠させて、刑務所に入ったこともあった。秋幸は、自分が龍造に似て体が大きいことや、姿かたちもそっくりなことを意識して、龍造との血のつながりに苦しみ、つねにその男の視線が自分に向けられていることも感じては息苦しい思いにとらわれている。 また、彼は自分と母親を呪って首を吊って死んだ腹違いの兄の記憶からも逃れられない。その兄の呪いは、ちょうど自分が、龍造とその子の秀雄に抱いている愛情と同じではないかと苦しんでいる。 秋幸の種違いの姉の妹の娘の亭主が、秀雄ら不良グループに袋叩きに遭って重傷を負う事件が起きて間もなくの盆踊りの夜、秀雄に殴りかかられた秋幸は、逆に秀雄を殴り殺してしまう。 河出書房新社 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||