| 129 森敦の読書セミナー 日常性の中に織りなす生と死の綾 津島佑子の『水府』『黙市』 指導 森 敦 インタビュー 沖山明徳 |
||
| 出典:文芸図書館 レ・ロマン 昭和58年10月30日 | ||
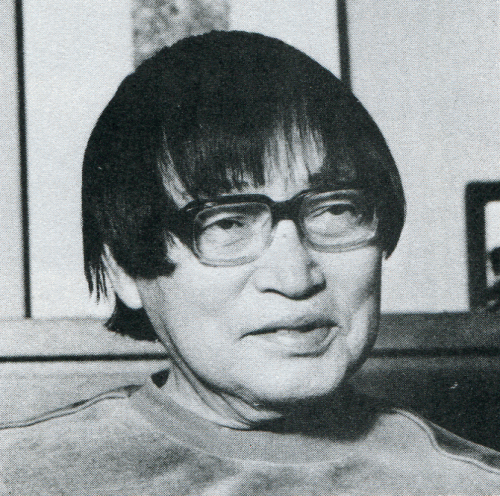  |
||
|
||
| 沖山 『水府』(河出書房新政)は、昨年九月に出版された作品集で、『ボーア』『多島海』『番鳥森』『浦』『水府』の五部作から成っています。また、『黙市』(「新潮」昭和58年六月号掲載)も昨年の七月に発表されたもので、今年第十回川端康成文学賞を受賞しました。いずれも短編です。 『ボーア』という作品ですが──ボーアというのは、アマゾン川に起こる巨大な川津波のことです これは、父親の違う娘と息子をもつ事務員の話で、娘の父親にも息子の父親にも逃げられてしまいます。まれにやってきても、父親としてでなく男として振舞おうとして、ついには追い出されてしまいます。ここには妻に逃げられた父子家庭の父親に関心をもつ話も出てきます。 『多島海』の場合は、二人の子をもつ妻と、一人の赤ん坊をもつ愛人の間を行ったりきたりして父親の役を勤めさせられる男が出てきます。二人の母親は、二人という数を受け入れられず、怒って荒れ、男にあたり散らすことをくり返しています。 『番鳥森』バンドリというのはムササピのことで、小さいとき外で夕方遅くまで遊んでいると、バンドリがくるといっておどかされた、その恐怖がまだ残っている女性が出てきます。彼女は二人の子どもをもっているが、父親は若い女に子どもをつくって、そちらにいっています。そのためかどうか、女性は少し異常気味のようです。 『浦』に出てくる男は、妻と子にも出ていかれ、また別の女に子どもをつくるが、これも離れていってしまう。女がいやがるにもかかわらず、男は三か月に一回自分が勝手に決めた養育費とおもちゃを届けにいって、父親としての役割を果たしたような気もちになっている。一方、家では若い女二人と同時に関係をもっています。 『水府』と『黙市』の場合は、父親は私が幼いときに女といっしょに川に身を投げて死に、父親のない家庭に育ちながら、自分もまた父のない子どもを育てるようになってしまった娘の私と母、それに子ども、つまり母、娘、孫との関係が描かれています。 つまり、どの作品にも、父親のいない家庭もしくは家庭のない父親が出てくるのが共通しているところですが、といってふつうの素朴なリアリズム小説のように、そういう父親のいない家庭の問題というものがことさらに描かれているというふうな作品ではないようですね。なにか、ひっそりしたものといっていいか、うまく口にはできないのですが、何かがあるようない気がします。 まあ、それはとにかく、まず文章についてお伺いしたいのですが。 |
||
|
||
| 森 さらっと書いていますね。とくにここに力を入れてやろう、というような文章ではない。『水府』のなかのものをみると、出だしが構えているな、と思われるものもあります。構えてわるい、というのではない。構えてもしかたがないんです。仕切りをしないと相撲がとれないんだから……。 しかし、いったんこの、仕切りがとれてしまうと、ちょっと見ると無頓着に見えるかもわからんが、肩から力を抜いてタマを投げるとタマがよく走る、とよく野球でいわれますね、そんなふうに文章が走ってきていますね。 とくに『黙市』の場合は、仕切りがない。いい意味で。実は、仕切りをみせないのがほんとうなんです。 ある女流作家──林芙美子なのですが──は、原稿を書いていて、これでいけるということがわかったら、はじめのほうの何十枚かは切って捨てた、といわれています。それでも、話のすじはちゃんと読者に伝わっていくし、読めるものになる、というんです。つまり、その話が心のなかですっかりできあがっていれば、始めをぶった切ってしまったところで、おのずと読者には伝わっていくということなのです。 そこで、林芙美子は仕切りをとれといっている。そのほうが、読者をいきなり話の渦中に引き込むことができるというわけです。(小説のなかの)事件というものは、書かれている前から起こっているんだから……。 また、ふつうの人は、自分がどう表現したらよいか──つまり、美人であるかどうかということを書かなければいけないだろう、と考えている。しかし、志賀さん(直哉)が『アンナ・カレーニナ』を読んだところ、意外にそんなに書き込んだところがなかった。それにもかかわらず、人物がはっきりとイメージされてくる、というのは、作者のトルストイが、それらの人物についてしっかりとしたイメージをもって書いているからではないか、ということをいっている。 沖山 仕切りをとりはらってしまうということと、人物にしっかりしたイメージをもつということですね。 森 『黙市』では、その二つがうまくおこなわれているのではないでしょうかね。犬や猫を捨てるというような、なんでもないような話だが、みんなはっきり動いてきますね。 そしてまた、文章が書きっ放しではないかと思われるくらい走っている。憑かれたような文章なんです。そうなると、ぼくなんかまるで催眠術でもかけられたように引き込まれてしまっていって、何か、感動というのとはちょっと意味がちがうが、ある真空を感ずるんです。 独楽(コマ)がよくまわり出すとアタマをふらなくなりますね。これを眠るといっていますが、このときが一ばんよくまわっている状態なんだけれど、ちょうどそんな状態になったような気がする。 ぼくらは文章をひじょうに大せつにし、苦労するが、そういうような段階を、津島さんは捨ててきているのかもしれない。前からそんなところがあったが、今度はそれが明確になってきている。 |
||
|
||
| 沖山 森さんはよく、小説の構造ということをおっしゃいますね。その構造という点からいうと、どうでしょうか。 森 眠っている独楽(コマ)の芯、その芯を象徴的にもってきているんです。象徴を造型しているわけです。『黙市』でいうと六義園ですね。六義園というのは、まわりにビルが立ち並び、そこでは人々が生活している。そんな生活の外にある空虚な空間ですね。これまでも、草原だとか深い谷などが出てきたように思いますが、そんな象徴的なものをもってきて、うまく使っているんです。 それは、『水府』に出てくる作品の場合も同じです。ボーアとかバンドリだとか、また六義園などのように造型されたものではないが、水だとか、水と死、水と生……。題名をみると、みんなそれらを象徴にしている。 そうして、象徴をうまく生かして、このなかから外の生活を眺めているんです。見えるものは男女関係であるかもしれないし、親子関係であるかもしれないが……。『黙市』でいえば、象徴である六義園のなかに入って、外の生活を描いているわけです。『ボーア』でいえば、ボーアを原点にして外の生活を見ているわけです。むかしは、外の生活を描いているにすぎなかったが……。 これは、だれでもやれることではない。大へんなことです。太宰のものにも象徴がないとはいえないが、津島さんはとにかくそれを造型しているんです。それが、また近代文学の特色でもあるわけですが。 たとえば、コンパスで円を描きますね。原点を定めて、任意にコンパスのまたを拡げて円周をかく。しかし、円周をかくことばかりに気をとられて、中心をあまり考えない。でも、中心が定まらなければ、円はかけないんです。第一歩は、その原点──中心に立つことなんです。 そこに立って、もろもろの生活を見たらどうなるか。日常のおそろしさ、大へんさ、それらが見えはじめてくるのではないか。──津島さんは、それができてさたということなんです。ところが、われわれはそうはしていないから見えないですね。彼女は、いったいいいつごろからそうなったんだろうか。 |
||
|
||
| 沖山 先日、女性の方と津島さんの小説にっいて話をしていたら、津島さんの小説は女性のほうがよくわかるのではないか、というようなことをいうんですね。 なぜかというと、どうも題材が父親のない家庭の場合が多いからのようです。いまの言葉でいうと母子家庭の問題というんでしょう。しかも、津島さんの小説に出てくる母親はだいたい自立している人が多いらしく、女の自立の問題を考えさせられるようです。またそんなことから、父親とは何か、ということ、さらに性の問題も出てくるわけですね。 それに、たしか津島さん自身、父親のいないお子さんをおもちのようですし、また太宰治の娘さんということもあって、作者の実生活の影を作品のなかに読みとろうとする興味もあるかもしれません。 森 小説の読み方というのは無限ですから、どう読もうと、これはもう読者の勝手なんです。だから、私小説として読んでいっこうに構わない。 ただ、わたしは津島さんの小説が私小説であるかどうか知らないがわたしはあ まりそんなことが気にならないんですわれわれの日常というのは、一見なんでもないようだが、実は生と死によって織りなされている。ふつうは、それを感じないだけなんです。そして、そのことのもっとも象徴的なものを考えてみると、実は男女関係になっていくのではないだろうか。津島さんの作品が私小説のように書かれていても、その作品に書かれている生や死、悶えのようなもの、そのほかいろいろな感情は、みんな生と死の織りなすところの象徴なのではないか。ぼくは、津出さんはひじょうに深いところをねらっているように思っています。 沖山 実はこういうわたしも、どうも色メガネをかけて見たがるタチなんです。なにしろ太宰治といえば、わたしたちの青春時代もっとも影響を受けた一人でしたからね。たとえば、津島さんの小説を読みながら、太宰の『桜桃』などを思い出し、「子供より親が大事、と思いたい」──ああ、ここでいう子供のなかには津島さんのことも含まれているんだなとか、うちでは子供に桜桃なんかたべさせたことはない、もっていってたべさせたらどんなに、よろこぶだろうなどと思いながら、太宰ひとりでペっペっと種を吐き出しながら桜桃をたべている場面もあったなあ……なんてよけいなことを考えたりしてしまうんです。 大事は父親のいない家庭を二つつくっています。その一つの家庭に育った津島さんがご自分も父のいない家庭をつくる。これは実生活の問題だから個人のことでとやかくいうわけではありませんが、作家として父のいない家庭のことを題材に小説にお書きになっていらっしゃる。これほどういうことなのか。単なる偶然なのだろうか。それとも、父というもの、男というものへの挑戦なのだろうか。また、その逆の表現なのだろうか。男なんかいらないということなのか。男はいるが、父親は必要ないということなのだろうか。あるいは、それらいろいろな場合を想定しての実験なのだろラか。 そうして、太宰治とはいったい津島さんにとって何なのだろうか、とどうしても太宰との関係を考えてしまい、どうも純粋になれません。だからといってどうかわかりませんが、わたしにはこのなかで 『水府』という作品が一ばん面白いんです。 森 太宰の私的生活と津島さんの私的生活とが似ているというのではなく、不思議なことに文学的な血脈は何かあるようだし、その血脈を探るために、太宰を読んでから津島さんを読むのではなく、津島さんを読んでから太宰を読むと、いい鍵になるのではないでしょうか。 また、そうすることで、太宰をいっそうよくわかってくるのではないだろうか、と近ごろ思うようになりました。 沖山 血脈といいますと‥‥。 森 津島さんはデカダンである、と考え勝ちかもしれませんが、たんなるデカダンでは絶対にない。 いまは、みんな新しがって、旧来のモラルを否定しているが、津島さんは否定しているのではなくて、むしろモラルの存在そのものを疑っているのではないか、とぽくには思われますね。だから、たんなるデカダンとはまったく関係ない。 もっとも、文学的な大きな流れからいったら、あるいはそういうことになるかもしれませんがね。 |
||
 津島裕子さん |
||
|
||
| 沖山 森さんは、檀一雄、太宰治とともに、たしか「大下の三悪人」とかいわれていたとなんかで読んだような気がしますが、そのくらいのおつき合いだったわけですから、太宰のこともよくご存知でしょう。 いま、太宰の小説を津島さんの小説とをくらべてみて、どうお思いになりますか。 森 太宰の小説というと『津軽』とか『富岳百景』などがいいといわれますが、ああいうのは、すぐれた才能によって、たのしい話を書いたものにすぎない。ぼくは、そうでなく、のっぴきならない、どうしようもないというところで書いたものしか感心しないのです。 沖山 作品でいいますと、何でしようか。 森 『おさん』(昭和二十二年発表)以後のものですね。ぼくは、太宰は、この『おさん』以後のものを読めばいいと思う。だから『おさん』をまず読んでほしい。短いものですから。 とにかく、太宰とぼくとは両極端なんです。ぼくは、抽象化、構造化しょうとするわけですが、太宰は、つべこべ文句をいわないで、とにかく面白く書けばいい、というんですからね。しかし、『おさん』以後はのっぴきならないところへきた。のっぴきならないというのは、題材の上でも芸の上でも押しつめられてきたということです。だから、最後彼はそれらのすべてにゆき詰って死んだ、とぼくはそう思っています。『おさん』以後の作品を読んでごらんなさい。あれは、全部、遺書です。遺書なんですよ。 ところが、津島さんのほうは、どういう図式をとればみんなにわかってもらえるか、ということを考えておられる。 津島さんはあるエッセイのなかで、小説はつくりものである、といっておられる。ということは、自分の感覚をいったんバラバラにして、再構成するということで、そうしないと真実というものは出ない、というわけですね。 そうそう、嘉村礒多という作家がいましたね。私小説の権化といわれた。一方、これもまた小説の鬼だったか神様だったか、そんなふうにいわれていた宇野浩二が、嘉村が『途上』という小説を書いたとき、そのなかに「池のふちを三度まわった」ということが書いてあったので、宇野さんが「ほんとうに三度いったりきたりしたのか、それとも文学的な表現として三度としたのか」と聞いた。すると、嘉村は、ほんとうに三度いったりきたりした。といったというんですね。 嘉村は、それを徹底したリアリズムだと思っていたわけですが、しかし、それは事実であって、文学的真実とは嘉村の考えていたようなものじゃないんです。 |
||
|
||
| 沖山 大へんへンな質間をして申訳ないんですが、もし、太宰がいま生きていて、津島さんの作品を読んだとしたら、いったい、なんといったでしょうかね。 森 うーん、わるいけど、気にいらないのじゃないかな。こういう(津島さんのような)作風はきらいじゃないかな。おそらく、何をいうんだ、という気がするんじゃないか。 とにかく、中学時代から芸をみがくんだといって三味線などを習う一方、左翼運動などもやったりしたが、とにかく芸を大せつにしていましたからね。どんな話を書いても、芸ということを忘れなかった人です。文字は「口説き」である、といっていたくらいですから。 しかし、津島さんは芸を否定して、新しく構造式をみつけようとしていらっしやるわけですからね。 ──でもねえ、生きていたとしたら、案外、うれしくてたまらないかもしれないな。いや、とにかく、生きていないんだから、わからないな。 沖山 太宰は、弱さをむき出しにして書いていた。おれは弱いんだ、おれは弱いんだ、と。若いときには、それに案外共感をもったものですが、年をとってくると、どうも甘い、という気がしてきます。 森 はじめは甘かったんですね。当時は、あんなふうに、甘さをぬけぬけと書く人はいなかったから受けた、という面もあるでしょうね。 沖山 それにくらべると、津島さんはつよいのではないでしょうか。文字の上でも、実生活の面でも……。なんだか作品を読んでいると、そんな気がしてくるんですが。 森 あのね、女というものは強いものなんですよ、津島さんにかぎらず……。 とにかく、津島さんは、これらも実生活の断片が多少もぐりこむことはあっても、もっと、もっとえらい仕事をしてくださるんではないでしょうか。ちょっと、こわいところがありますねえ。 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||