| 130 私 子年です 森 敦(作家) 10年ぶりに筆をとってもうひと頑張り |
| 出典:サンケイ 夕刊 昭和59年1月12日 |
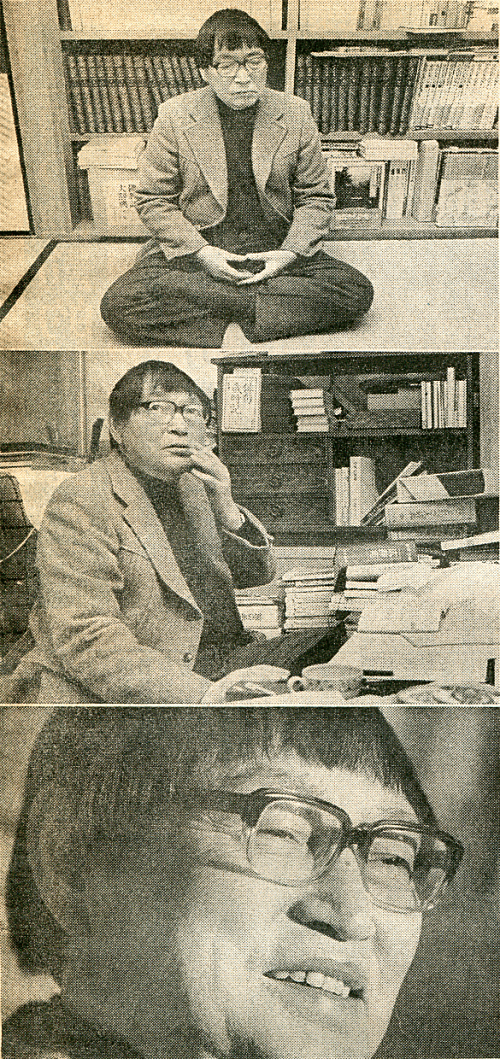 |
| あれから十年──。流されるままにマスコミ界を“放浪”してきたが、「月山」いらい十年ぶりに創作の筆をとる。 その人生には、ほぼ十年ごとの周期がある。放浪時代からそうだった。十年働いて、十年遊ぶ。 「働く時は一生懸命働きましたよ。女房と二人だけだから、まあ、小屋でも借りて、海岸の流木でも拾っておる分には、一生食えると思っておった。それが、やっぱり十年たってみると食えなくたる。そういうふうにインフレが進んでいきますね」 明治四十五年生まれの子年。 せっかく入った一高を中退し、放浪する息子を温かく見守った母親も、ともにさすらった妻も、もうこの世の人ではない。 最後の放浪からオカに上がったのが六十歳。東京・飯田橋の印刷屋に就職した。 印刷屋時代に書いた、清れつな自伝小説「月山」で、四十九年、第七十回芥川賞を受賞、“還暦の受賞”とマスコミをにぎわした。 十年ぶりのフィクションの題は「われ逝(ゆ)くもののごとく」。「論語」の「逝く者は斯くの如きかな、昼夜を舎(お)かず」からとった。「群像」三月号から一年間連載する。 舞台は、山形県の港町・加茂(鶴岡市)。これも三十七、八歳ごろ住んでいた放浪の地である。 「加茂は、かつて酒田に匹敵する繁栄を極めた町でした。庄内平野で金持ち十人をあげれば、三人までが加茂の人といわれた。現在も家や倉など、その歴史が眠ったままあるわけです。『月山』は白分の体験でしたが、今度は、いろいろな人が登場、ぼくが見聞したことを書きます」 昨年五月から七回にわたり、NHKの取材で「おくのほそ道」をたどった。芭蕉の歩いた道は、まさしく自分の放浪の地を線で結んだものだった。それが十年ぶりの創作意欲を刺激したのかもしれない。 「この年ですから、小説を書こうという気持ちは、もうないんです。だけど同時に、これが最後だから、ひとつがんばってやろうかなあ、という気持ちも、その裏にあるんです」 |
| (文・影山 勲 撮影・田中 清) |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |