| 133 私の死生観 既ニ死ヲ知ラバ何ゾ生ヲ知ラザラン |
||
| 出典:週刊小説 昭和60年1月11日 | ||
 |
||
| いま若者たちの考え方に、明らかに小さな変化が起きている。浅田彰ブームもその一つだし、森敦さんが最近著わした『意味の変容』も、いまキャンパスの一部で、じわりじわり不思議な人気を集めつつある。「ここには私の死生観がある」と森さんはいうが、編集部では新春TALKとして、その考え方の一端を聞いてみた。 | ||
|
||
| 私の好きな言葉に「未ダ生ヲ知ラズ、焉ゾ死ヲ知ラン」(論語)という言葉があります。これは、孔子の弟子の子路が、「死トハ何ゾヤ」と孔子に問うたときの答えです。 子路という人は、もともと無頼の徒であり、剣も使え、腕力もある男でした。彼は、近ごろ孔子という人が出てきて、何かいろいろな説教をしているらしい。ひとつ剣でおどしてやれというので、孔子を訪ねてきたのがそもそもの始まりですから、孔子の門弟としては早い方で、弟子の中では一番年をとっている人です。 普通なら、武勇を口にするような人は孔子が嫌いそうなものですが、この子路を、孔子は弟子の中でも一番愛していた。 というのも、孔子という人は、困ったことに決して文弱の徒ではなかったからです。礼(礼儀)、楽(音楽)、射(弓を射ること)、御(馬に乗って戦争すること)、書(書くこと)、数(数学、つまり易数)すべての達人ですので、それらしくふるまうからです。 とくに、孔子が音楽に非常に長けていたことは、定評になっています。『論語』の中でもオーケストラの説明をしているのですが、その説明が、ちょっとだれもいえないようなことをいっています。現代のオーケストラ奏者でも、それを開くとびっくりするくらい、音楽に精通していたと思われます。 彼は、あらゆるものの根本は音楽だ、「礼」も心の調和をあらわしているが、雅楽とか舞楽はみんな音楽がもとになっている、宇宙の調和も、音楽がもとになっているといっています。 新潮社から『新孔子伝』という本が出ていますが、それを読むと、どういうわけで孔子は音楽がうまかったのかというところから説き起こしています。 彼のお父さんの叔梁紇(しゅくりょうこつ)という人は、武人の出です。戦争に行って敵の城に攻め込んだとき、大きな扉が上からドンと落ちてきて、出られなくなった。 「新春トーク」ということなのでちょっとわき道にそらしていただければ、そういう目に遭った人は、古来、歴史上にはいっぱいいるのです。たとえば、セルバンテスは、あまりにも勇敢だった。あまりに勇敢なのは、かえって危ない。スペイン軍がトルコと戦争をしたとき、セルバンテスは真っ先にトルコ軍の軍艦に飛び乗った。というのは、昔の戦争は、大砲はあるのですけれども、舷々相摩して戦うわけですから、船から船へ飛び移るわけです。 スペインが負ければ、そんなことはなかったのでしょうが、勝ってしまった。敗れたトルコ軍の船は、ワァーッと国に逃げ帰ったわけです。その船にセルバンテスは乗っていた。敵中にたった一人では勝てっこない。そういうことがあって、セルバンテスは非常におもしろい生涯を送ったんです。 叔梁紇もそれと同じです。敵の城に攻め込まなければよかったのですが、一軍が一斉にワーッと攻め込んだために、謀られたのかどうか知らぬが、重い扉が上からダーンと落ちてきて、退路を断たれた。 そのとき叔梁紇が、ものすごい怪力をもってその扉をワッと持ち上げた。落っこった扉を上げるだけでも大変なのに、一軍が全員退却してしまうまで持ち上げていた。 彼は正式な結婚をせず、女楽と野合した。その子供が孔子だというのです。そのために、孔子は小さいときから母親に連れられて、宮廷に出入りして、舞楽や雅楽を聞いていた。そうでなければ、あんなに音楽ができるはずがないという観点で、『新孔子伝』は展開されています。大変おもしろい本です。 そういう人の子ですから、孔子は、武勇もちっともこわくない。何とかやっつけようと思ってやってきた子路が、一遍に弟子になったくらいですから、孔子の力は大したものだったわけです。 子路は市井の無頼であり、力は強く、剣を持たしたら、そんじょそこらの“幡随院長兵衛”には負けない人ですが、音楽は柄ではないわけです。けれども、孔子の弟子になった以上、「楽」もやらなければならない。幾ら習っても、めちゃくちゃな音楽を弾く。今でいえば、テンポも狂えば音程も狂っている。そうすると、孔子の弟子たちが笑うわけです。そのとき孔子が、ニコニコ笑って、そうじゃないんだ、子路は「既ニ門ニ入レリ、未ダ堂ニ入ラザルナリ」といったわけです。「堂に入る」という言葉は、そこから来たんですね。「楽」のヘタくそな子路でも、孔子は、そのくらいかわいがっていたのです。 |
||
|
||
| このように、孔子の教えは主に生の哲学であった。死の哲学ではなかった。根本は「修身、治国、平天下」といって、自分の身を修めて、国を治め、天下を治めるというのが孔子の生き方ですから、あの世のことなんかは、あまり問題じゃない。 「怪、力、乱、神ヲ語ラズ」(論語)ですから、『霊異記』みたいな話は話さない。常に当たり前のことを説いたわけです。 この世の中に鬼神というのがあります。 「鬼神ヲ敬シテ、之レヲ遠ザク」(論語)といっていますから、福沢諭吉のように、神様なんかないんだといって、神様のほこらをあけて、その中に石を入れておったとか、そういう人ではないわけです。「敬シテ、之レヲ遠ザク」ですから、神仏は尊敬しなければならないけれども、これに頼ることはいけないといって、死んでからどこに行くとかなんとかということは、まったく語らない人でした。「修身、治国、平天下」が王道だといって、いつも王道を説いていた人です。 だから、あまり「死」ということには触れていない。そもそも彼は、死とはいわないで、「天」という言葉を使っている。天というのは神様のことなのか、天然、自然の思意のことなのかわからない。しかし、顔淵という、ちょうど子路と対照的な秀才の弟子がいたのですが、それが若くして死んだとき、「アア、天、我ヲ亡ボセリ」と嘆いている。そのときも、顔淵は死んでも成仏するだろうなどとは決していっていない。 子路という人もおもしろい人で、孔子は、子路は畳の上では死なないだろうといっていた。事実、戦争に行って、めちゃくちゃに斬り合いをして死にかけたときに、冠の紐が切れて垂れそうになったのを、しつかり結び直して死んだという逸話が残っています。子路は、あげくの果てに、めちゃめちゃに肉を切り刻まれて、塩辛にされてしまった。それきり孔子は塩辛を食わなかったという程度の死生観なんです。 ただし、それでは「死」ということをないがしろにしているかというと、儒官の着る儒服は、いわゆる喪服だといわれている。常に親孝行をせんならんと説いていたのですが、お父さんやお母さんが亡くなったときも、そのそばを離れないで、「三年喪二服スレバ、孝ノモトナリ」といっているくらい、ものすごく厚葬をしている。厚葬というと語弊がありますが、礼儀正しい。けれども、それは、僕の考えによると、どうも、あの世があるからやっているのではなくて、孔子は、あの世があるかないかは問うてない。とにかく自分の親に対する孝行だと思って、お墓をつくり、その横に小屋をつくって、三年間離れないでおるということは、だれもやらなければいかぬといっている。 それが、主に「修身、治国、平天下」のためになるわけです。親を敬うということは、すなわち身を修めることであり、身が修まっていれば、必ず国が治まり、天下が治まるという考えの人ですから、普通の仏教でいっているような「死」というふうには彼は考えていない。だから、死とはいわないで、「後世」というのです。後世というのは「生」です。 弟子たちは孔子に向かって、一体この世には神様がおるのか、仏様がいるかということをときどき聞くわけです。それをもし否定すれば「後世必ズ畏レザルモノアラン」。後の世に必ずおそれない人間が出てくるんじゃないか。おそれがないということは、殺人をやるか、強盗をやるかわかりません。 そういうふうに「あの世」とはいわず「後世」というのです。というのは、そういうことをないがしろにさせていると、「後世畏レナシ」で後世に生きている人たちが何をしでかすかわからないとみているからでしょう。 こういうような意味に、すべて解釈していくと、孔子は生というものを根本に置いて、ビクともしないでそれを考えているわけです。その孔子に、ほかの顔淵とか子夏とか、とにかく非常に頭のいいやつが聞いてくれれば、また別の答えが出たかもしれない。ところが、事もあろうに子路が、「敢テ死ヲ問フ」と聞いたわけです。柄じゃない。その柄じゃない者に対して、孔子は「未ダ生ヲ知ラズ、焉ゾ死ヲ知ラン」、こう答えたわけです。 |
||
|
||
| 僕の考える『意味の変容』でいえば、「未ダ生ヲ知ラズ、焉ゾ死を知ラン」ということは、つぎのようになります。一つの円を描いたとき、その線を境界線とします。境界線は幽明の境、ですから、あの世とこの世の間で、達することはできないところです。 ということは、円を描いて内部を「生」とし、外部を「死」とするならば、幽明の境である境には、生きている間はどうしても到達できないので、いわば、無限大のところです。 それを今後は、「死」の方からみてみます。「AはBなり、BでないものはAでない」という命題がありますが、Aを否定してBにもっていき、Bを否定してAにもっていくというように変換をすれば、孔子のいっている「未ダ生ヲ知ラズ、焉ゾ死ヲ知ラン」ということは、「既ニ死ヲ知ラバ、何ゾ生ヲ知ラザラン」ということになるのです。 「既ニ死ヲ知ラバ、何ゾ生ヲ知ラザラン」ということは、すでに宗教概念になるのです。だから、対偶命題は、論理学的にはいつも真なのです。 つまり、一つの「生」という領域があって、生きている間は、どうしても「死」の領域に達せられない。幽明境に達せられない。あした死ぬといわれても達しない。そこで、「未ダ生ヲ知ラズ、焉ゾ死ヲ知ラン」ということになる。境界線は決して内部にはついてない。幽明境は決して「生」の領域には属していないのです。 ところが、それが対偶命題を使うことによって、不思議なことに「既ニ死ヲ知ラバ、何ゾ生ヲ知ラザラン」になる。この対偶命題をとるという考え方は、私の『意味の変容』(筑摩書房刊)に詳しく書いてあるけれども、結局、「内部思考」「外部思考」ということになるのです。 つまり、「孔子ハ人間デアル」というでしょう。内側にとれば、孔子は人間です(A)。境界は人間に関係ない。境界の内部にあるものはみんな人間ですから、孔子は人間です。境界というのは、厳密にいうと孔子であるものも、孔子でないものもあるということになります。このベクトルは内部に向かっていますから、「内部思考」だというのです。 ところが、「外部思考」では、「孔子デナイモノ」と「人間デナイモノ」は、いずれも境界がそれに属する領域では外部になります(B)。そうすると、「孔子デナイモノ」の方が大きい。これが対偶なんです。人間でないものは孔子でない。人間であるものの中に孔子は含まれている。内部というものは、含む・含まれるの関係です。これが根本的な考え方です。 |
||
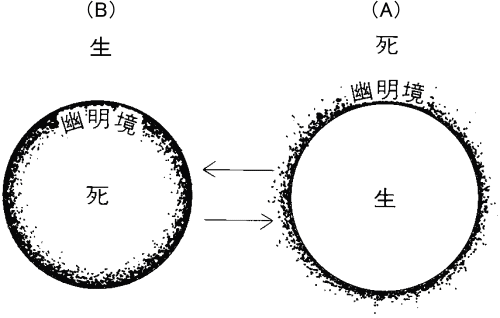 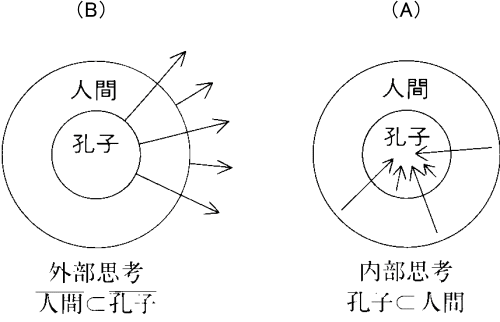 |
||
|
||
| 僕が、どうしてこうした『意味の変容』を考えたかといいますと、最初は光学会社に一○年勤めた。その後、一〇年遊んだわけです。実際は一〇年どころか、一生遊ぶつもりで会社をやめたんです。 僕は、働いているときは「修身、治国、平天下」で、それこそ「未ダ生ヲ知ラズ、焉ゾ死ヲ知ラン」だった。「朝ニ道ヲ聞ケバ、夕ベニ死ストモ可ナリ」とか、そういう孔子の考え方は、全部一貫したところから出ているのです。だから、僕もめちやくちゃに働いたし、貯蓄もした。ソニーの株を持ったりして、カネを儲けることも考えて、一生懸命頑張った。これなら、一生遊んでおれると思ってやめたのです。 僕の女房は金持ちの出ですから、お嬢さん育ちで、僕に働かないでくれといっていました。それは、女房の家に厄介になればできることですけれども、僕はまたこういう性格ですから、そんなのは嫌です。よく、遊んでいて家に帰らぬという人がありますけれども、僕は働くために家に帰ってこないわけです。女房が働かないでくれというくらい物すごく働いた。これだけあったら、その当時の相場で一生食えるなと思ってやめたんです。 一〇年たってみたら、お金がなくなった。というのほ、インフレーションの計算を間違えたわけです。『意味の変容』もみんな数学思考でやっているくらいで、僕はわりに数学に長けているわけです。カネを儲けるというのも数学思考ですから、「礼、楽、射、御、書」とまではいかなかったが、「数」は相当やった。にもかかわらず、一〇年たったら、ちょうどお金がなくなって、勤めざるを得なかった。 そこで今度は電源開発に勤めた。そしてまた、「修身、治国、平天下」で一生懸命働いて、一〇年たって、今度こそは一生遊べると思って会社をやめました。海岸に行って流木を拾ったり、山に入って松かさを拾って楽しい生活をしていたのです。これなら絶対大丈夫だと思っていたけれども、やっぱり一〇年するとお金がなくなった。 そこで、また一〇年目に、今度は印刷屋に勤めたわけです。それまで勤めたところは、光学会社もダム会社も、日本有数の大きな規模の会社だった。それが、印刷屋はそれこそ小さな小さなところでした。 結局、光学が小説に書けるなら、ダムも小説に書ける。印刷会社だって書けるかもしれない。むしろ、印刷会社の方がおもしろい小説が書ける。 それが対等であるということは、つまり、光学もダムも小さな印刷屋も、それが働く人たちの世界であるということにおいては等しい。大小という観念はない。我々はいつも内部におる。外部に行くわけじゃない。奥さんなんかから見たら、うちのお父さんは小さな会社におるとか、大きい会社にいるというが、これは境界線を外から見ているからいえることなんですね、内側に入ってみると、境界は全然ついていないわけでしょう。だから、大も小もないのです。 僕は、内部におる、内部におると思っている(A)うちに、いつの間にか境界がぐっと内部の方にひっついてしまった。それは実は外部なんです(B)。 外部というのは、円を描いて、その外が外部で、円の中が内部であるというものではない。境界がついているものを外部といい、境界がついてないものを内部というというふうに決めておけば、そのままの姿でも外側が内部になり、内部が外部になるのです。ちょっと観念的になるかもわからぬけども、定義によってそうなる。それが『意味の変容』なのです。 |
||
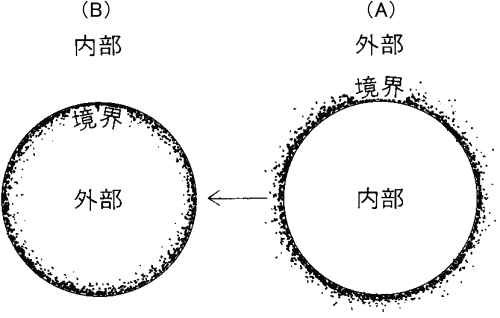 |
||
|
||
| 芭蕉の『奥の細道』の中の有名な言葉に、 雨矇朧として鳥海の山かくる というのがあります。彼は、翌朝象潟に行って舟を浮かべ、そこから初めてズバアッとした鳥海山を眺めるわけです。その鳥海山の麓に吹浦という農漁港がある。芭蕉はそこで、 あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ という句をつくった。 僕も、芭蕉が通ったというところへ行ってみたのです。そして毎日、鳥海山を眺めたり、海のかなたには飛島がありますから、それを見たりしておった。 そして、地図を書いてみたりしているうちに、何か今まで勤めてきたものと同じではなくて、大小があることに気がつきはじめた。 ところが、その大小というものは、外から見た場合にだけあるのですね。つまり、「既ニ死ヲ知ラバ何ゾ生ヲ知ラザラン」の見方でしかない。内側から見たら境界線というものはない。生きているということは、死んでいないのだから、死を知ることはできない。だから、生きている間に境界線はないのです。境界線、幽明境というものはいつも外部にあり、「死」にあるのであって、「内部」「生」ではないのです。 ところが、境界線はいつか中でつくるのです。すると、内部と思っているところが、あにはからんや外部になり、生と思っているものが死になる。それを「変容」といっているのです。 ところが、近代数学では、「近傍」という観念を使うのです。丸を描いて、円周が外側についているものを「近傍」というのです。実は、この内部が「壺中の天」です。 「壺中の天」なるものは何かといえぼ、双曲線空間なんです。つまり、非ユークリッド空間になります。この場合、双曲線の延びるところすべての空間であり空間でないと双曲線は描けない。だから、「壺中の天」は、実は双曲線空間なんです。「壺中の天」ということは、境界がそれに属してない。つまり、円周がついてない。内部に入り込んでいるわけです。 我々は、普通はユークリッド空間で教えられていた。それをある大天才、例えばロシアのロバチェフスキーとかハンガリーのボーヤイが平行線理論を説いたでしょう。平行線理論では、ユークリッドみたいな平行線はない、必ず交わる、交わってしばらくすると、また交わらない空間ができて、しばらくいくとまた交わる、としています。それを非ユークリッド空間というのです。その非ユークリッド空間のうちの一つが双曲線空間なのです。 はかの人は、ユークリッド空間ができて、いろいろなことがわかったといっているけれども、なぜユークリッド空間というものをつくらなければならなかったかというと、我々は無意識のうちに、非ユークリッド空間「壺中の天」におるわけです。だから、どうしても理想空間を考えないと計算できない。そのユークリッド空間の理想空間を破るのに、どのくらい努力をしなければならなかったか。その理論がいろんな方に通用するというのが「意味の変容」なのです。 |
||
|
||
| 僕の人生は「壺中の天」ですから、死ぬまで内部にいる。理念として、「既ニ死ヲ知ラバ、何ゾ生ヲ知ラザラン」というのは宗教です。真言宗でも禅宗でもみんなそうです。それは、生の方から死を見ているから、境界がぴっちりわかるわけです。そういう認識の仕方があるわけです。『意味の変容』に書いたことは、僕の人生観といってもいいことです。だから、本当はペンで書いて、ゼロックスでコピーして、本当に好きな人にだけ上げようと思っていたわけです。こんな本を出しても、頭の変なやつが出てきて、難しいことをいうとばかにされるだろうと思っていたら、結構若い人たちが読んでくれているようです。 僕のこの考え方は、一つの宗教、つまり世界観ですから、これ以上には発展させられない。もっと発展させたいなら、「トポロジー」、つまり位相数学を勉強しなさいといっているのです。僕がトポロジーを数学として説いても、むしろ民衆にはわからない。というか、そんな失礼なことは思っていないけれども、僕の分野ではない。 僕は作家であり、いろいろな人生を渡ってきて、僕の実人生に当てはめてみると、この「意味の変容」が、余りにも当てはまっていることに驚く。 変容(メタモルフォーゼ)という言葉は、別に特殊な言葉ではない。我々は常に変容してきているのです。例えば、「生」から「死」に変容することもできますし、「死」から「生」になることもできる。要するに「死生観」といってもいい。僕が死んだといってもいいし、変容してしまったといってもいい。キリストの変容は、むしろよみがえりの方にとっていますけれども、外側は「死」といっていても、それを中側で見れば、中側が「死」になる。 キリストは変容して蘇生したのですから、「ははあ、これは仏教でもキリスト教でもみんなに通ずるものだな」と思ったわけです。それを数学的にやれば、トポロジーであり、一言でいえば、それは「近傍」ということになるわけです。しかし、それから先の数学的なことは、数学者でもだれでもほかの人にやってもらう。僕にとって、そこから先は必要のないことです。 世界はどうして構成されるかということが小説です。小説は世界を書くことなのですから、男女のことを書いたり、暴力を書いたりしておっても、あれはあれで、世界を何とか書こうとしているのです。それが世界でないなどとはいえない。『戦争と平和』が世界であれば、彼らの書いたものでも世界なんですよ。少なくとも世界を書こうと努力している。そして、本当に世界を書けた人だけが残るのでしょう。 高級文学とか低級文学というのは、あまりないんです。だれかが外側から見てそういっているだけです。そしてまた、それを内側に魅き込むことを「魅了する」といって、外側に立っておられないような気持ちにさせてしまうのが、芸術の技術です。 小説でも、その小説の世界に魅き入れてしまう。小説を読んで、「こんなもの」といわれている間は、それに魅き込まれていない証拠である。本当のいい作品は外側の世界をいつの間にか内側に持ってきてしまうものです。読む人をして人ごとでない思いにさせ、外側から見ておられないようにするものです。それが「身につまされる」ということになるわけです。つまり、いつの間にか「意味の変容」が起こって、外部が内部にいることになる。それが結局、本当の小説だというように思っています。 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||