| 134 「内部と外部」 「二進法」的論理で生活し、人間をみる。 森敦 |
| 出典:ダイヤモンド・ボックス 昭和60年9月1日 |
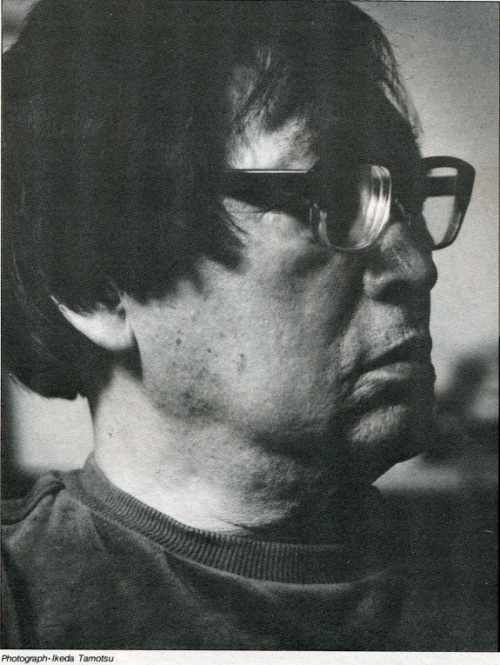 |
| もり あつし 1912年、熊本県生まれの作家。「月山」にて芥川賞受賞。20歳の天才青年として、横光利一の推薦で「酩酊船」を「毎日新聞」に連載。以後、日本国中知らないところなしとばかりに放浪。62歳で芥川賞を受賞、独得の人生観を持ち、ファンも多い。 |
| 「ぼくの『月山』を読んだ七五三掛のひとたちは、まるで昔のジイさん、バアさんが生きているような感じがするっていうんです。どうしてこんな細かい動作とかことばを覚えているのか、とね」 森敦さんの芥川賞受賞作、『月山』を読んで、なにか冥界にさそわれるような印象を受けた読者は多いことだろう。森さんの人間を見る眼が、徹底的にモノのディテールをしっかりとつかんでいるからこそ、『月山』の現場に最も近い人たちを驚かせたわけだ。月山のふもとにある注連寺に住む、若い男の雪にとじこめられた内部生活を描いたこの小説の裏には、森さんの独特な社会と人間に対する見方がある。 「いまでこそ、コンピュータの0と1のような二進法的な論理や、内部と外部が反転するメビウスの輪のようなパラドクスが問題になるようだけど、ぼくなんか、旧制中学生の頃から、このような見方で生活しようと思ってきましたよ」 少し前に出版された森さんの『意味の変容』(筑摩書房)は、評論家の柄谷行人氏らが注目しているが、そこには森さんの思考のエッセンスが集約されている。74年の『群像』初出時は、誰もその新しさに気がつかなかったようだ。いまでこそホッホシュタッターの『ゲーデル、エッシャー、バッハ』(白揚社)などの、コンピュータ学と、もののパラドクスをリンクさせる本が読まれる時期だから、『意味の変容』はそれとの関連で理解しようと思えばできるが、当時はそのテの情報がとぼしかったから、みんなその内容を理解できなかったのである。 森さんは20歳で『酩酊船』を毎日新聞に連載してデビューして以来、ひとつの会社で一〇年は徹底的に働き、得るものがあったと思えば仕事をやめ、次の一〇年は“遊び”に徹したという。まるでコンピュータ論理のオンとオフのような、放浪と定住の生活をささえている森さんの人間関係の読み方とは、どのようなものだったのか。 「ぼくは光学メーカー、ダム建設現場、印刷会社に勤めたのだけど、外からみれば三つの会社は大、中、小という規模でしかみえない。でも内部に入ってみると、ひとつの大きさであることは皆同じです。つまり、この世界と同じ大きさを持っているんです。たとえば、地球のようなまるい球面のうえに円を書くでしょ。するとそこには<境界>ができます。この場合、境界は、円と球面のどちらに属しますか? つまり、円を内部、球面を外部としますと、内部というのは、境界が内部に属さない領域であり、外部とは、境界が外部に属する領域なんです。内部は境界が内部に属さない領域ですから、無限であり、無限であることでは同等なんですが、境界が内部に属さない領域からみれば、大中小というように、大きさがちがって見えてくるんです」 まるで数学の集合論と禅問答を両方聞いているような感じにおそわれてしまった。森さんいわく、「いや、かんたんなことですよ」。勝手に解釈してみれば、こういうことだろうか。たとえば、日本の会社人間は、自分の会社のことを“うち”と言う。すなわち“内部”という帰属意識をほとんど無意識に持っている。人間関係さえも、同じ会社のとなりのセクションのヒトを“外部”とみなして「うちの課こそ……」などと、時には敵対意識をむき出しにしがちだ。 |
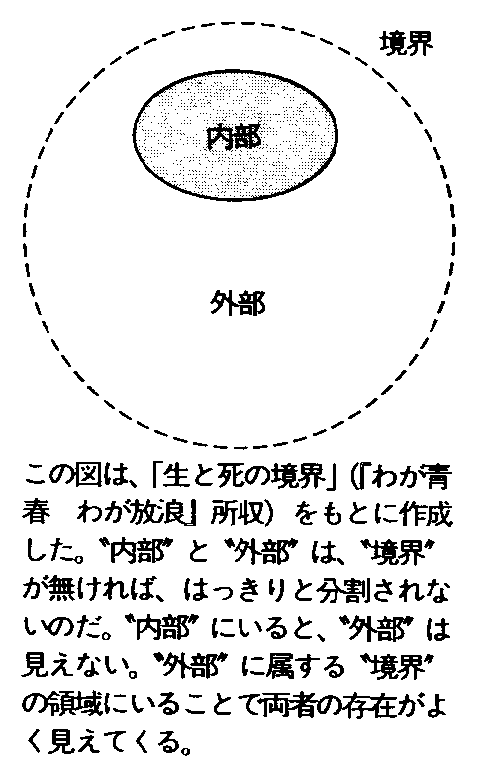 |
| 仲間意識とか、サラリーマンがよく持つ“領分”を侵されることへの恐れ、いらだちというのは、まったく森さんのいう“境界”を欠いた“内部”に、すっぽりと取りこまれてしまっていることからきているのではないか。森さんは、境界は外部に属するものだ、という。森さんはどの会社でも十分に勤め、「勉強させてもらった」と、満足感をもってやめたともいう。 数学の考え方ではすでに普遍化しているらしい、この“境界”という視点で、森さんが会社の人間関係を見ていたことからくる満足感ではなかったか、と、勝手に解釈してしまった。境界に視点をうつせば、社内の人間関係もよく見える! この解釈でいいんでしょうか? 森センセイ。 |
| (N) |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |