| 142 小説は交響楽でなければ… 森 敦氏に聞く |
||
| 出典:赤旗 昭和62年3月21日 | ||
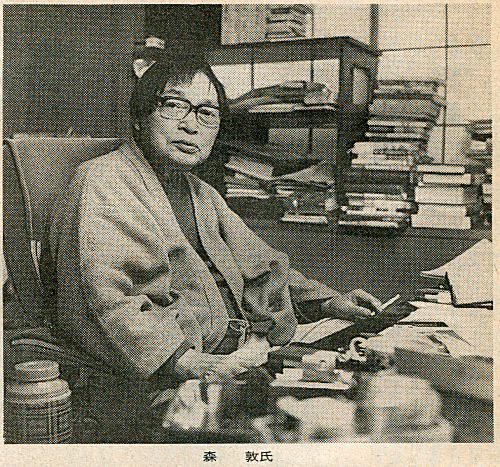 |
||
| 「月山」で芥川賞を受賞(一九七三年)した森教(もり あつし)氏は、今年で七十五歳。最近、三年がかりの長編「われ逝くもののごとく」(『群像』連載)千六百枚を脱稿しました。東京・飯田橋、外堀通りの桜並木を眼下にのぞむ自宅を訪ね、話を聞きました。 | ||
| (牛久保建男記者) | ||
|
||
| ──三年間、一回も休まないで連載を続けたというのは大変なことだと思いますが、作品としてもこれまでで一番長いものになりますね。 「何か大きなビルを建てるような作業でしたね。連載を終わってから書き直していますが、全然違うものになります。今は、これに渾身(こんしん)の力をふりしぼってます。出版社はあまり喜んでいません。はやい話が、一丁あがりでいきたいわけです。このごろの作家は一丁あがりが多いんですよ。僕もね、天命を知ってきましたから、やっぱり今生の思いのつもりで書かないと、ちょっと困るわけですよ。三十代の青年と違うわけですから。ただし僕は、六十ごろになって東京にあがってきたわけです。それから書いたもんだから、こんなえらいことになっているんです」 ──作品の時代は、太平洋戦争末期から戦後にかけてですね。やはり山形県の月山を中心とした世界ですね。 「『月山』をもっと拡大してゆこうと思ったんです。庄内のあっちに住み、こっちに住みしてましたから、そこで出会った人々を書きとめたいと。地元では、登場人物をさして、あれは、おらほの親父だなどといっているようです」 「僕は小説は交響楽でなければだめだというのが念願だったのです。それをいつか書いてみようと思ってね。日本の文学には、いわゆる独奏はいいものはたくさんあると思うんです。だけど交響楽というのはあまりない。トルストイや、ドストエフスキーのように、僕もオーケストラにする以上多元描写にしないといけないと、意識してやったんです。多元でないと広くとらえられないんです」 |
||
|
||
| ──「われ逝くもののごとく」というのは、印象的な題ですが…。 「『論語』の『逝くものかくのごときか、昼夜をおかず』からきている言葉です。たとえば、川の流れに小波がピカピカ光りますね。それを一つひとつとらえていったら、何か命題がでてくるのではと。それに三年かかったんです。人間は死んでいくもの、これだけは確実なことです。実際、この作品でも登場人物はどんどん死んでいきます。僕だけがのこっているわけです。だから生きとる間に何とかしなければならない。死んでいくから現在を大切にする…」 「会社に勤めていたって何だっていいんですよ。そこで本当に充実した人生を送れるかどうかね。また充実してないっていっている人は、自分がさせてない人が多いんですわ」 ──青春時代には、横光利一に師事し、太宰治、檀一雄らと深いつきあいをされてますが、プロレタリア文学などはどうでしたか。 |
||
|
||
| 「プロレタリア文学というのは、ぼくはやっばり尊敬しましたよ。プロレタリア文学をした人はね、命をかけてないとできないんですよ。殺されるかもしれない、実際に殺された人もたくさんおるんです。文学的にも立派なのがたくさんあった。だがいつの間にかいなくなったから、どうしたのかと思うと、警察にいったと。あの文学運動は弾圧されたからつぶれたんです。彼らの仕事を今日明らかにすることは大切なことです」 現在刊行中の『日本プロレタリア文学集』(新日本出版社)について、「本当に意味がある」と何度もうなずきながら── 「プロレタリア文学と純文学の作家は文学的には争っていたが仲はよかった。それが文学の発展にもなったが、現在は、ぬるま湯的な空気にひたって、いいものがでない」 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||