| 148 森 敦(作家) 人間の存在はすべて「逝くもののごとく」 |
| 出典:紀伊國屋カード通信「しおり」第21号 昭和63年5月20日 |
 |
| (もり あつし) 一九一二 (明治四十五)年一月二十二日、長崎市銀屋町に生まれる(原籍が天草のため、戸籍面では能本県天草郡の出生となっている)。「敦」という名は「汝、徳を敦うせざれば危うし」ということから父が命名した。朝鮮京城府鐘路小学校、京城中学校卒業後、昭和六年、旧制第一高等学校に入学したが、翌年、依願退学。昭和九年、二十二歳の時、師と仰ぐ横光利一の推輓で、処女作「酩酊船」を「東京日日新聞」・「大阪毎日新聞」に連載。昭和十六年(二十九歳)、横光利一夫妻の媒酌で、山形県八幡町の旧家の娘・前田暘と結婚(夫人は昭和五十年他界した。享年五十七歳)。やがて、各地を転々とした放浪生活が始まる。この間、表だった創作活動はほとんどなく、たまに檀一雄主宰の同人誌「ポリタイア」に作品を発表。昭和四十九年、一月「季刊藝術」(第26号)に発表した「月山」で第七十回芥川賞(昭和四十八年下半期)を受賞。六十一歳という最年長の受賞だけに世間の話題になる。以後、今日に至るまで精力的に作家作動を続けている。また昨年『われ逝くもののごとく』(講談社)で野間文芸賞を受賞。著者のライフワークともよべる大作で、目下、七版を重ねている。 |
| ◎思えば不思議な人生を歩んできた |
| 六十一歳で芥川賞を取り、今度は七十六歳で野間文芸賞をもらった。野間文芸賞の『われ逝くもののごとく』は三年半かかり、千五百枚にもなったんです。芥川賞のときも、今度も年齢のことが話題になってしまうんですが、こうして考えてみると、自分でもどうも不思議な人生を生きてきたと思いますね。 僕は書きだしたのはかなり早かったんだが、その後日本全国を放浪しておったでしょう。自分でも、いつごろどこにおったのか、もうよくは覚えていないんですよ。山形県にしばらくおったんですが、村の人たちが「森さんは、あのじいさんがおったときにいたのう」とか、あのばあさんが何をしていたときにおった、とか言う。そんなことを調べて歩いた人間がおって、それでようやく三十五歳ごろからのあしかけ十年だった、ということが明らかになった、という具合で、自分では分からない。そんなものですよ。自分では、もう忘れちゃった。 僕の人生は、大体十年周期で、十年働いては十年放浪する、そんな繰り返しでした。 ふるさとから離脱したいという気持ちが結果として、放浪になったのかもしれない。でも、放浪は何かを求める気持ちがさせるものであって、きっと何かを求めておったのでしょう。 奈良にも数年おったし、庄内にも約十年。ところが、『月山』のときも、今度の『われ逝くもののごとく』のときも、どうも作品の舞台としては、庄内になるんですね。 僕が初めて庄内地方に行ったのはもう四十年以上も昔の話になるんですが、明るい太平洋沿いから行ったせいか、この暗い日本海沿いの生活には、妙に引かれるものを感じたんです。吹浦、狩川、酒田、大山、湯野浜、加茂といった庄内の町や村を転々としていたんですが、そのどの町にも本当の生活があるように思えたんですね。いつのまにか、庄内がわがふるさと、のごとくになっておったような感じです。 庄内で力のあった家の娘と結婚した縁で、たまたま庄内に足が向いたんだが、ここには日本人の原質ともいうべき何かがあったんです。それでたまらない愛着を覚えるようになったんでしょう。 |
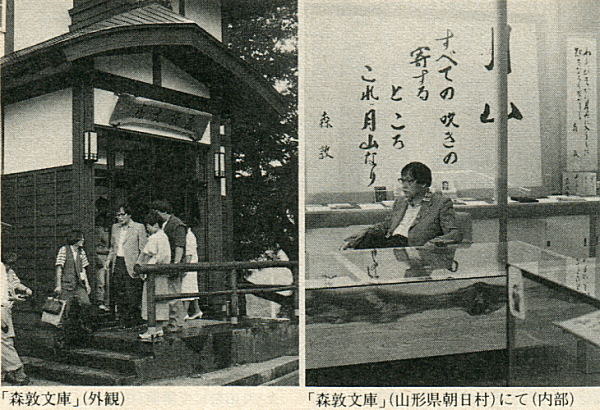 |
| ◎どんな人間でも抱え込む社会 |
| 庄内、中でも酒田は、東北ではあっても北前船のおかげで、関西と直結していて、文化的には非常に進んでおったんです。酒田では御殿女中をみな京都から呼んでおったんですよ。だから、言葉にも柔らかい関西風の響きがある。そういう洒落た町でありながら、「やっこ」というのがおりましてね。「やっこ」は、ちょっと智恵が足りないような人間なんですが妙な特権をもっておって、たとえば『われ逝くもののごとく』にも三人のやっこが登場してるんですが、「安」というのはいつも、“わっぱ”を持っていて、当時の酒田には三十八軒の酒蔵があったんですが、そのどこの酒蔵に入っていっても、そこでいちばんよい「蔵酒」をわっぱいっぱいもらえるんです。それで、朝から酒をくらって寝ている。多分、「安」に酒をやらないと店が傾く、そんな言い伝えがあったんでしょう。酒造家なんていうのは、案外信心深いですからね。「安」は人が通りかかると「明日は晴れだぞう」とか、あんまり当たったことはないんだが、天気予報のようなことをするんですね。「お松」という女のやっこはいつもほうきをもっておって、道をはいている。それで、何かをもらって生きている。もうひとりの「やんぞ」というやっこは、善宝寺に住んでいるんだが、高い階段を登って、薪を運んでいる。それがどんなに小さい薪でも、雷で倒れたひとかかえもあるような薪でも、一度に一本しか運ばない……。そういうのが、本当におったんです。こういう社会はおもしろいなあ、これを書いてみよう、と思ったのが今回の小説なんです。 |
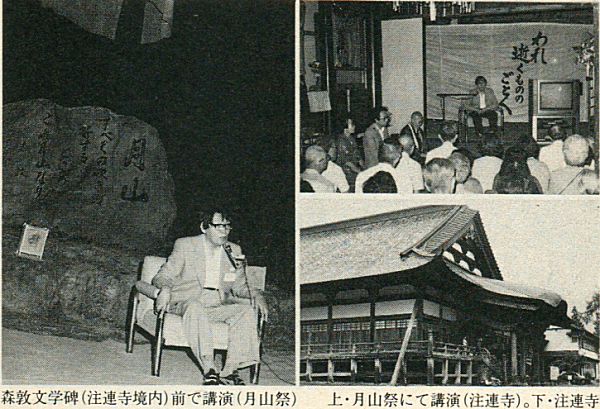 |
| ◎胎蔵界の構造で書いた作品 |
| 京都の東寺に「現図曼荼羅」というのがあるんです。金剛界が左手、胎蔵界が右手にかかっていて、僕はそれを見せてもらったことがある。五人がかりくらいで広げないと見ることができない、という大きなものなんだが、胎蔵界曼荼羅というのは、ピラミッドのような構成になっているんです。一番下をなす層があって、その上にもう一層あって、その上にさらにもう一層ある、というような、下から積み上げていく、という構造ですね。 僕がこれまで書いた『月山』などは、反対に大きいところから、下へ、下へとおろしてくる、という構成だったんです。これは「金剛界」の構造なんですね。 ぼくは、『われ逝くもののごとく』は「胎蔵界」の構造で書いてみよう、そう思って、「やっこ」から書いたわけです。どこの町にも「やっこ」がいまして、酒田には道を行ったり来たりしている女の「やっこ」がいた。彼女は数字は十までは知っているんだが、順序を知らない。彼女はおそらく十歩歩きたかったんだ、と思うんですが、三の次に五が来るんだか、六が来るんだか分からなくなってしまう。途中で分からなくなってしまう。だから、いつまで経っても十に達しないから、行ったり来たりしているんですね。 後になって、その「やっこ」達に会いたい、と思って訪ねてみたんですが、もうひとりもいなくなっちゃった。皆、施設に収容されちゃったんです。 僕は、こういう人は天の子だと思うんです。だから、歩きたかったら歩かせておけばいいんで、施設なんかに収容する必要はないんじやないか、とまあ、そういうことも書きたかった。 そういう「やっこ」などの社会の最上層に大日如来がいるんです。大日如来は万物破壊、万物創造の仏で、それを「サキ」という少女が探して歩く、とまあ、そんな話を書いたんです。 当時の庄内では、酒田から来た人間は「酒田」と呼ぶ、そんなならわしがあって、西目というところから来た人が洞窟におって、それが大日如来なんですが、それを皆で「西目」と呼んでいた。ところがここにもうひとり西目からやってきた人間が現れて、それも「西目」と呼ぶものだから、区別をしなければならなくなった。それで洞窟のほうの人間はいつも「われ逝くもののごとく」と言っておったので、その人物を「われ逝くもののごとく」と呼ぶようになったんです。「われ逝くもののごとく」とは論語の「逝くもの斯くの如きかな、昼夜を舎かず」から取った言葉です。僕は孔子ほどえらい人間じゃないんで、われわれは、せいぜい水の表面がキラキラ光っている、そのきらめきの一片にすぎないから、われわれの存在は「逝くもののごとく」である。そんなことを考えて書いた小説なんです。 大日如来というのは、さっきも言ったように、万物破壊、万物創造の仏なんです。最後のほうに、十二滝、これは最上川の支流の北俣川をさかのぼったところにあるんですが、そこにきれいな大きな石がたくさんあったんです。ところが、林道を作るためにそれを破壊している男がいる。万物破壊の大日如来なんですね。ところが「わたし」がその男を見ているうちに、その男がすうといなくなって、いつのまにか「わたし」がその男になって、石を破壊しているんです。 「逝く」ということは、一回死ぬことだ、と思うんです。でも「死ぬ」というのは僕が死ぬんじゃなくって、周囲の人が過ぎていってしまうことじゃないか。そうして「無」になるんじゃないか、とそういうことも書いたつもりなんです。 |
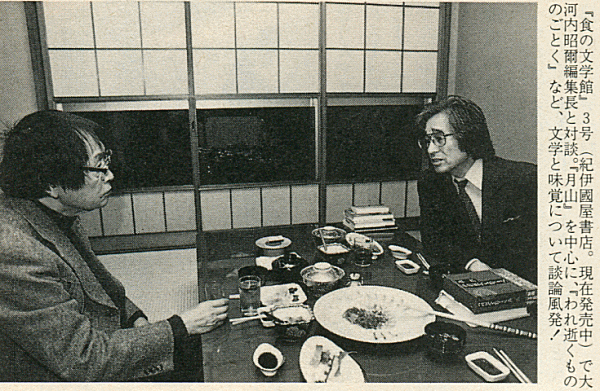 |
| ◎すべて月山の体験から生まれた |
| 『われ逝くもののごとく』は三年以上もかかったので、書き終わったときは、ほっとして、嬉しかったですね。 僕は、以前に「人生の一点一画が違っても、現在はありえない」と書いたことがありますが、『月山』がなかったら、今度の『われ逝くもののごとく』も生まれなかった。そして『月山』は、昔、酒田におったとき、注連寺という荒廃しきった寺があって、そこで冬を過ごしたことから生まれた。すっかり荒れていて、寺守のじいさんだけがいる。というような寺で、そこで、冬を過ごしたのは、女房の母親が「あそこの紅葉はきれいだから、ぜひ見ていらっしゃい」と勧めてくれたんです。それは美しい紅葉で、ちょっとこんな紅葉は見たことがないというくらいすごいものでした。紅葉をみたので「帰る」と言うと、寺のじいさんが「雪を見て帰れ」と言う。そこで滞在をのばして雪を見た、月山が白くなって、そのうち下の仙人岳、それから塞ノ神峠が白くなり、やがて十王峠が白くなって、ものすごい雪が降ってきた。こうなったら、もうバスも通らず、翌年の春までいるしかない。でもこのときの体験がなければ『月山』が生まれず、『われ逝くもののごとく』も生まれなかったんです。 |
 |
| ◎次は滑稽小説を書きたい |
| 『われ逝くもののごとく』は僕が死ぬ前に、ぜひ書き残しておきたい作品でした。書き終えてみると、書きたいことはまだまだあって、今は芭蕉の「奥の細道」を書いています。芭蕉も放浪をした文学者で、出家者ではなかったけれど、出家者よりももっと仏教的だった。しかも、芭蕉は実に計算しきった旅をしていますね。 それから、これはずっと昔から言っておるんですが、僕はセルバンテスの 『ドン・キホーテ』が好きでね。こういう滑稽小説を書きたい。 毎年八月末にやっている「月山祭」もだんだん参加者が増えてきて、僕はだんだん山形の人間だと思われるようになってしまった。いつのまにか、山形が自分の中でもふるさとのようになってしまって、さんざん放浪したあげくに、ふるさとを持つ、という人生の不思議には、驚くような気持ちでおるんです。 |
 |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |