| 149 教師の図書館 十年前の『月山』の極をなすもの 『われ逝くもののごとく』森 敦著 |
| 出典:『中学教育』 昭和63年6月1日 |
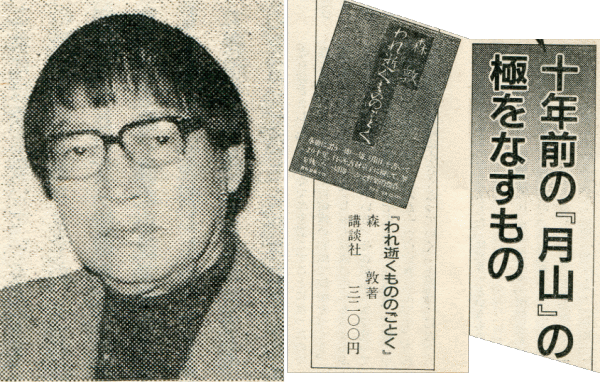
|
| 作家 森 敦氏 略歴 一九一二年長崎市生まれ。旧制一高中退。横光利一に師事する。昭和49年『月山』で芥川賞を受賞。主要著書に『鳥海山』『私家版聊斎志異』『文壇意外史』などがある。 |
| ──野間文芸賞ご受賞おめでとうございます。反響はいかがでしょうか。 森 みなさんが読んでくださるのはありがたいんですが、五十冊とか百冊とかまとめて買って、それにサインしてくれといわれるんですね。僕は手が書痙なもんで痛いんですよ。それでいま困っています。(笑い)『月山』を書いてから、純粋な小説を書いたのは十年めなんですね。ふつう、十年も小説を書いていなかったら誰も頼まないでしょう。それを「群像」の編集長が書いてくれといってきた。四年かけて千八百枚書きました。それが野間賞をとったということで、また騒がれてしまった。僕が『月山』を書いて芥川賞をとったのが六十一のときでしたから、そのときも大騒ぎされましたがね。 こんなに厚くて、しかも値段の高い本が今八刷なんですね。この十年間、随筆は書いていますが、小説は全く書いていませんでしたから、それで読まれるんでしょう。 ──装幀も立派ですね。 森 司修さんという方がやってくださったんですが、これには僕も驚いているんです。函の裏に三角形と金色の輪が描いてありますが、これは、万物を破壊し、かつ創造するという「胎蔵界大日如来」の力を現わしたものなんですね。僕が小説で書こうとした「胎蔵界」というものを、別に説明したわけでもないのに司さんは、装幀で表現してくださったわけです。この本は、函までがものを言っていると評されたものもありました。 ──先生がお書きになろうとした「胎蔵界」というものについてご説明ください。 森 僕のいう「胎蔵界」は、東寺にある「両部曼荼羅」の一つです。左手にあるのが「金剛界曼荼羅」で、「一即一切」を表し、右手にあるのが「胎蔵界曼荼羅」で「一切即一」を表しています。「一即一切」と「一切即一」はイコールなのです。「金剛界」というのはこういうことです。蓮の葉に朝露が輝いている。その朝露は玲瓏玉のごときものである。だとすれば、この朝露は全世界を映し出している。実は映し出しているのではなく、その朝露の中に全世界があるからだ。全世界があればこそ、全世界を映し出している。もし、全世界があるならば、その中にも蓮の葉があり、朝露も輝いているであろう。その中の朝露もまた全世界を映し出していることになる。このようにして、無限に朝露が続いている。ということは、ずっと無限大に小さくなつていっても、そこに一切があるということになるわけです。これが「一即一切」ということです。 この考えで『月山』は書かれています。だから、山形県の庄内平野を書き、そして月山の山ふところの七五三掛という小さな村を書き、さらにその村の注連寺という寺を書きました。その寺で冬を過ごすことになったので寒さをしのぐために寺の祈祷簿の和紙で蚊帳をつくり、その中に僕はおりました。しかも蚊帳の中にあるどんぶりの中には一匹のカメ虫がいる。それがふちまで登ってはまた落ちる。庄内平野、七五三掛、注連寺、蚊帳の中そしてどんぶりの中、みんな一つの世界なんです。それを、朝露が無限に小さくなっていく「金剛界」になぞらえて、中へ中へ、小さく小さく世界をとつていったのが『月山』なんです。 それとは逆に、中の朝露から外の朝露に、それからまた外の朝露に、そしていちばん大きな朝露にというふうに、中から外にべクトルを向けて書いたものが、『われ逝くもののごとく』なんです。これは、「一切即一」を表わす「胎蔵界」の構造ということになります。 ですから、まずその小さな世界として加茂という山に囲まれた村を書いた。そこからトンネルを抜けると広大な地域になり、少しずつ円を広げていきますと、鶴岡や酒田があらわれる。その庄内平野というものが、まさしく月山や鳥海山に、あるいは防風林に囲まれていて一つの世界を成しているというわけです。 「一切即一」の「胎蔵界」というのは、絵にかきますと、いろんな仏様が雛壇にのっているんですね。ですから、上からみますと、大中小の四角が三つ重なって書かれているだけなんです。立体的に考えますと、三段の山になっている。いちばん下のところは、ちょっとみれば救われないような人、異域の人、異人なんです。『われ逝くもののごとく』では、“やっこ”にあたります。酒所である大山には天気のことしかいわぬ安、善宝寺には、大きいものでも小さいものでも薪を一本ずつしか持って石段を上がらないやんぞ、鶴岡にはお松という女の“やっこ”というように、いろんな土地にいる“やっこ”から書いていっています。仏教においては、“やっこ”になることは“三宝のやっこ”になることに通じるんですから、“やっこ”である間は“やっこ”だけれども、“三宝のやっこ”になった瞬間、これは“聖”になるんです。 そして、中の段には菩薩や天人がおられる。「なになに様」と名前を書かないんや、そのほとんどが天人である“あねま”(遊女)がそれにあたり、いちばん上が、「胎蔵界大日如来」です。湯殿山のご神体、大渓谷にある温泉の湧出する大岩石は「胎蔵界大日如来」とされていますからね。「胎蔵界」の構造に合致するのです。 ──お書きになる前からこういう構想をもっておられたのですか。 森 初めはそんなことまで考えてやったんじゃないんです。三分の一ぐらいきたときに、おっ、これは「胎蔵界曼荼羅」が書けるなあ、ということに気がついたんですね。ただし、『月山』を書いてから、今度書くものは、何かそれと極をなすものにしたいなあということはずっと考えておったんです。 僕が直接出て、こういうむずかしいことを書いてはかえってわからなくなると思って、華厳経の善財童子になぞらえて、サキという女の子を遍歴させたわけです。 善財童子というのは、五十三人の偉い人をたずねて、頂上をきわめるということになっており、ジャワのボロヴドゥルの塔は、善財童子がまわったあとを彫ったものなんですよ。東海道五十三次というのもこれからきているんですね。華厳経というのが、昔はいかに一般に広がっていたかということがよくわかります。 『われ逝くもののごとく』では五十三はまわっていませんが、困ったことに、山形の人たちが、これがサキに違いないといって写真を持ってくるんですよ。(笑い)そんなのいるわけないんです。僕の心の中の善財童子なんですから。また、僕は昔加茂に居たことはありますが道がどうなっていたか、僕のおった家がどの辺にあったかなどということは全く覚えていないのです。僕が考えていたことを書いただけなんですけれど、あそこの人はよく森さんは加茂のことを調べて書いたもんだ、いつ調べたんだろうと感心されています。(笑い) ──先生にとって小説をお書きになるということは、どういうことなんですか。 森 ものを書くということは、雲があらわれてその雲が美しいということも文学の要素の一つではありますがその背後に論理を持っていなくてはいけないのです。 孔子様とかお釈迦様というのは、世界を包むようなものすごい背後論理を持っているんですね。そういう人の書いたものに会いますと、ふしぎなことに反射して僕も背後論理を持つことになるんです。『論語』や経典などむずかしいといわれる方が多いと思いますが、あれは、人間は“こんにちは”に始まり“さようなら”で終わるということが書いてあるんです。僕の小説もそうなんです。人生というと大変なことのようですが、“こんにちは”“さようなら”なんですね。 僕の小説の中で僕が大きな背後論理を持ち得たとしてそれを読む方がいくぶん納得してくださったり、面白いなと思ってくださるのなら、その人もまた背後論理を持ってくれていることになるのです。僕がその人に背後論理を授けるなどというえらそうなことではなく、それがひとりでに感応するということなんです。 僕は、これを“対応”“コレスボンダンツ”といっています。『われ逝くもののごとく』において、僕は『月山』のときより、この“対応”による構造をより深く構築しようと試みました。 物語または筋と呼ばれるものは、なんらかの意味で密接に時間の線上にあります。むろん時間も構造を持っている。私たちが過去、現在、未来というとき、すでに時間を構造として捉えていますね。しかも構造は時間なきものと思われがちです。そこで僕は、物語または筋を、それらが密接にその線上にあるところの時間として書いていくと、奥へ奥へと組み立てられる構造になると思ったんです。構造を奥へ奥へと組み立てていくと、ある一つのベクトルが出るわけです。ベクトルというのはある方向を持った考え方と思えばよろしい。これこそが時間というもので、何月何日にどうしたということは本当の時間ではないのです。小説というものは、こうした時間をあらわしていかなければいけないんです。 ちょっとむずかしくなりましたかね。(笑い) ですから僕としては、芥川賞や野間賞をもらうことはもちろん嬉しいですけれど、多くの人に読まれ、僕の背後論理に感応してくれる人が増えるほうがはるかに嬉しいですね。 ──“森敦の生死一如の全思想を集約した交響楽的長編小説”という惹句がありますが、先生の生死一如の思想とはどういうものですか。 森 仏教はすべて生死一如を説いています。生死一如のために私たちは修行をする。これは仏教の修行でなくてもいい。苦しんで何かをやればいいんです。私たちが苦しむということは、主観と客観が一致しないということなんです。 主観というものは、どっちに向いているかは別としてある方向を持った考え方であることは間違いないんです。それに対して客観というのは逆の方向を持っているわけです。 目に見えるものを客観というのではなく、主観も客観も自分の心の中にあるのです。その主観と客観が一致するということは、同じベクトルが一直線上にあって長さがピシッと等しくなるということです。数学でゼロになるということですね。 偉い人のベクトルというのは、主観もいく方向に無限大、客観もいく方向に無限大であり、しかもいずれもゼロになっている。ところが小人にはその主観がわからない。ただし、小人といえども極端な主観はわかる。それが“生”です。これ以上大きな主観はないというものが“生”なんです。それに対して最大の客観が“死”になるわけです。この最大の主観と客観を一致させてゼロにするということを“空”とか“無”になるといいます。簡単にいえば悟るということですね。これが生死一如ということです。悟るために修行する、坐禅をしたりヨガをやったりするわけです。 僕は、生も知りたいけど知ることができない、死も知りたいけど知ることができない。しかし、生死一如ということで“空”になることはできるわけです。 ──仏教に興味を持たれたのはいつごろからですか。 森 仏教そのものに興味を持ったかどうかわかりませんが、僕は二十歳ぐらいの子供のころ、東大寺にしばらくおったことがあるんです。 入学して八か月ばかりおった一高をやめた後、横光利一にすすめられて『酩酊船』を新聞に連載しました。それを読んだ東大寺の上司海雲という人から、「何もせぬでいいから、とにかく東大寺に来て遊びなさい」という手紙をもらったので、東大寺に行ったんです。 彼も文学青年だったんでしょう。ほんとうに何もせずに、朝からお酒をいただいたり昼寝をしたりしていたわけです。決して修行で行ったわけではないんです。僕はほとんど経典というのは読んでいないのですが、ずいぶん考えましたね。知識があるとすれば、すべて門前の小僧です。 僕の小説は、華厳経で書いたわけでもないし、正法眼蔵で書いたわけでもないんです。僕の小説には坊さんは出てきませんからね。ただ、仏教というものは、さっき言ったようなコレスポンダンツというものを持っているんですね。一つの世界に同感させる力があるんです。魅了ということです。魅了しなければ何もできない。魅了されたから納得するんですね。それは仏教に限らず、小説にもいえるということでしょう。 ──『酩酊船』でデビューなさった後、“忽然と”文壇から姿を消されたといわれておりますが、それには理由があったんですか。 森 “忽然と”じゃないんですよ。僕は東大寺に行ってお酒を飲んだり、いい気持ちになつて昼寝をしとっただけなんです。龍宮城に行っとったようなもんです。(笑い) 奈良の東大寺と瑜伽山に足かけ十年、浦島太郎のようにいい気になっておったわけですが、帰ってきたら太宰治は死んどるし、文壇の様子もすっかり変わっていた。それから後は戦争ですから、働かざるをえないわけです。僕の十年働いて、十年放浪するというその後の生き方はここから始まっているんです。このパターンでいくと、次に書くときは八十五歳になっているわけです。恍惚の人になっているかもしれない。でも僕は、恍惚をきらわずに、ありがたいと思って恍惚の人になりたい。 ──どうもありがとうございました。 |
| ↑ページトップ |
| 森敦インタビュー・談話一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |