| 022 顔 世界の構造を見る視線 |
| 出典:日本読書新聞 昭和49年2月4日(月) |
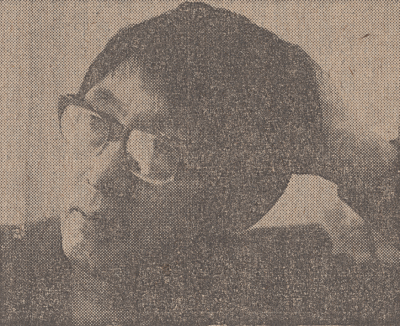 |
| 一九歳の時、横光利一らの推挙で、「ダンディズムとデカダンスの小説」と自ら評する「酩酊船」(これの題は勿論、ランボウの詩から取ったものである)を発表した森氏は、その後、檀一雄氏に誘われて太宰治らと共に「青い花」の同人となったが作品は発表せず、「ダンディズムとデカダンス、すなわち文学とは反思想的思想だという自分の信条」故に、日本浪曼派には接近しなかったと言う。そして戦後も「ポリタイヤ」に短編を幾つか発表した以外は、沈黙を守ってきた。しかし今回の受賞作「月山」にしろ、「天沼」(「文芸」新年号)にしろ、これらの近作は氏の四十数年の文学的沈黙の意味を我々に明かしてくれるように思う。 「独自性は棄てる事によって出来るものだ」と氏は語ってくれたが、森氏の静謐な視線は「この世のもの」を全て削ぎ落しながら、「この世ならぬ」死の世界を浮び上らせる。それはあたかもランボウが酩酊、錯乱を通して獲得した見者の視線のようである。沈黙の四○年はこの視線を獲るための時間であったのではないだろうか。 そのような視線について氏は「私は風景描写が上手いと言われるが、そうでなくて、私の眼は何時も地形に向いている。地形を見ていると世界の巨きな構造が見えて来る」と言い、また「知を捨てて初めて大きな叡智が出るように、世界も個も無意味にする事によって、それから大きな意味が出てくるのです」とも語ってくれた。その「構造」、あるいは大きな「意味」とは、例えば「天沼」において冬の山に囲まれた空が突然「沼」に見えた瞬間を指すのであろう。そして、その〈天沼〉は、あるいは、「この世ならぬ」人々の背後に何時も無言で聳える死の山〈月山〉は、見者としての氏が究極に視線を向けている生の彼岸に、ふと垣間見る名付け難い何物かなのではないだろうか。 「これから何を書くのか自分でも分らない」と語る氏は、やはりランボウ的な意味で真の文学的冒険者なのである。この国では稀有な、この真の文学的冒険者のこれ以降の歩みを追っていく事は、読者にとっても又稀有な冒険であるように思われる。 |
| ↑ページトップ |
| 森敦関連記事一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |