 |
| 051 『天沼』注解 岩井克人(東京大学経済学部助教授) |
| 出典:森敦著『意味の変容』付録 昭和59年9月 |
|
| 寺のじさまのすすめるままに、さわ(沢)まで出てきた「わたし」は、はるか下のほうからさわ道を登って自分の木小屋に行こうとしているもくえんのじさまに誘われて、一緒に雪のさわ道を登りはじめる。さわを登っているかと思っているうちに道はいつのまにやらさわをはずれ、さわをはずれて歩いているかと思っているうちにいつのまにか道はまたさわに戻っている。いつしかじっとり汗ばんで、じさまのあえぎに合わせてあえぎはじめるうちに、また雪の斜面になり、ふと遠くを見ると十王峠と西山のあいだにも山があることに気づく。じさまはそれが天沼山だと教えてくれる。 |
「なるほどね。あの上にそんな沼でもあるんですか、天沼山というのは」
「沼はねえんども、登れば向こうさ、また山があるもんだ。天沼というなださけ、どっちゃも山で天がそげだに見えるというんでねえか」
「そんなら、ここも天沼じゃありませんか」
「まンず、そげだもんだ。おらほうだばどの山さ登っても、どっちゃもたンだ山だでの」そう言われれば、頭上を掠める重く渦巻く冬雲がほんとうに天沼のように思えて来ただけではありません。…… |
(『天沼』)
|
|
『意味の変容』のなかで、森敦は次のような命題を提示している。
〈任意の一点を中心とし、任意の半径を以て円周を描く。そうすると、円周を境界として、全体概念は二つの領域に分かたれる。境界はこの二つの領域のいずれかに属さねばならぬ。このとき、境界がそれに属せざるところの領域を内部(あるいは近傍)といい、境界がそれに属するところの領域を外部(あるいは域外)という>。そして、さらに、<……円内の任意の点には、必ずこれに対応する円外の点がある>。
すなわち、内部と外部でいわゆる全体概念が成立し、しかもそのなかの内部と外部とはおたがいに対応すると言うのである。それゆえ、内部とは全体概念の一部でありながら、同時にそれ自身全体概念をなすものでもあると考えられる。そして、「天沼」──「天沼」とは、まさに内部において実現している外部、すなわちここではない世界でありながら、同時に今「わたし」が歩いている地点の近傍において実現している世界のことなのである。それは、まさにそれ自身が「天」である「壷中の天」、いや近傍の天にほかならない。 |
……かつて考えもしなかったこの別天地に来ながら、なんだかここにこうして来たことがあるような気すらしたのですが、わたしが思わずそう言うとじさまは頷いて、
「ンでろうの。十王峠を越えて来た客も、よく前世を思いだしたみてえなこと言うたもんだけ」
「前世を……」
「ンだ。過ぎた世をの。どうせおらたは出たとこさ、戻するよりねえなだし、それで月山を過ぎた者(死者)の来る山というんでねえか。だども、冬ででもねえばとてもこうは見えねえもんだ。よう見るんだちゃ。これがおらほうのけえしき(景色)というもんださけ」
「…………」
そう言われるとわたしにも、なんだかここに来たような気がしたのは、気だけではない。われともなく忘れてしまっていたところに、戻って来ていたように思えるのです。 |
|
だが、カントールやゲーデルをもちだすまでもなく、全体概念とはそれ自身矛盾をふくむものである。なぜならば、全体概念である内部を内部たらしめている境界とはそれ自身けっして内部に属することはできず、それゆえ内部とはけっして全体概念として自己完結しえないものなのだからである。この矛盾をはらむ外部の境界なるものと、内部において対応している点が内部の中心あるいは近傍の原点にほかならない。中心とは、全体概念としての内部なるもがもっている矛盾をすべて集中した点である。そして、われわれ人間とは、<われわれの近傍の原点に、矛盾として実存>しているものなのであると森敦は言う。
だが、同時に、〈矛盾はつねに無矛盾であろうとする方向を持つ〉。 |
「来ましたね、やっと。あれでしょう、木小屋は……」
とわたしが言うとじさまは、
「ンでね。あれも木小屋だども、いまはもう廃れてしもうた木小屋だの」
……
「じゃア、じさまの木小屋は、もっと上にあるんですか」
「ンだ。もくえん(杢右ヱ門)の木小屋は山の上ださけ、まだ余ッ程あるの」
|
|
| ところで、〈任意の一点を原点として、境界がそれに属せざるところの近傍と、境界がそれに属するところの域外に分かたれる構造をもつものを空間という〉ならば、〈時間もまた空間と見做すことができる〉。しかも、〈現瞬間を原点としてなすところの近傍には、いくらそれを小さくしても、その中に過去と未来が含まれる〉が、〈過去と未来はあきらかに対立矛盾するものだ〉という。しかしながら、〈矛盾はつねに無矛盾であろうとする方向を持つ〉。そしてこのような〈矛盾〉が〈無矛盾〉であろうとする方向によってつくられる道こそまさに〈時間〉の流れにほかならない。そこでは〈その行く先が未来であるのではなく〉それをわれわれが〈未来と呼んでいる〉のにすぎないのである。時間とはいわば〈矛盾が無矛盾になろうとするもっとも自然な道〉いやもっとも自然な「さわ道」なのである。 |
「……ほれ、さわの下さ廃れてしもうた木小屋があったんでろ」
「廃れた木小屋……」
「ンだ。あれだばにんぜん(仁左ヱ門)の木小屋いうて、いまのにんぜんのじさまがのう」
「縊れたんですか、あそこで」
わたしにはなんだかあの廃れた木小屋に、すでに不吉めいたものがあったように思いだされて来るのですが、
「それを見つけておろしたよそえんのじさまも、よそえんの木小屋での」
「げんぞうぼう(玄蔵坊)のじさまも、げんぞうぼうの木小屋での」
「…………」
|
|
すなわち、まさに時間という一次元空間によって、〈いかなる空間の矛盾も遅速の矛盾に置き換えられて直進し、この直進によってあらゆるものが整列され、整列されたことによって時間を感じさせて行くように現れては消え、消えては現れて来る〉のである。
だが、時間もまた空間であり道であると言っても、〈道路と時間には、ただひとつ違ったところがある〉。われわれは、つねにわれわれの近傍のなかの矛盾としての原点にいるが、近傍とは定義上境界がそれに属せざる領域である。それゆえ、いかなる道路もその境界に達することはけっしてできないはずである。しかし、〈境界に達することのできる道路が一つある〉と、森敦は言う。 |
「あの月山から、どこに水を引こうというのですかね」
「十王峠の頂さ引いて来て、峠の向こうの山裾さ、水をやろうというんだや」
「十王峠の頂に……。じやァ、天保堰もこのあたりまで来てるんじゃありませんか」
……
「ンだ。それをおらほうさも分けてもろうて、あのさわさ入れとるんだて」
「あのさわに? じやァ、あのさわを辿っても、いつかは月山に行くわけですね」
天沼は近く、しかも依然として遠いが、わたしにはこれがやがてはそこに行く道のような気がするのです。
……
「ンだ。おらたはみな過ぎて月山さ行くというのも、やがては天沼さ行こうというもんだし、どこまで登っても墓原はつきねえもんだ。……」
|
|
すなわち、〈境界に達することのできる〉唯一の通路──それは、まさに〈われわれを幽明境にも導く、時間という道路〉のことなのである。
ところで、この〈幽明境に達しうる、したがって通過しうる唯一の道をなす〉時間が、もし幽明境に直交していると仮定するならば、それは唯一の大円を描いて円環するにちがいない。しかし、もしそれがかならずしも幽明境と直交しないと仮定すれば、無数の円環を想定することが可能になるであろう。そこで、〈ある宗教は時間と呼ばれる一次元空間が唯一の大円を描いて円環するところのものをもって世界とし、ある宗教はその無数の円環するところのものをそれぞれ世界として包含する〉。(もちろん前者はユダヤ=キリスト教であり、後者は仏教を指しているのであろう。)だが、森敦自身は次のように結論する。〈しかし、それがいかなる世界であったにしても、わたしがそこにいるというとき、すでに世界は内部なるものに変換し、境界がそれに属せざるものとして無限なるものとなるから、そこに大小なく対等とされねばならぬ〉と。
すなわち、これが、〈いかなるものからもその意味を取り去ることによって構造し、構造することによって意味を見いだす〉ことによって達せられた森敦の〈死生観〉にほかならない。すなわち、ここに〈意味は変容して宗教となる〉のである。 |
* |
あえぎあえぎじさまのあえぎを聞きながら、一歩も歩けぬその一歩を踏んでいると、またかすかな木霊がし、それが次第にハッキリして来るのです。
「さわですかね、ここも。なんだか、またおなじところに来たような気がしますね」
「ンだ。このさわを降りれば、すぐげんぞうぼうの木小屋ださけの」
「げんぞうぼうの…」
「ンだ。お前さまもおらほうの月山も見たもんだ。おらの杖を貸してくれっさけ、ここらでさわ道を戻るんだて。……」
……
「下りは下りで楽ではねえだかし、お前さまもわァの目で見たものをガッチリ背負うて戻るんだ。……」
|
|
| はたして私自身、自分の目で見たものをガッチリ背負って戻れるかどうかはなはだ心もとありません。いや、自分が見たものが一体何であったかも、本当は定かではないのです。だが、『意味の変容』から聞こえて来る森敦の声は、「ふたたび会わずに終わりながらふとその言葉を思いださせる人」の声のような不思議な響きをもって私には聞こえて来ることだけは確かな事実にほかありません。 |
|
|
| ↑ページトップ |
| 書評・文芸時評一覧へ戻る |
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 |
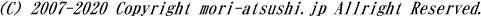 |