| 069 森 敦著「われ逝くもののごとく」を読む 休むことなく練りあげつづけた論理 前例を見ない現代的小説 著者の到達しつつある全存在を投入 |
||
| 小島信夫 | ||
| 出典:週刊読書人 昭和62年6月22日(月) | ||
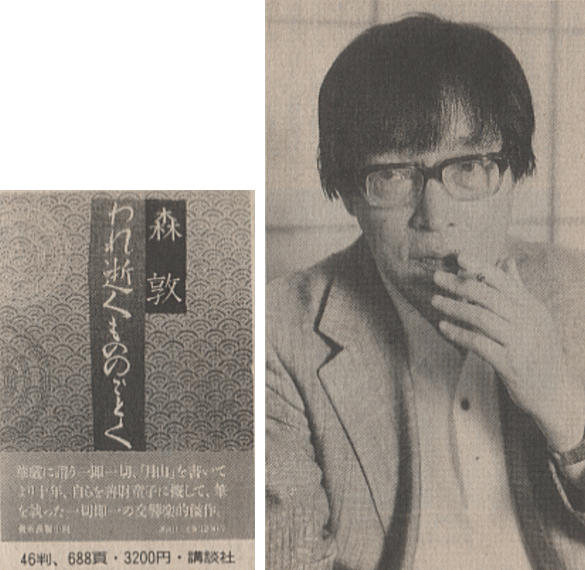 |
||
| 森敦氏の新著『われ逝くもののごとく』が刊行された。これは、「群像」に三年にわたって連載された一六〇〇枚の大長編である。文壇デビュー作『月山』と同じく山形県の庄内地方を舞台に、さまざまな登場人物を通して人間の生、死を問いかけるこの小説をマルケスの『百年の孤独』のようだ」と評する小島信夫氏に書評を寄せてもらった | ||
| (編集部)
|
||
|
||
| 前に「月山」が発表されたとき、私は自分が森さんのことをほとんど知らなかったということを知った。あれから十何年になるが、『われ逝くもののごとく』を読むと、こんどもまた、森さんのことを全くといっていいほど知らなかったということが分った。 「月山」の舞台になった注連寺は、今から四、五年前に森さんに案内していただいた。私がそれまでにこの寺のあたりを一度や二度訪ねたことがあったとしても、私は「月山」を読んで森さんのことは何も知らなかったと思ったのではないだろうか。 こんどの作品が出て、私が森さんのことを全く知らなかったような気がする、と驚きを洩すと、森さんの返答は、次のようであった。 「だいたいあなたの知っているところや、知っているような人が出てきているだけですよ。それにみんな実在で、あんなような人がいて、みんな死んでしまったのです。じっさいにあったことを書くと、そこのところは、ふしぎにウソくさく見えるとは、困ったものです」 とはいえ、これは綿密に計算されたフィクションである。たしかに私は酒田の柳小路も、吹浦も、いっしょに散歩した。森さんは鳥海山麓の大物忌神社のそばの家に夫人と住んでおられ、夏のことだったので、森さんといっしょに海で泳いだ。森さんと、吹浦から象潟へ汽車で出かけたときのこともおぼえている。またいっしょに遥か沖合に浮かぶ飛島も見た。夫人の家がいかに大きな地主であったかということ、その父上がケンブリッジ大学に留学しておられたということも以前から何度もきいていた。それから夫人の母上にも酒田でお会いしたことがある。 さっきもいったように注連寺もその下の村も、背後の山もミイラも、羽黒山も湯殿山も知っている。すべて森さんに案内していただいたところであり、そのとき、ある程度の説明もうかがった。 たしかに加茂や大山や西目などは知らないが、私が全く森さんを知らなかったと思ったのは、そういう材料になりそうな個々のことよりも別のことであるようだ。こんどは「月山」の場合よりも一層そうかもしれない。 |
||
|
||
| 森さんは『意味の変容』『マンダラ紀行』のようなエッセイを、長年の探究のあとで本にされた。「月山」の時にもこういうものにあらわれている森さんの、この世の論理というものを駆使して、月山という山ふところに抱かれた注連寺やその周辺の村を舞台にして小説化された。こんども月山は庄内地方の人々の死霊の集るところという山であるのだから、厳然と存在しているが、鳥海も屢々姿を見せ、もっと広い地域にわたっている。加茂が中心で、大山、吹浦、酒田、鶴岡などあらわれ、人物たちの道行が小説世界を縦断し、横断する。森さんのよく口にされる、俗信が人々にからみついている。龍神様のお礼とか、あねま屋(遊女屋)とか、白痴で聖なる扱いをうけるヤッコのような人物も、登場し、「月山」でも大きな役を演じた闇洒運びやら税務署のことなども話題になる。念入りに屍体を焼く場面も、そのための薪をはこぶ場面もある。ドストエフスキーの『白痴』や『カラマーゾフの兄弟』などを思い浮かべることもできるが、これは庄内地方だけのことではなく、いずこにおいてもこの通りだった。 犬を連れた西目とアダナされる、ふしぎな智恵者も登場する。といっても噂ばかりで、人物そのものは姿を見せず、どうもこの小説世界を動かしている中心でもあるかのようで、「われ逝くもののごとく」という文句は、この影の存在から伝播し、みんな題目のようにとなえはじめるのだったと思う。といっても、当然ながらあらゆる題目を唱えるときとおなじで、本気でもあり、本気でもない。西目が姿を消したあと、彼の犬もこの題目でよばれながら祭りの山を歩いている。この西目からは何か分身の如き紳士が出現していささか読者をケムリに巻くかの如くである。ケムリに巻くといえば、文字通りそうなのが、怪物の善念大日様で、真言秘密を地で行こうとしている男で、どうも西目と張り合おうとしている気配が見える。「あねま屋」の遊女あがりの女を妻にしている女好きとみなされている船主の親方もいる。そうしてこの親方が気にしているのは、北氷洋へ連れて行きそびれているうちに戦死させてしまった、若者のことだ。この若者と年上の女房との間に一人の少女がいる。この若者の出征とその死から小説ははじまる。この死が最初の死である。 私が思い浮かべるままに漫然と書きつらねてきたが、若者の父母といっても文字通り爺婆であるが、彼らのこともふれなければならない。爺さんは息子の戦死の報らせのあと、大分たってから、ひそかに注連寺へやってくる。途々鶴岡の紙屋の女主人やら、「神さま」を訪ねたりして辿りつく。鉄門海上人のミイラは出はらっていて、代りに善念大日様がいる。 私には登場する女性群が忘れられない。その半数は遊女であるか、遊女であった女である。すなわちアコガレの的の女、悪女、親方の女房となっている堪える女。「神さま」もこれまた「あねま屋」にいた女である。サキという少女は鬼女と思われている女といっしょに西目のいる洞窟を訪ねている。至るところに出没するのがサキである。この少女は今も生きていて、森さんはあるときその消息を知ったということだ。 |
||
|
||
| そして…… 「そうですね、一口でいうと、この小説は、マルケスの『百年の孤独』みたいなものだ、と人にいっているところです」 と、私が森さん自身にいったところ、森さんはとっさに「〈善男善女〉という意味ですか」といわれた。私はそこで、「そうです」とこたえた。 この小説には〈善男善女〉というコトバが度々みんなの口の瑞にのぼる。もちろん登場人物すべて善人善女である。そのことをいうための小説といってもいいくらいだ。 「月山」を読んだときもそうだが、この小説を読むと、森さんが何を考え、何を見、何を聞いていたかということがまざまざと分る。そしてどういうわけか、そのありふれたことが、私を驚かした。森さんの練りに練ってこられた理論は、どんなものかということは、森さんのエッセイを読めば分る。ある人々は、このエッセイこそが森さんの私小説に当るものだ、といったこともある。 ところが『われ逝くもののごとく』を読むと、森さんは着々と、その小説を計画し、しかるべき時機が到来するのを待っていたのだ、という気がする。誰もそのことに気づかなかったのだが。その間輪理そのものを練っていたのかも知れないが、むしろ小説の材料は論理を柔軟にし深めつつあったのではないか、と思える。そのことを考えると悩ましいほどである。 森さんは、色々な人々と応接しているとき、相手を活気づけたり我に返らせたりする魅力的なことがいえる人である。それは強力で優しく明るく、救いの気配がある。気がつくとその奥に、森さんの論理があることが分るというふうである。作者はタクトを揮って、文字通り交響曲を展開してきたが、登場人物への接し方には、私が今のべたようなものが一様に感じられる。小説の分り易さもこのことと関係があるのであろう。論理々々というが、作者の論理は小説論というようなものではなくて、それでいて小説化されたとき、いよいよ小説を何か本来の小説のあるべき姿にすることができるという不思議な性質のものである。 この小説がだいたい終戦直後の庄内地方を扱いながらも、時空をこえた日本そのものだという思いを抱かせることを知ってもらいたい。この三、四年間の現在において、七十歳代の一年々々をこえながら到達しつつある全存在を投入して出来たものゆえ、しかも作者が休むことなく練りあげつづけた論理によるものであるゆえ、どんなに前例を見ない現代的な小説が生まれることになったかを、知ってもらいたい。 作者が長期にわたり千何百枚を書きつづけ、そのうちに次第に小説が作者を動かし、読者にとっては奇跡と見える物語──まぎれもない──に現前したことを思うと感動せざるを得ない。それから、この小説では方言をきくことなしには一行も進むことがないが(読みづらいことは全くといっていいほどない)、たとえば月山、湯殿山、梵字川、あらゆる名称、人物なども同等の存在であるというふうに私は読んで楽しんだ。 |
||
|
☆もり・あつし氏は作家。旧制一高中退。在学中の処女作を菊池寛に認められ横光利一に師事。のちに太宰治・檀一雄らと同人誌「青い花」創刊に参加したが作品は発表せず各地を放浪。一九七三年「月山」で第七〇回芥川賞受賞。著書に「月山」「鳥海山」「意味の変容」「マンダラ紀行」など。一九一二(明治45)年生。 |
||
|
★こじま・のぶお氏は作家。東大卒。著書に「アメリカン・スクール」「抱擁家族」「別れる理由」「寓話」「静温な日々」など。一九一五(大正4)年生。  |
||
| ↑ページトップ | ||
| 書評・文芸時評一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||