| 077 生命の流れの内の「死」 人間模様 綾なすマンダラ 森 敦著「われ逝くもののごとく」「十二夜」を読む |
||
| 井上 謙(日本大学教授) | ||
| 出典:世界日報 昭和62年7月20日(月) | ||
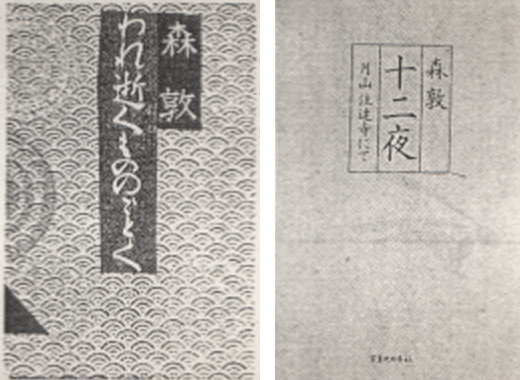 |
||
|
||
| 近ごろ、森敦氏の「われ逝くもののごとく」が話題になっている。『月山』『鳥海山』以来の作品ということもあるがそれだけではない。この作品は昭和五十九年三月から六十二年二月まで『群像』に連載され、単行本にするに当たって、さらに手を加えたすばらしい大作である。舞台は前作と同じく月山や鳥海山を望む庄内であるが、今回は出羽三山に対峙(じ)した西羽黒(荒倉山)の西目(にしめ)と高館山の麓加茂周辺が主要舞台である。というより、前作で点描されていた庄内がこの作品で一層網羅され、総括されたといってもよいほど、氏の目は複眼的で、筆致は非常に緻密である。 登場人物も多い。ここでは少女サキを通して<西目>という人物が物語をリードし、その<西目>がのちに「われ逝くもののごとく」姿を消して、後半になると今度はその顛末(てんまつ)を逝(す)ぎたものに会うため森の供養に詣る<わたし>が語るという筋立てになっていて、しかも、その<わたし>が<西目>と重なるような暗示を仄(ほの)めかせながら終わるという構造になっている。 そこに登場する人々は、さまざまなしがらみを背負って暮らす地元のだれそれであり、その多様な群像はあたかも時の流れに従って何の異和感もないように逝ぎて行く。時代は戦争末期から戦後の混沌期にかけてであるが、世相をあらわす事物はわずかに復員兵や闇米、ジープなどに象徴されている程度で、全体的にはいつに変わらぬのどかな農漁村と地方部市、いわゆる鄙(ひな)に生きる人々の赤裸々な生きざまが展開していく。そして、それらは徹底した「方言」による表現と瑞瑞(みずみず)しいタッチで見事に活写され、庄内地方の生活感が匂い立つようである。森氏特有の「です」「ます」調の語り口と、平明な描写によって謳いあげられる大自然の雄大なパノラマ、その中で豊かな内面を秘めながら坦々と語られていく一大叙事詩は読み手をいつの間にか作中に引き込んでいく。 この物語は圧内の小さな港、加茂に住む貧しい日傭取りの一家によって始められる。年老いたじさまとばさま、その一粒種の息子である漁の手伝いのだだ、魚の背負い商いをしているがが、その間にできたサキ。ところが、これまでの穏やかな暮らしは、だだの出征と戦死によって崩れていく。息子の死を信じようとしないじさまは、心のより所を求めて注連寺へ向かい、やがて岩場で死体となって発見される。その衝撃でばさまが死に、以後わずかの間にこの一家に関わりのある人々の死が続く。 あねま(女郎)屋のお玉、船主の親方のがが、あねま屋の主人とその女房、親方、お葉、吉雄、善念大日様──主要人物が次ぎ次ぎに逝ぎていくドラマ展開は凄じく、それらの逝ぎ方がすべて縊死や事故死であるのも無気味で、それが何気なくという風に語られているのが怕(おそろ)しくて恐い。一見のどかな営みの中にくりひろげられるこれらの不白然な葬れん(みずひき)は残酷である。残酷ではあるが、永遠の時空の世界では逝ぎることは自然なのだ。 |
||
|
||
| 森氏は「月山」で自然の苛酷と慈悲を鮮明に描いたが、「われ逝くもののごとく」では俯瞰(ふかん)された庄内を背景に部分部分を丁寧に掬(すく)いあげ、それを人間模様の綾なすマンダラの世界と捉えているかに見える。この作品が宗教小説とか、万物流転小説といわれる所以もそこにあろう。「月山」では『論語』の「未だ生を知らず、焉(いずく)んぞ死を知らん」という命題で<生>の世界が描かれているが、「われ逝くもののごとく」は氏の言によれば『論語』の川上嘆「逝くものはかくのごときかな 昼夜を舎(お)かず」にその命題を置いたという。とすればこの作品はまさしく「月山」に対応して、生きとし生けるものの生命の流れのうちの<死>の世界を描いたことになる。これこそ氏の創作視座である壮大な世界観の対応と照応による作品構造といわねばならない。 おそらく氏は『月山』や『烏海山』以来、この作品をいつか書かねばならない命題として永く秘めていたに違いない。つまり、「月山」発表時からこの作品執筆までの歳月は氏の内的放浪であり、『月山』『鳥海山』と「われ逝くもののごとく」を以って氏の命題が集大成されたと見るべきであろう。氏の口癖である十年遊ぶことによって、森文学の世界が完結したと思われる。 「われ逝くもののごとく」の発刊に続いて氏の講演記録『十二夜』が出た。文字通り十二夜にわたって氏が語った、七十数年の白身の生涯と人生観宗教観であり、氏の作品の論理と視点がこれを読むと理解できる。大作である前者と打って変わり、こちらは二百八十三ページで、活字も大きくて読み易い。一夜ごとに区切られた文章は、語りの面目躍如としてユーモアに富んでいる。 それにしてもこの二冊が同時に世に出たことで、作家森敦の存在がまた大きくクローズアップされ、「われ逝くもののごとく」はわたしたちに、久々に純文学の真髄を見せてくれた。 |
||
| ↑ページトップ | ||
| 書評・文芸時評一覧へ戻る | ||
| 「森敦資料館」に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ||